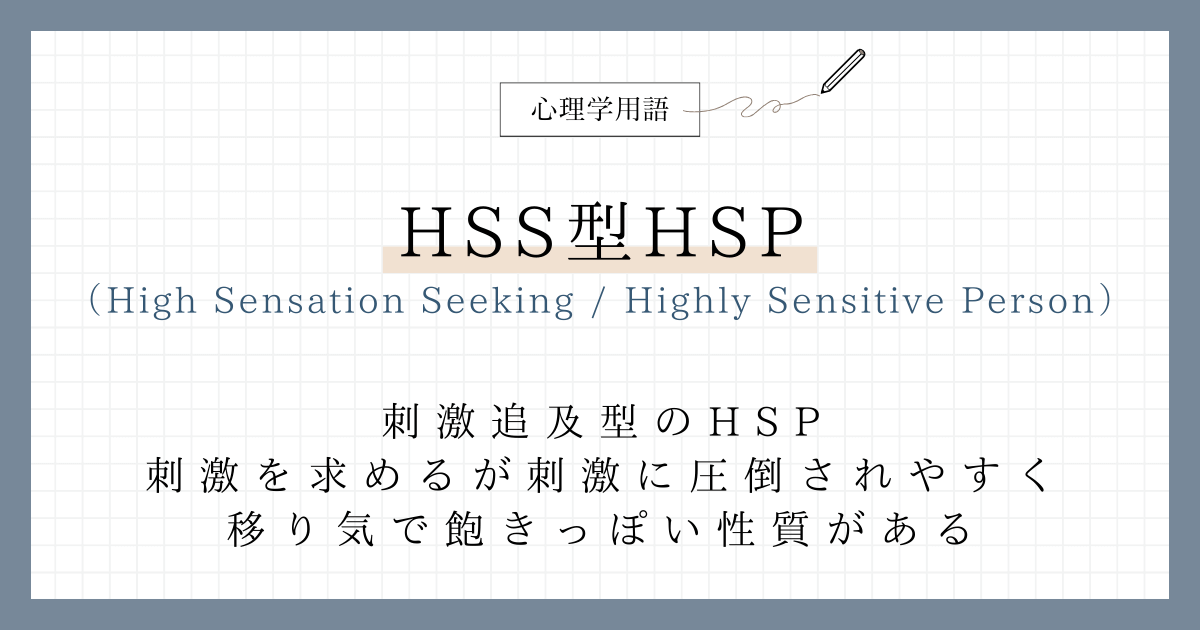HSS型HSPとは
HSS型HSPとは、とても繊細な人(HSP)でありながら、高い刺激を求める(HSS)という特性を持つ人のことを指しています。
- HSS(High Sensation Seeking)
→高い刺激を求める - HSP(Highly Sensitive Person)
→とても繊細な人
もともとは、アメリカの心理学博士エレイン・アーロン氏が提唱していたもので、以下のような矛盾した特性を持つことが特徴です。
- 人と話すのは好きだけど、疲れてしまう
- 新しい刺激を求めるが、すぐに飽きてしまう
- 大胆だが、小さいことを気にして凹んでしまう
- 社交的で外交的に見えるけど、実はネガティブで自信がない
このように、対照的な特性が共存しているHSS型HSPは、人口の6%と少数派であることからも「生きづらい」と感じている方が多くいます。
HSS型HSPの特徴
HSS型HSPは、繊細だけど刺激を求めるという傾向があり、以下のような特徴を持っています。
- 自分自身の内的世界を大切にしている
- 積極的に新しい刺激を求めて行動を起こす
- 刺激を求める反面、疲れたり傷ついたりしやすい
- 外の世界に対して興味を持ちがち
代表的な2つの特徴に関して、深堀りしてみましょう。
HSS型HSPの特徴#1
敏感なのに刺激を求めがち
一般的にHSS型HSPは、変化を好み、新奇なものを求め、それゆえその経験を得るためのリスクは厭わない傾向があります。
目新しい経験やスリルを求めるがゆえに、同じことを繰り返すことはあまり得意ではありません。それと同時に、刺激に圧倒されやすかったり、疲れやすかったりします。
また変化や人の気持ちに気が付き、思慮深い言動をとることも可能です。
こうした対照的な特性を持ち合わせるのが、HSS型HSPの特徴のひとつです。
HSS型HSPの特徴#2
二面性に苦しめられがち
HSS型HSPは、自身の二面性に苦しめられる傾向があります。
HSS型HSPは、新たな情報や発見を求めて自分で調べたり外に出かけたりしますが、そうした探求のなかでときに傷つき、ひどく打ちのめされることもあります。
しかしながらコミュニケーション能力には磨きがかかっているため、本心ではどう思っていようと、人前では飄々と接することができるのです。こうして内面と外面との間に乖離が生じます。
その結果、自身の二面性の調整に苦心したり嫌気がさしたりして、自己否定的な感情を抱きやすくなってしまうケースがあります。
非HSS型HSPとの共通点と違い
HSS型であってもHSPである以上、繊細な人であるという特性は変わりません。例えば、以下のような共通点があります。
・物事を深く考える傾向がある
・他人よりも細かい情報に気が付く
・自分よりも周りや相手を優先しがち
・人から頼まれごとを受けると断れない
・いつも周囲の人や環境に気を遣っている
・においや音、光といった外部の刺激に敏感
・相手の裏に隠れた感情や思考を読み取れる
・受け取る情報が多いため、情報処理に疲れやすい
・映画や文学などの作品に、深く共感、感情移入する
このようにHSS型HSPは、HSP特有の繊細さを併せ持っているため、ネガティブで、傷つきやすく、一方で想像力や発想力、共感力が高いといった傾向にあります。
違いは「刺激を求めるか否か」
HSS型HSPと、一般的なHSP(非HSS型HSP)との違いは「新たな刺激を求めるかどうか」とシンプルで、特性として以下のような差分が見られます。
- 一般的なHSP(非HSS型HSP)
-
- 静かで安定した生活を好む
- 内向的で好奇心はそれほどでもない
- 人との関わりがそれほど好きではない
- HSS型HSP
-
- 刺激的な生活を好む
- 外交的で、好奇心が強い
- 社交的で、人との関わりが好き
こうした傾向もあって、HSS型HSPの人は自分がHSPに属すると気づいていないケースがあります。また反対に、社交的であるがゆえに、周囲の理解を得られにくいケースもあるでしょう。