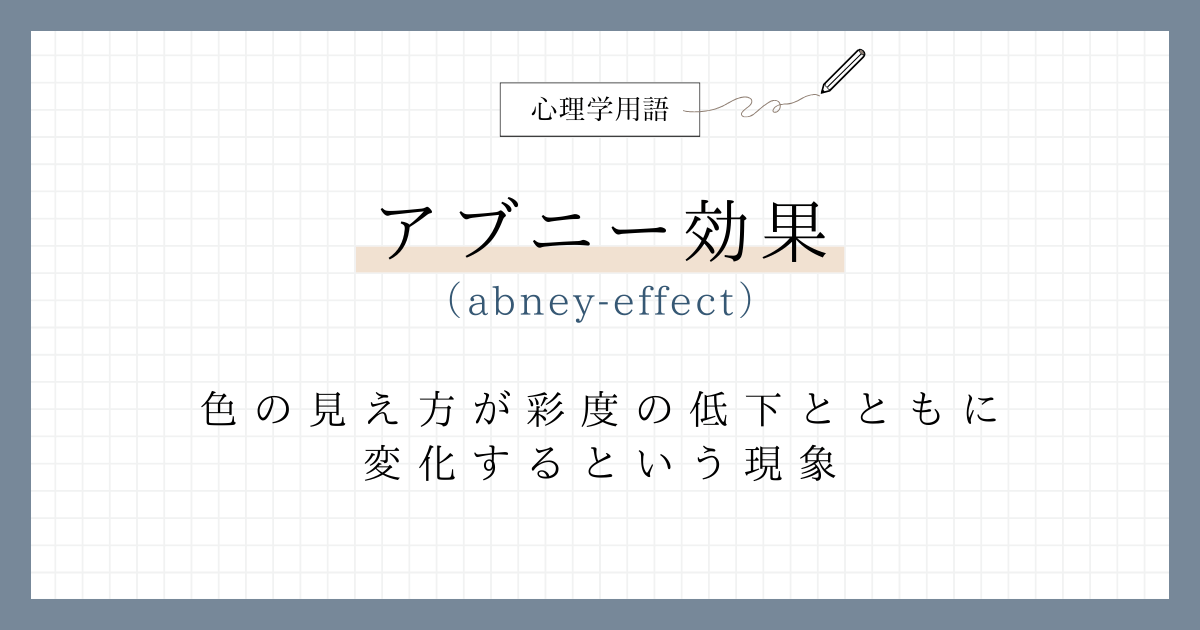アブニー効果とは
アブニー効果とは、色彩心理学の用語で、「色の見え方は、彩度の低下とともに変化する」という現象のことです。
例えば、同じ宝石でも「蛍光灯と太陽光で、それぞれ違う色に見える」といった不思議な現象がアブニー効果に当てはまります。
ここでは、そんな不思議な効果を持つアブニー効果の影響と、関連する色彩心理学の用語を詳しく解説していきます。
「色の三属性」を元にアブニー効果を理解しよう
アブニー効果について知る前に、「色の三属性」について理解しておきましょう。
色の三属性とは、色が持つ3つの属性を指しており、以下の3つがあります。
色の三属性
- 色相
「赤」「青」「黄」といった「色の違い」 - 彩度
「色の鮮やかさ」の度合い
彩度が高いと鮮やかに、低いと落ち着いて見えます。 - 明度
「色の明るさ」の度合い
明度が高いと明るく見え、白に近づいていきます。
逆に明度が低いと暗く見え、黒に近づいていきます。
この「色の三属性」を踏まえ、
アブニー効果「色の見え方は、彩度の低下とともに変化する」の例を説明をすると、
例えば、明るさが一定の状態で、色相が「青」の色に、「白」を混ぜていくと「彩度」が低下し、
そして「彩度」が低下したことで、実際の色相は「青」のままで変化していないにも関わらず、「紫」から「ピンク」へと赤みを帯びて見えてしまうというものです。
このように、色相は変化していないのに、彩度を下げることで色相が変化して見えると現象をアブニー効果といいます。
アブニー効果の由来
アブニー効果は、イギリスの写真家・天文学者・化学者であるウィリアム・アブニー(William de Wiveleslie Abney)が、1909年の英国王立協会紀要において発表したとされています。
アブニー効果に関連する色彩心理
アブニー効果は、色彩検定やカラーコーディネーター検定といった「色に関わる資格」の取得試験範囲となる用語です。
日常で話題になることは滅多にありませんが、このような色の専門家であればかならず押さえておく必要があるでしょう。
その際に、アブニー効果と合わせてしばしば挙げられるのが、下記で紹介する「ヘルムホルツ・コールラウシュ効果」と「ベゾルト・ブリュッケ現象」です。
ヘルムホルツ・コールラウシュ効果
ヘルムホルツ・コールラウシュ効果は、同じ輝度でも彩度の高い色を明るく感じるという現象です。
「輝度(きど)」とは、「照らされた面から反射された光が、ある方向から観測している人の目にどのくらい届いているか」の程度を表す度合いです。
輝度と似た「照度」との違いに注意
照度(しょうど)とは、「照らされた面にどのくらいの光が到達しているか」の程度を表しています。
名前は似ていますが、少し違うので気をつけましょう。
このヘルムホルツ・コールラウシュ効果は、主に絵を描く場面において言及されることが多く、写実的な絵を描く際に意識すべき効果です。
なお、ヘルムホルツ・コールラウシュ効果という名称は発見者の人名が語源となっています。
ベゾルト・ブリュッケ現象
ベゾルト・ブリュッケ現象とは、輝度によって知覚される色相に変化が生じるという現象です。
輝度が高いと黄色と青が、輝度が低下すると緑と赤が優勢に見える傾向があります。
この現象は19世紀にベゾルトとブリュッケという2人がそれぞれ発見したことから、2人の名前をとって名付けられています。
イラストや絵画、マンガや映像制作などに応用できる色彩学の必須知識といわれていますが、人の知覚のあり方について研究する知覚心理学にも関連しているといえるでしょう。
アブニー効果が活用される場面

アブニー効果は、今回合わせて紹介したヘルムホルツ・コールラウシュ効果や、ベゾルト・ブリュッケ現象といった他の効果や現象と同じく、色を扱う職業において覚えておくべき知識といえるでしょう。
実際に、色彩検定やカラーコーディネーター検定では出題対象となっています。
なお、今回取り上げたアブニー効果の関連で紹介したベツォルトブリュケ現象は、絵画やイラストにおいて色を塗る際、特に影響があるとされています。
アブニー効果を知っておくべき職業
主に下記のような職に就いている、もしくは目指している方々は、アブニー効果やベツォルトブリュケ現象、ヘルムホルツ・コールラウシュ効果といった色の知覚に関する心理を知っておくと、スキルの幅がより広がるかもしれません。
- イラストレーター
- アーティスト(画家)
- 写真家
- 映像技術者(映像クリエイター)
- 漫画家
- カラーコーディネーター(カラーリスト)
- 印刷メーカー勤務者
知らないとまったく仕事ができないというわけではありませんが、知っておくとどこかで仕事に役立つ機会もあるでしょう。