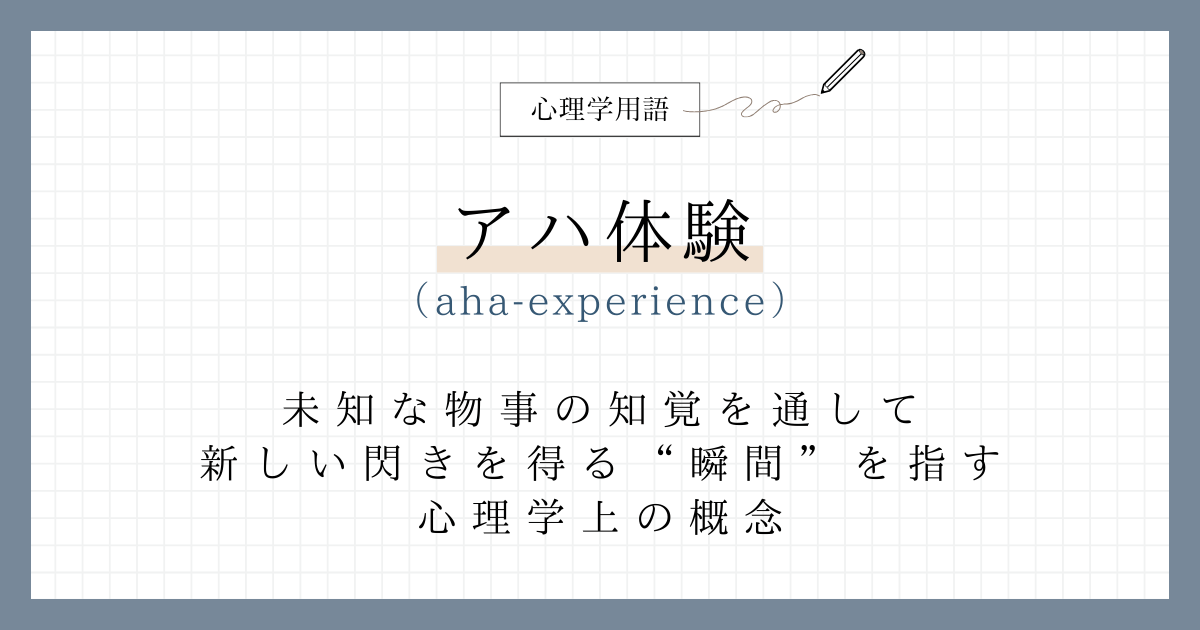アハ体験とは
アハ体験とは、未知なものごとの知覚を通して、今まで全く理解できなかったことや思いつかなかったことが閃く瞬間を指す心理学上の概念です。
例えば、「木からリンゴが落ちる」のを見て、万有引力を閃いたニュートンの逸話が、これに当たります。
なお、本来の語源はドイツ語ですが、文化にかかわらず普遍的な体験のため、何かを理解した際に英語圏で用いられる「a-ha」という言葉も関連しています(「aha! moment」と呼ばれます)。
日本では、脳科学者の茂木健一郎氏が、アハ体験を世に広めたので、知っている方も多いでしょう(提唱者とされることもありますが、実際は異なります)。
また別称ですが、ドイツ語で「Der Groschen ist gefallen(硬貨が落ちる=腑に落ちる)」と表現されることがあります。
今回はそんなアハ体験について解説していきます。
ドイツの心理学者カール・ビューラー(Karl Bühler)が提唱した理論
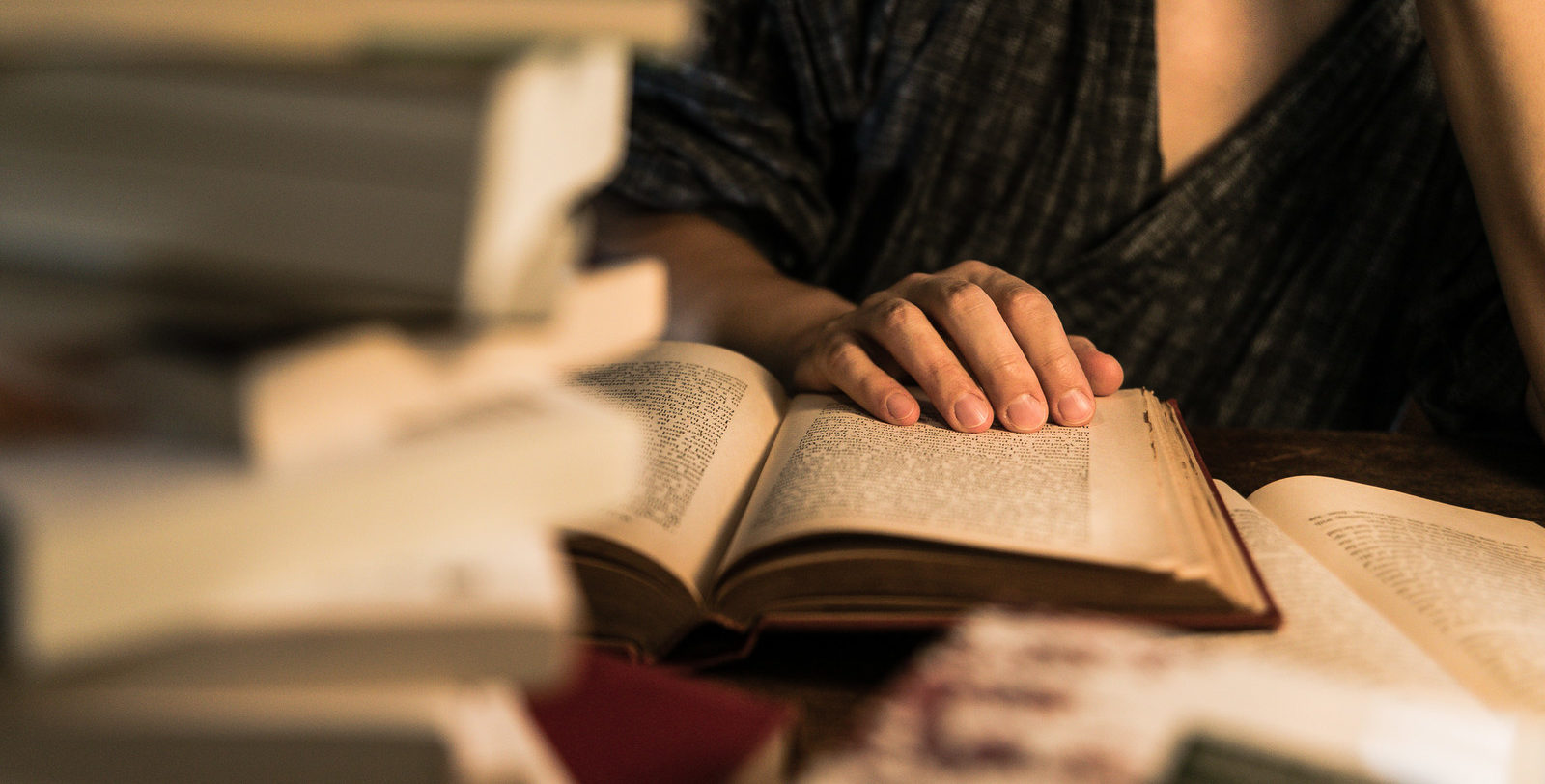
1907年、ドイツの心理学者カール・ビューラーによって、アハ体験が提唱されました。
実際の論文が↓になります(ドイツ語です)。
カール・ビューラーの論文
Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge
アハ体験には以下のような4つの特徴があります。
- アハ体験は、何の前触れもなく突然起こる
- アハ体験によって、知覚した問題はすぐに解決される
- アハ体験は、しばしばポジティブな感情を喚起させる
- アハ体験によってひらめきを得た人は、そのひらめきの信頼性を疑うことなく信じようとする
ただしこれらの特徴はすべて関連したものであり、研究上では1つに結びついています。
なぜなら、アハ体験のような高度な脳内処理は肯定的感情の生起につながりやすく、それによって判断や真偽の洞察が正確になされやすいためです。
また茂木健一郎氏によれば、アハ体験によって脳の神経細胞が活性化して「一発学習」が行われ、頭の回転が良くなり、まるで世界が変わったようになる、とされています。
なお、よくある誤解が「徐々に変化する画像や映像などの変化に気づくこと」です。
これはバラエティ番組によって流布されたものであり、「突然の知覚に寄ってひらめきを起こす」ことが特徴であるアハ体験ではありません。
「アハ体験」の例:間違い探し

アハ体験のもっとも有名な例は、「ニュートンが木からリンゴが落ちるところを目撃して(知覚)、万有引力の法則を発見した(ひらめき)」というものです。
また、「間違い探し」で2枚の絵の違いを発見することもアハ画像です。
「アハ体験」と「ゲシュタルト転換」との混同

ニュートンのひらめきが二度と起こらないことと同様に、アハ体験は、経験したあとにそれを覚えていますが、同じことを再現できません。
カール・ビューラーは、その点を踏まえてアハ体験を提唱していますが、茂木氏の見解はそれと異なり、同じことが再現できてしまうため、厳密にはアハ体験と呼べないという批判もあります。
例えば間違い探しであれば、一度見つけられれば二回目以降はすぐ同じことを再現できてしまいます(間違いを見つけやすくなるということです)。
茂木氏の提唱するアハ体験は「ゲシュタルト転換」と呼ばれる心理概念で、もともと結びつきのなかったバラバラの要素を全体的に俯瞰して見かたが丸ごと変わってしまうというものです。
なお、本記事では茂木氏の提唱内容も俗説としてアハ体験の一部としましたが、この点に留意してください。
「アハ体験」がもたらす効果と再現方法
先ほど茂木氏の言及について触れましたが、脳科学的な見地では、アハ体験によって脳細胞が活発に働くようになり、日常のものごとに対して鋭い感覚を持てるようになります。
しかし、アハ体験は、日常で意識的に経験することは極めて困難です。
なぜなら、「たまたま起きた未知の出来事を知覚する」ことが引き金になっているためです。
ですが、これを解決する方法が例として挙げた「だまし絵」や「間違い探し」などでしょう。
これらは用意された画像や映像を見てだましや間違いに「たまたま」気づくことができるため、アハ体験に近い経験を生み出すことが可能、となります。
もっとも、ニュートンの発明のように世紀の大発見にはならないものの、日常的にいわゆる「脳トレ」をするという意味ではうってつけだといえるでしょう。
「アハ体験」は心を緊張から解き放ち、喜びを与える

「アハ体験はポジティブな感情を喚起させる」と解説したとおり、アハ体験によるひらめきは、心を緊張から解き放ち、大きな喜びを人の心にもたらします。
この例は間違い探しで顕著に現れるでしょう。
例えば、最後の1つがどうしても見つからなくてモヤモヤしつつ5分、10分と経過するうちに、偶然小さな違いが目に入ってようやくクリアしたときの
「これか!」という「カタルシス(精神浄化作用)」に似た感覚は、日常ではなかなか味わうことのできない貴重なものなのではないでしょうか。
また、普段からひらめきやすい心の姿勢を育むことは、ニュートンならずともあらゆることからポジティブな発見をし、豊かな感受性を育むことにつながると想像できるでしょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。
アハ体験(Aha-Erlebnis)とは、未知のものごとを知覚した際に、瞬間的なひらめきを起こすという心理学上の概念で、
まさにニュートンの「木からリンゴが落ちる」のを見て、万有引力を閃いたという逸話が、まさにアハ体験に当てはまりました。
なかなか現状では再現することができない特徴があるものの、
もし体験することができれば、脳細胞が活発に働くようになり、日常のものごとに対する鋭さが増し、なにか閃くかもしれません。
そのために、普段通りの日常をただ受け流すだけでなく、より一段深く考えて考察を重ねることが重要なのではないでしょうか。
このページを読んだあなたの人生が、
より豊かなものとなることを祈っております。