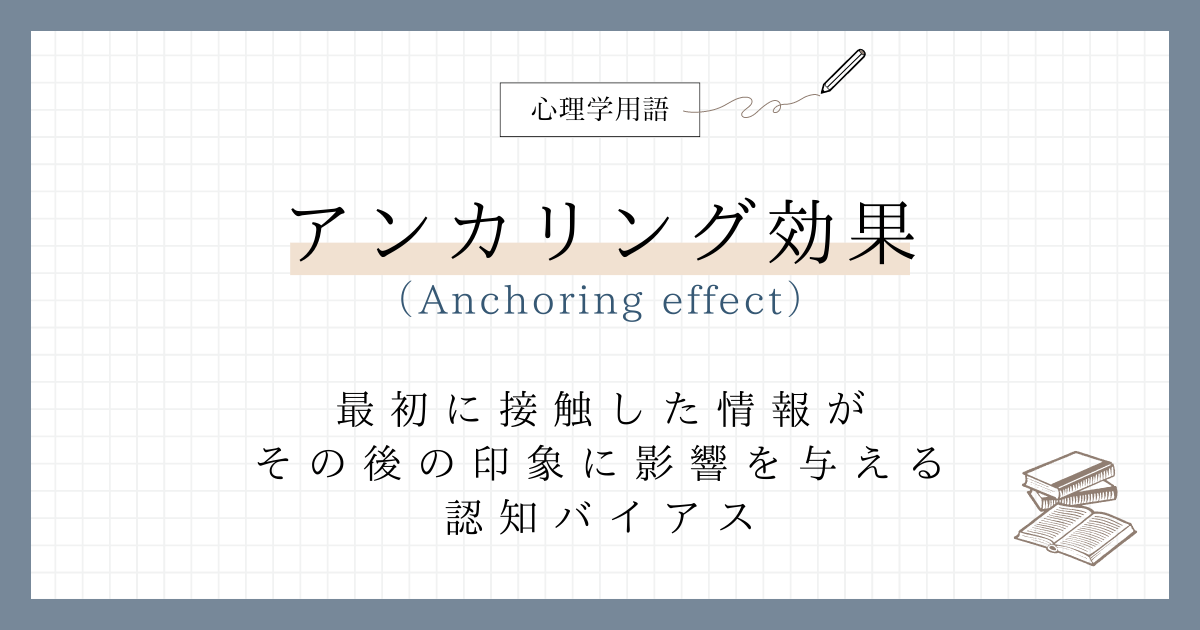アンカリング効果とは
アンカリング効果とは、最初に提示された情報(特徴や数値的なデータ、価格など)が基準となり、その後の評価を左右するという傾向、認知バイアスです。
下記のような値引き表示が典型例ですね。
¥100,000¥80,000- ¥80,000
この最初の提示した判断基準となる情報をアンカー(和訳:船の碇)と言います。他にもいくつか例をあげてみましょう。
アンカリング効果の具体例
値段
- セールや値下げ(アパレルなど)
- 値下げ前提で「見積もり金額」を提示する
- 店舗入口に高価な商品を配置(指輪店など)
評価
- 転職活動における「前職の年収」
- 普段、素行の悪いヤンキーが、たまに良いことをすると素敵に見えるギャップ
- 評判の良い飲食店だと、相応の期待をして味わいながら食べますもんね
このように、最初に提示されている評価や値段が、その後の認識や意思決定を左右する基準になります。
 運営者
運営者なにかを評価するときには基準が必要ですからね。その基準より、良いか悪いかで、感じ方が変わるのがアンカリング効果です。
補足:認知バイアスとは
認知バイアスとは、常識や固定観念、また周囲の意見や情報など、さまざまな要因によって、誤った認識や合理的でない判断を行ってしまう認知心理学の概念です。
アンカリング効果の実証実験
アンカリング効果では、エイモス・トベルスキー(Amos Tversky)とダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)が1976年に、2つの実験を行っています。
アンカリング効果の実証実験A
異なるアンカーを提示した実験
この実験では、2つのグループに分けた被験者に対して「国連加盟国の中でアフリカ大陸にある国の割合は『○○%』より大きいか小さいか」という質問し、具体的な数値を回答させ、比較しています。
- 「65%」より大きいか小さいか
→回答の中央値は「45%」になった - 「10%」より大きいか小さいか
→回答の中央値は「25%」になった
上記のように、最初に提示した数字(65 or 10)に大きく引っ張られる回答結果になりました。
アンカリング効果の実証実験B
異なるアンカーを提示しない実験
この実験では、被験者を2つのグループにわけて、数字を掛け算した結果を5秒以内に推測させました。
- 8×7×6×5×4×3×2×1と提示
→回答の中央値は2,250 - 1×2×3×4×5×6×7×8と提示
→回答の中央値は512
(ちなみに正解は40,320です)
上記のように、並べている数字は同じでも、最初に大きな数値を配置した場合の方が、回答として大きい数値が返ってくる結果となりました。
アンカリング効果を説明する理論
ここでは、アンカリング効果のメカニズムを解説していきます。認知心理学における研究では、2つの説「数的課程説」と「意味的課程説」が提唱されています。
アンカリング効果を説明する理論#1
数的課程説(不十分な調整説)
まず、人は「特定の数値」を推測するとき、最初に提示される数値(アンカー)を基準として、より適切と思われる数値に向けて調整を行います。しかし、この調整が不十分であるというものです。
例えば、ある商品の価格を推測する場合、まずは最初に提示された価格(アンカー)からスタートして、価格を上下に調整するはずです。
実際、推測のスタート地点が低いのに、高い数値をいきなり推測する人は少ないはずです。
この「不十分な調整」は、人が持つ先入観やバイアス、情報処理の限界によって生じます。



時間が限られるほど、アンカーから離れた数値の推測をすることが難しくなりますね。
アンカリング効果を説明する理論#2
意味的課程説(選択的アクセシビリティ説)
意味的課程説では、人々が最初に与えられたアンカーに基づいて、関連する情報や思考を選択的に取り出しやすくなるという背景から、アンカリング効果を説明しています。
例えば、小学校の先生が「このバケツには何リットルの水が入っていると思う?」とバケツを見せながら「2リットルくらいかな〜?」と最初に言ったとしましょう。
すると生徒たちは無意識のうちに「2リットル」に関する情報に自然と引き寄せられます。それこそ「2リットルは大きいペットボトル1本」といった情報を思い出したり。
このように、アンカーによって、特定の情報や思考が活性化された結果として、最終的な判断や推測が影響されるというわけです。



一度出されると、しばらくは「2リットル」から連想されるものを中心に考えますもんね。
認知バイアスを緩和するポイント
認知バイアスの原因は「経験や直感からくる思い込み」にあるので、対処すれば、一定は軽減できます。※ただ、人間である以上、全てを防ぐのは不可能です。
- 認知バイアスへの理解を深める
- 認知バイアス診断で思考の癖を知る
- 批判的に考え、第三者の意見を取り入れる
順番に解説していきます。
認知バイアスを緩和するポイント①
認知バイアスの理解を深める
まず、認知バイアスの存在を知らなければ、防ぎようがありません。あなたがAIではなく人間である限り『なにかしらのバイアスはある』という認識を持ちましょう。



仮に「自分だけは大丈夫」と思っているのであれば、それこそがバイアスです。
認知バイアスを緩和するポイント②
認知バイアス診断で思考の癖を知る
次は、自身が「どういったバイアスを持ちやすいのか」という思考の癖を知ることをおすすめします。ミイダスで診断可能ですね。(記憶だと、無料でできる診断は唯一のはずです。)
▼ミイダスで診断してみよう
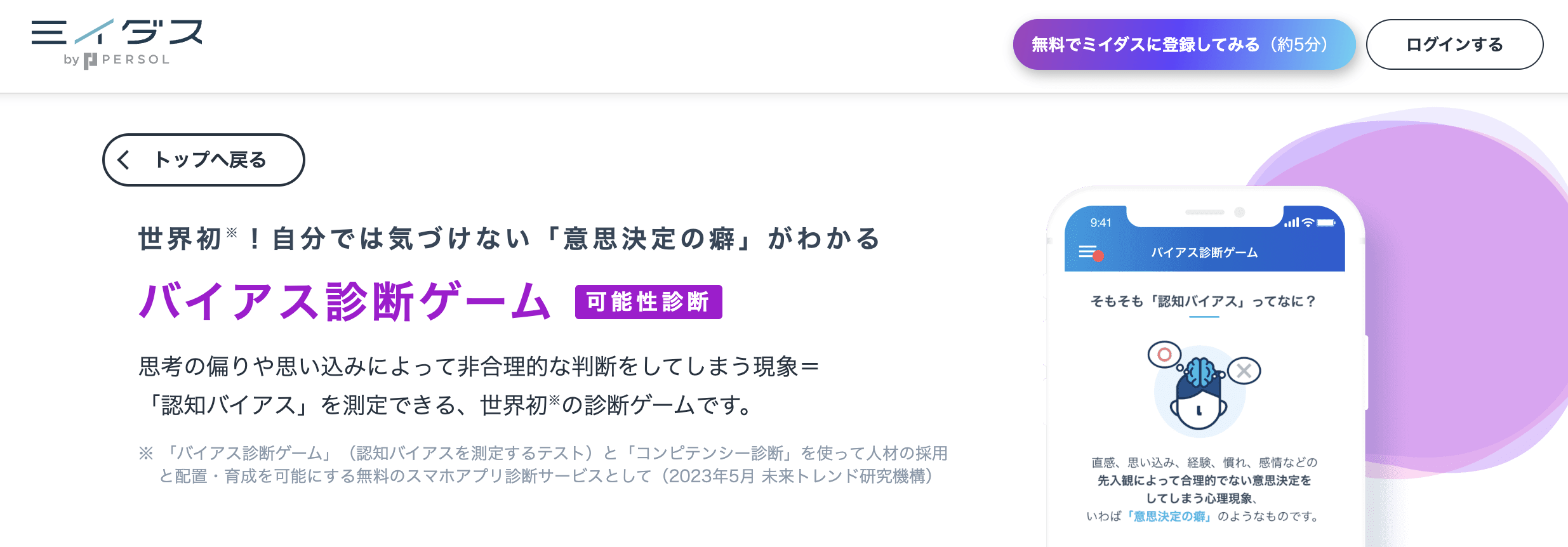
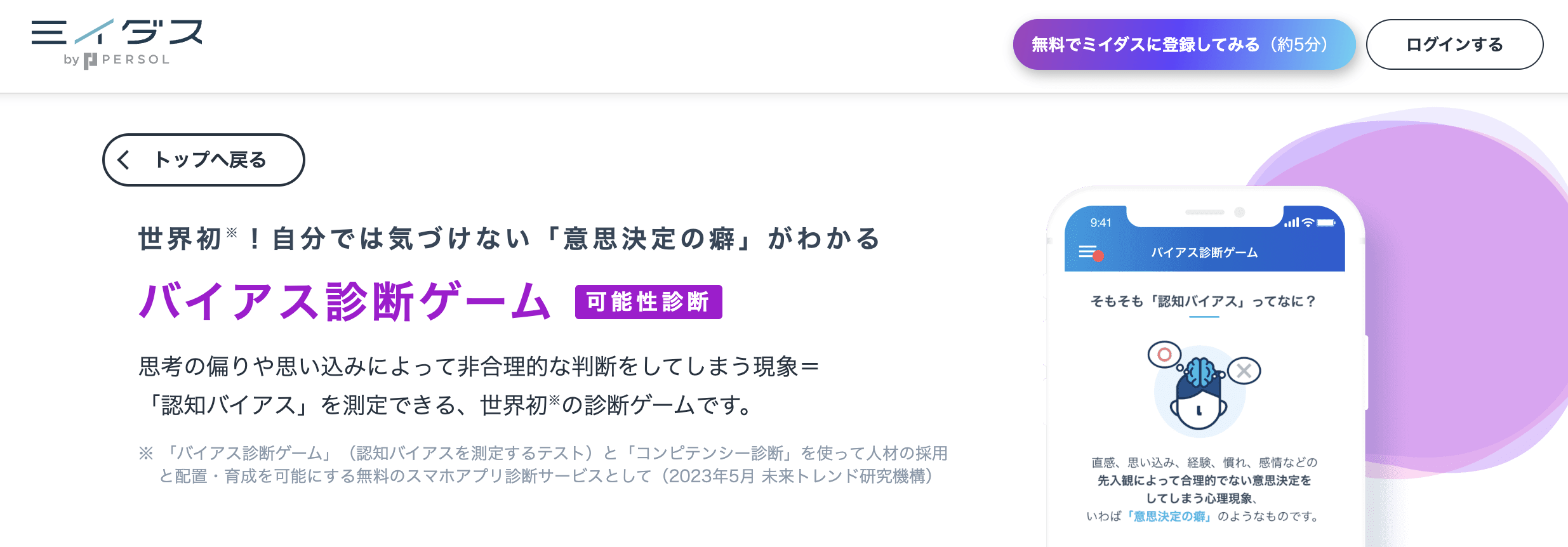
ミイダスはもともと、転職市場価値を診断できるアプリですが、「バイアス診断ゲーム」をはじめとした心理学系の診断がいくつかあります。誰でも登録できるので、興味があれば試してみてください。
認知バイアスを緩和するポイント③
批判的に考え、第三者の意見を取り入れる
認知バイアスに陥るのを防ぐために「なにごとも疑ってかかる」「自分と異なる意見を取り入れる」ことが重要です。 例えば以下のようにですね。
- 何が事実で、何が解釈か
- 別の観点から考えると、解釈は変わるか
- どのような反対意見があるか
このように、さまざまな角度から複眼的にとらえることができれば、認知バイアスに陥りにくくはなります。いわゆるクリティカルシンキング(批判的思考)というものですね。



第三者の意見を取り入れるのもおすすめです。利害関係がなく、都合が悪いことも率直に伝えてくれる相手にしましょう。
他の認知バイアス【一覧と具体例】
認知バイアスは『様々な理由で認識が歪んでしまい、事実を正しく認識できずに不合理な(事実でない)認知をしてしまう傾向』を総称したもので、いくつもの種類があります。
| 認知バイアス | 説明・具体例 |
|---|---|
| 正常性バイアス | 自分に都合が悪い事実を信じない、現実を見ない 例:連帯保証人になったら友達が音信不通に。でもきっと大丈夫! |
| 確証バイアス | 自分の信念を裏付ける情報を探し求め、それ以外を見ない 例:大好きな彼氏はココが良い!ココも素敵! |
| 生存バイアス | 現在、生存している事例(成功例)しか見ない 例:成功した起業家を分析して、失敗例を見ない |
| 後知恵バイアス | 過去の事象に「それは予測可能だった」と勘違い 例:そのじゃんけん、チョキなら勝てるってわかったよね? |
| 自己奉仕バイアス | 自身に好意的な認識を持ちやすい傾向がある 例:成功は自分の能力が高いおかげ。失敗は外部環境のせい |
| 自己中心性バイアス | 自分を基準に、他者の心情や認知を推察する 例:自分の価値観を押し付ける、相手目線で考えられない |
| 感情バイアス | 感情的な好き嫌いが意思決定に影響を与える 例:性能は悪いが、つい好きなブランド商品を買ってしまう |
| 投影バイアス | 自分の好み、感情、価値観を他人に投影して認識する 例:まわりの人も自分と同じ意見、感情だと思い込む |
| 一貫性バイアス | 他者の1行動に一貫性があると思い込む 例:さっきナンパしてきた人、絶対いろんな女子に声かけてるよね |
| 保守性バイアス | 新しい情報を取り入れて、考え方や行動を変えることに躊躇する 例:革新的な新技術が出ても、使わず、従来のやり方に固執する |
| バーナム効果 | 曖昧な特徴でも、自分に強く該当すると思い込む効果 例:占い師「あなたは◯◯な人間ですね」→そうかも! |
| ハロー効果 | ある事象への評価が、他の目立った特徴に引っ張られる効果 例:清潔感がない人は、仕事もできなさそうだし性格も悪そう |
| ダニングクルーガー効果 | 能力の低い人ほど自分を高く評価しやすい心理効果 例:もうこのゲームはコツ掴んだな!オレ最強かも! |
| コンコルド効果 | 過去の投資を惜しんで、追加投資をやめられない効果 例:UFOキャッチャーを取れるまでやってしまう |
| バンドワゴン効果 | 多くの人々が支持する意見や行動に信頼感を抱く効果 例:子どもが、他のみんなと同じオモチャを欲しがる |
| フレーミング効果 | 同じ情報でも伝え方によって受け取り方が異なる効果 例:電池残量が「残り50%もある」と「残り50%しかない…」 |
| アンカリング効果 | 最初に提示した情報が基準となり、その後の認識に影響を与える効果 例:商品の値下げ(大きく下がっているとお得に感じますよね?) |
| アンダードッグ効果 | 不利な立場の負け犬を同情・応援したくなる効果 例:バレンタインに縁がなさそうな人にチョコをあげたくなる |
| クレショフ効果 | 2枚の関係ない写真に、意味的な繋がりを感じる効果 例:「野菜」「不機嫌な人の顔」→野菜が嫌い? |
| バックファイア効果 | 信念に反する情報を提示すると、裏目になる効果 例:大好きな彼氏を批判されると、かえって愛情が増す、守る |
| 真理の錯誤効果 | 繰り返された情報を真実だと思い込む効果 例:「最高品質」と効果を連呼するTVCMを繰り返しみて信じる |
| リスキーシフト | 集団の中だと、よりリスクの高い意思決定をしやすくなる効果 例:赤信号、みんなで渡れば怖くない |
| 錯誤相関 | 二つの事柄に、相関関係があると錯誤(思い違い)すること 例:雨男/雨女、アイスの売上と溺死数 |
| 根本的な帰属の誤り | 他人の行動の場合、外部要因を過小評価してしまう傾向 例:遅刻の原因で、状況要因を考慮しにくい(性格のせいにしがち) |
| アロンソンの不貞の法則 | 知らない人からの褒め言葉を、より嬉しく感じる法則 例:家族よりも、他人から認められると嬉しい |
| 代表性ヒューリスティック | ある対象の判断を、既知概念の代表的特性との類似性で判断する 例:「尻尾が丸い動物」→「うさぎかな?」 |
| 可用性ヒューリスティック | ある判断をするとき、すぐに思い出せる事例や情報から判断しやすい 例:馴染みのものや、人気ブランド、記憶に浮かぶ商品を選びがち。 |
| 選択のパラドックス | 選択肢が多ければ多いほど不満を感じやすくなる 例:レストランのメニュー、料金プランの種類など |