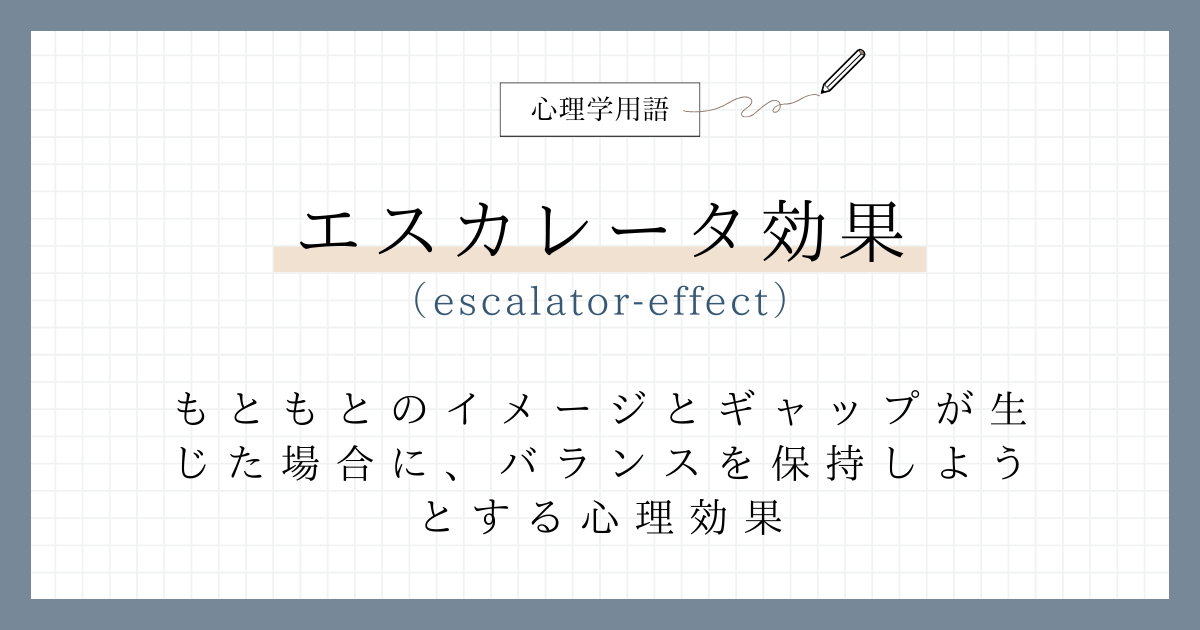エスカレーター効果とは
エスカレーター効果とは、もともとイメージがあるものに対してギャップが生じた場合に、バランスを保持しようとする心理効果のことです。
例えば、何かと自社商品を買わせようとしてくるイメージの営業が、自社商品を売ろうとせず、「御社にはこっちのがほういいですよ」と他社商品を推薦してきた場合、好感度が上がる、などです。
また、エスカレーター効果の元々の由来は、止まっているエスカレーターを上り下りする際、足が重いと感じる現象のことを指していて、これは、普段エスカレーターを乗り降りする際は、脳が「エスカレーターは動くものである」と認識しているためであり、「バランスを保持しようとする」指令がでてしまうためとされています。
この「バランスを保持しようとする心理効果」を取ってエスカレーター効果とされたのです。
エスカレーター効果の具体例

エスカレーター効果は具体例が浮かびにくいので、もう少し例を挙げます。
①安く売るがなぜかフォローも手厚い
お昼どき、弁当が300円で売られていたとします。それを聞くと、中身は大したことないだろう(おかずが揚げ物1、2種類くらい)という意識が頭をよぎることはないでしょうか。
しかし実際はシャケや漬け物、煮物だとたくさんのおかずが入っていたら、まさに「思い込みによる違和感」が生まれる瞬間です。
そしてこれは家電量販店のスタッフのように「いい意味での裏切り」を生み、弁当屋さんに対してよい印象を抱くようになります。
② 契約前より契約後のほうが充実したサポートを受けられる
企業における大きなサービス導入契約に関しては、契約前の営業スタッフは売り込みに熱心ですが、いざ契約すると放置されるといった場面も少なくなく、実際そのような思い込みも少なくありません。
ここで、契約後も営業スタッフがサポートスタッフと連携して「お困りごとはありませんか?」「順調に導入できていますか?」「不明点があれば遠慮なくお問い合わせください」と連絡をより密にしてくると、「この営業スタッフは商品が売れたあとも顧客のことを考えてくれている」という意識から、やはりいい意味で裏切られることになります。
なお、直接連絡でなくとも定期的なメール連絡、個人的なセールスレターなどによって同様の効果が期待できるでしょう。
エスカレーター効果の活用方法
自分が商品やサービスを販売するスタッフになったときにはこれまでの例は非常に使えますが、より私的なものへと転換していきます。
服装を変える

職場でいつもスーツを着ている人が会社外で同僚と会うときに(その人を意識していたとします)、あえて私服を着ていくことで「いい意味での裏切り」を起こすことができますよね。
また、普段はキレイ目のコーディネートをしている人がラフな格好で現れた場合も、その人を強く印象付けるきっかけになるでしょう。
思考パターンを変える

デートにおいて、行き先を「相手に任せる」という人が「今日は自分に任せて!」と言ったとしたら、なんとなく頼もしさを感じませんか?
このように、いつも受け身の人が主体性を持つように意識を変えたり、それを行動に移して周囲の人に驚かれたりすることも、いい意味のすれ違いです。
表情を変える
いつも仏頂面をしたコワモテの男がふとした瞬間に見せる笑顔の「ギャップ」が魅力的というのもエスカレーター効果の例です。
逆にいつもニコニコしている人が真面目な顔をする、例えは古いですが「昼間のパパはちょっと違う」というギャップも、「こういう一面もあるんだ」とまわりを驚かせ、印象を強めるよいきっかけとなるでしょう。
いい裏切りが好印象を生む
これまで紹介したように、エスカレーター効果によって「いい意味での裏切り」は受け手にとってよい印象につながりやすいものです。
ただし、ギャップが「いい意味」になるかどうかは受け手の感覚次第でもあるので、コントロールしにくい面もあります(私服などは似合っていないと逆効果になりますよね)。
それでも今回挙げた例は、比較的「いい裏切り」を見せる好例なのではないでしょうか。
したがって、今回のようにエスカレーター効果をうまく使うには、それによって相手がどう反応するかを想像してシミュレートしておくことも非常に重要といえるでしょう。
エスカレーター効果のメカニズム
エスカレーター効果が生じるのは、脳からの「バランスを保持しようとする」指令と、実際の「エスカレーターの動き(普段と異なって停止している状態)」との間にギャップが生じるためです。
これは、普段エスカレーターを乗り降りする際は、脳が「エスカレーターは動くものである」と認識しているため、
たとえエスカレーターが止まっていてもエスカレーターを目の前にすると動いていると誤った認識をして、脳からの指令によって体がバランスを保とうとするためです。
このように、人間は脳から指令を受けて、歩いたり走ったり、今回のようにエスカレーターを上り下りする際に、無意識にバランスを維持しようとする働きを持っています。
そしてこの「無意識のバランス調整」が、このような違和感を生むわけです。
エスカレーター効果の一般的な解釈
エスカレーター効果はその内容が転じて、「思い込みによって生まれる違和感」という意味で、エスカレーターの上り下り以外の場面で使われることもあります。
例を挙げると、家電量販店などの接客営業の場面で「スタッフは全員、店頭の商品をなんでも肯定的に紹介して買わせようとする」と思っている節はないでしょうか。
しかしここで「この商品はお客様の用途に合っていないので、正直お客様にはあまりおすすめできません」と言われたら、なんとなく違和感を覚えるはずです。
この違和感がいい意味で自分に対する裏切りを生み、スタッフに好印象を受けたり、別の商品を紹介された際に肯定的に受け入れられたりするようになります。
最後に
エスカレーター効果とは、もともとイメージがあるものに対してギャップが生じた場合に、バランスを保持しようとする心理効果のことです。
そして、いい意味のギャップを生むことで、心理的にポジティブな印象を持たせることが可能なので、ビジネスの場で広く活用されています。
このページを読んだあなたの人生が、より豊かなものとなることを祈っております。