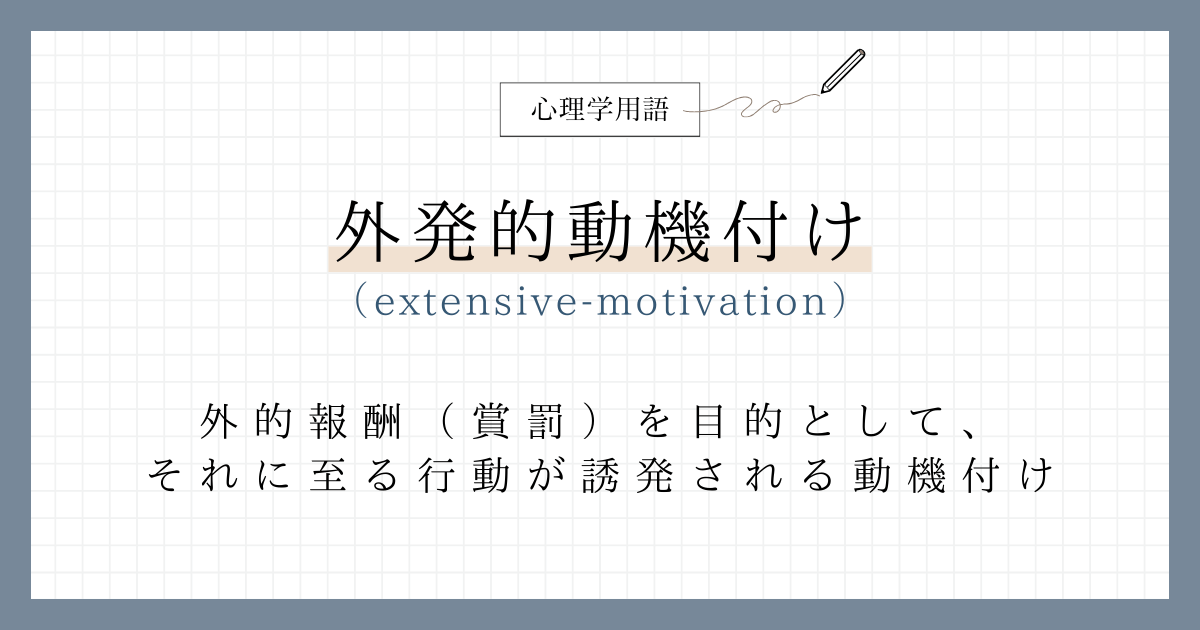外発的動機付けとは
外発的動機付けとは、手に入れたい外的報酬(賞罰)を目的として、それに至る行動が誘発されるような動機付けのことを指します。
いわゆる「飴と鞭」で、以下のような状況が当てはまります。
- 昇進するために努力する
→「昇進する」ことが外的報酬 - 上司に怒られないように営業する
→「怒られるという罰を受けなくて済む」ことが外的報酬 - お小遣いをもらえるから宿題を頑張る
→「お小遣いをもらえる」ことが外的報酬
こういったモチベーションこそが「外発的動機付け」と呼ばれるものです。
内発的動機付けとの違い
外発的動機付けを理解する上で、対称の意味となる「内発的動機付け」の存在は欠かせません。
この「内発的動機付け」とは、結果として得られる賞罰や成果のためではなく、それに向かっていくプロセスそのものや自身の内的報酬(充実感や自己実現)が動機付けになっている状態のことを指します。
- もっとスキルをあげたいから努力する
→「スキルアップの達成感」が内的報酬 - 顧客の笑顔が見たいから営業する
→「笑顔を見ると嬉しいという充実感」が内的報酬
この内発的動機付けは、活動することそのものがモチベーションとなるので、自発的にその活動量が増えていくことが特徴です。
エドワード・L・デシの実証実験
「外発的動機付け」および「内発的動機付け」を理論化したのは、エドワード・L・デシ(Edward L. Deci)という米国の心理学者です。
デシは、人は自分自身の選択で行動でき、自分は自由だと感じているとき、つまり「その行為が行為する人の手中にある状態において、人は自律的にモチベーションを高めていく」のだと主張しました。
補足:当時主流だった行動主義心理学
当時(1960年頃)心理学の世界で主流とされていた「行動主義心理学(その人の感情などは考慮せず、目に見える行動だけに着目した心理学)」とは反する理論として主張されました。
- 罰を与えれば怠けることはない
- 動物に芸を覚えさせるには餌を与えればいい
- 労働者をしっかり働かせるには十分な報酬を与えればいい
実験内容
まず、学生を2つのグループに分け、当時流行っていた面白いパズルを解かせるまでは同じなのですが、それぞれに違った条件を提示します。
<Aのグループ>
パズルを解くと金銭的報酬(1ドル)を受け取れる
<Bのグループ>
バズルを解いても金銭的報酬(1ドル)は受け取れない
両グループに、30分間パズルを解かせた後、監督官が「これで実験はおしまいです。データ入力作業があるため離席します。」と言い残し退室することで、残された学生たちに“自由時間”を与えました。(パズルのほかに、雑誌なども置かれていて、好きに時間を過ごせます。)
実験結果
そして、この「自由時間に何をするのか」を見ていたのですが、2つのグループに明らかな差が出ました。Aのグループの学生は、もともともらえていた報酬がなくなることで、あまりパズルに取り組まなくなってしまいました。しかし、Bグループの学生は、比較的長くパズルに取り組んだのです。
これは、パズルをやる理由を、金銭報酬(外発的動機)にすり替えられた事が原因です。元々やってみれば面白いパズルであったとしても、報酬がないとやらなくなってしまうのです。
外発的動機づけと関連する心理効果
ここでは外発的動機づけ、外的報酬と強く関連する心理効果を2つ紹介していきます。
- アンダーマイニング効果
- クレスピ効果
外発的動機づけと関連する心理効果#1
アンダーマイニング効果
内発的に動機付けられた行動に対して、外的な報酬を加えることで元々の動機付けが低下してしまう現象をアンダーマイニング効果と言います。
・本来の目標を見失ってしまう
・報酬がなくなるとモチベーションが急落
・報酬の大きさに慣れてしまい、モチベーション維持が難しい
これは、もともと「行動すること自体が報酬」であったはずなのに、外的な報酬を加えることで、「外的報酬を得ることが目的」となってしまったために起こる現象とされています。
このように外的報酬には、元々あるモチベーションを上書きして潰してしまうほどの副作用(悪影響)があるのです。
具体例をさらに見たければ

2015年、日本実業団陸上競技連合が一般社団法人化し、「Project EXCEED」を開始したときの事例です。
公益財団法人日本陸上競技連盟が認める「マラソン大会で日本記録を更新したら報奨金1億円」という大きな外的報酬が呈示され、多くのランナーが参加しました。
次々に日本記録が更新されたいったのは記憶に新しいところでしょう。ところが、外発的動機付けは強力な一方で、アンダーマイニング効果も働いてしまったのです。
「Project EXCEED」の報奨金も、事前に設定していた期限が来る前に報奨金が底をつき、日本記録を更新しても満額の報奨金をもらえない選手が出てしまいました。
結果として、期待していた報酬がもらえなくなったことで残念に感じ、挑戦をするランナーのモチベーションが下がったことは言うまでもありません。
本来なら、例えば、
- 日本記録保持者になれるという外的報酬
- 一番でゴールテープを切る喜びといった内的報酬
だけでも相当嬉しいものであったはずです。
これは、報奨金(1億円)という強力な外的報酬が呈示されたことで、元々あった内発的モチベーションが相対的に低くなってしまったことが原因です。
このように、外発的動機付けが強力になればなるほど、元々あったモチベーションを上書きし、潰してしまうだ強力なアンダーマイニング効果となるのです。
外発的動機づけと関連する心理効果#2
クレスピ効果
クレスピ効果とは、外的報酬量の変化によって意欲が変化する心理現象のことを指していて、特にマイナス効果である、「それまで一定だった報酬が減少すると、その後の意欲が顕著に低下する」現象が非常に有名です。
例えば、これまで時給1,000円で働いていたのに、ある日突然、「明日から時給990円」と言われたら、実質1%しか給料が下がっていないのに、モチベーションはそれ以上に下がるのです。そして、一度落ちたモチベーションを戻すためには、最初以上の報酬量が必要なこともわかっています。
このように、外発的動機付けとして一度報酬を与えてしまうと、その報酬量を下げた場合に大きなデメリットがあるので注意するようにしましょう。
外発的動機付けは短期集中決戦に活用するべき
ここまで説明してきたように、外発的動機付けは、長期的な動機付けではなく「短期的な決戦」に大いに向いています。例えば下記の通りです。
- 同僚や部下を短期的に奮起させる
- 一念発起して転職活動を始めようとする
なお、外発的動機付けをしてしまったあとに、そのモチベーションを長期的に維持し続けるためには、以下の2つの方法があります。
(1)内発的動機付けを高めて、外的報酬の有無に左右されないようにする
(2)報奨金制度を継続して、効果が薄れる度に金額を増やして、外発的動機付けを高める
とはいえ、(2)は指数関数的に必要な金額が増えていくため、現実的ではないでしょう。そのため、(1)にあるような、「外発的動機付けから内発的動機付けへの移行」ができれば、それが一番効果的でしょう。
機能的自律性|外発的動機付けから内発的動機付けへの移行
元々は外発的動機付けによる行動であっても、やっているうちに内発的動機付けに変化していく現象を「機能的自律性」と言います。例えば下記の通り。
- やっているうちに、仕事の楽しさに気づいた
- 勉強するうちに興味が広がってどんどん調べていた
また実際に、2014年のロイファナ大学の研究でも、人は時間をかければかけるほど、情熱が高まってくることがわかっています。これは、「グロウス・パッション」と呼ばれる心理現象で、人の「情熱」は今までかけてきたリソース(時間やお金)の量に比例する、というものです。
そのため、最初は外発的動機付けを活用しながらうまく導入し、それを次第に内発的動機付けへ移行させていくことができれば、モチベーションが途切れることはなくなります。
この切り替えが綺麗にうまくできた状態が、一番効率的かつ持続可能なモチベーションの持ち方と言えるでしょう。
最後に
ここまで、外発的動機付けの影響について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
金銭的報酬などの外発的動機付けは、短期的にモチベーションを上げられることが大きなメリットですが、
ただ、長期的には続かないという「副作用」もあるので注意が必要です。
特に、人生で大切なものほど、短期努力で得られるものではなく、長期的に粘り強く進んでいくことで得られるものです。
そのため、目の前の魅力的な報酬によって、「本当に大切なものはなんだったのか」を見失わないように意識を傾ける必要があるでしょう。
このページを読んだあなたの人生が、より豊かなものとなることを祈っております。