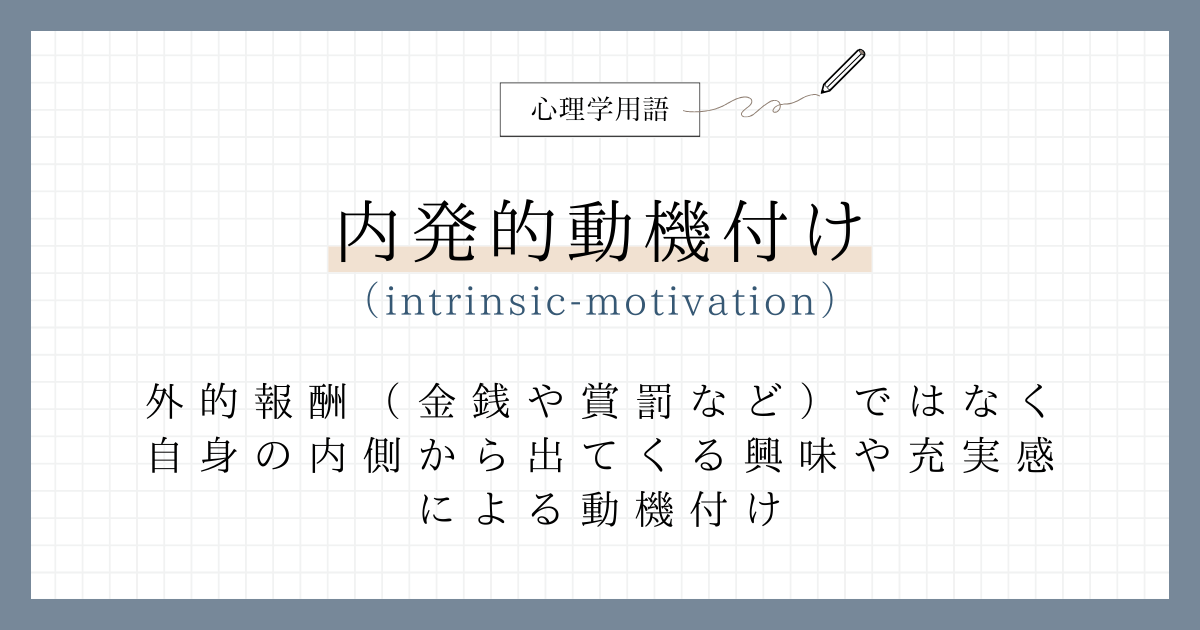内発的動機付けとは
内発的動機付けとは、とある結果に向かっていくプロセスそのものや自身の内的報酬(充実感や自己実現)による動機付けのことを指します。
- 仕事がうまくいったときの喜びがやりがい
→うまくいったという達成感が内的報酬 - お客さまの喜ぶ顔を見るためなら頑張れる
→人を喜ばせることができたという有能感が内的報酬
このように、作業(結果へ向かうプロセス)自体に夢中になる状態こそが「内発的動機付け」と呼ばれるものです。
結果ではなく、活動することそのものが動機付けになるため、目標達成までの苦難の道のりや試行錯誤の連続であっても、それを自らの糧と捉えることができ、さらなる活動や努力の原動力になっていくことが特徴です。
内発的動機付けの特徴#1
自律性への欲求から生まれる
「内発的動機付け」は、自分のすることは自分で自由に決めて行動したいという「自律性への欲求」を満たすことで高まるという特徴を持っています。誰に言われるわけでもないのに、自ら楽しみながら行動していく、これがまさに「内発的動機付け」というものです。
子どもの頃、自分の興味があることを進んで調べてみたり、もっと発展的な問題を解いてみたいと感じたりしたことは誰しもあるでしょう。外部(他者)から指示されたりコントロールされたりするものではありません。
内発的動機付けの特徴#2
外発的動機付けとの違い
内発的動機付けを理解する上で、対称の意味となる「外発的動機付け」の存在は欠かせません。
「外発的動機付け」とは、手に入れたい結果(外的報酬や賞罰)があり、それを得るための手段として行動をとっている状態のことを指します。
いわゆる「飴と鞭」で、下記が代表例です。
- 昇進するために努力する
→「昇進する」ことが外的報酬 - 上司に怒られないように営業する
→「怒られるという罰を受けなくて済む」ことが外的報酬
この外発的動機づけは短期的にモチベーションが上がることが特徴ですが、それが継続しないことや他のモチベーションを下げてしまう副作用があることも知られています。
エドワード・L・デシの実証実験
「内発的動機付け」および「外発的動機付け」という概念を理論化したのは、エドワード・L・デシ(Edward L. Deci)という米国の心理学者です。
デシは、人は自分自身の選択で行動でき、自分は自由だと感じているとき、つまり「その行為が行為する人の手中にある状態において、人は自律的にモチベーションを高めていく」のだと主張しました。
補足:当時主流だった行動主義心理学
当時(1960年頃)心理学の世界で主流とされていた「行動主義心理学(その人の感情などは考慮せず、目に見える行動だけに着目した心理学)」とは反する理論として主張されました。
- 罰を与えれば怠けることはない
- 動物に芸を覚えさせるには餌を与えればいい
- 労働者をしっかり働かせるには十分な報酬を与えればいい
実験内容
まず、学生を2つのグループに分け、当時流行っていた面白いパズルを解かせるまでは同じなのですが、それぞれに違った条件を提示します。
<Aのグループ>
パズルを解くと金銭的報酬(1ドル)を受け取れる
<Bのグループ>
バズルを解いても金銭的報酬(1ドル)は受け取れない
両グループに、30分間パズルを解かせた後、監督官が「これで実験はおしまいです。データ入力作業があるため離席します。」と言い残し退室することで、残された学生たちに“自由時間”を与えました。(パズルのほかに、雑誌なども置かれていて、好きに時間を過ごせます。)
実験結果
そして、この「自由時間に何をするのか」を見ていたのですが、2つのグループに明らかな差が出ました。Aのグループの学生は、もともともらえていた報酬がなくなることで、あまりパズルに取り組まなくなってしまいました。しかし、Bグループの学生は、比較的長くパズルに取り組んだのです。
これは、パズルに取り組むこと自体に「面白さ」や「楽しさ」のような内的報酬を見出し「もっとやりたい」というモチベーションを自ら高めていったために生まれた差分だと分析されています。
内発的動機付けは外側からは促進させづらい
ここまで説明してきたように、「内発的動機付け」は、その人の持っている能力を最大限に引き出すことを可能にする力を秘める、いわばモチベーションの源泉です。
もし、企業などの組織に所属する一人ひとりが「内発的動機付け」をもって職務に励むことができたとしたら、その組織の生産性はめざましく発展していくでしょう。
しかし、そのような企業を耳にすることはほとんどありません。なぜなら、「内発的動機付け」は、外側(企業や上司)が意図的に促進させていくことが非常に難しいからです。
というのも前提として、内発的動機付けの獲得には、相手の「自律性への欲求」を高めることが重要なのですが、ある組織に所属する以上、一人ひとりに自由な裁量権を与えるなんてことは、現実的ではないことが主な原因の1つでしょう。
社長賞や昇給目安を呈示するのは逆効果
例えば、社員のモチベーションを高めようとして社長賞を設けたり昇給・昇級の目安を呈示したりすることがありますが、このような「外発的動機付け」は、「内発的動機付け」にとってそれは逆効果です。
デシの実験で、1ドルを与えられたAグループの学生が自由時間ではパズルにあまり取り組まなかったように、「報酬があるときにだけやり、報酬がなければならない」という状態がつくられやすくなってしまいます。
短期的にモチベーションを高めたい場合であれば機能するのですが、長期的にモチベーションを高めて働いてもらいたい企業にとっては悪手でしょう。
このように、外発的動機付けには、元々あるモチベーションを上書きして潰してしまうほどの副作用があるのです。
内発的動機付けを促進させるための3ポイント
「内発的動機付け」を高めるためには、個々が自ら内的報酬を獲得し、それをやりがいと感じられるような風土をつくっていくことが最も大切です。
内発的動機付けを促進させるポイント#1
能力や成長段階に合わせた裁量権を与える
最低限のルールをしっかりと示しつつ、各自の能力や成長段階に合わせた裁量権を与えることで、自律性の欲求を満たしていくことが必要になります。
内発的動機付けを促進させるポイント#2
簡単な業務だけでなく新しい挑戦をさせる
裁量権を与えるにしても、簡単な業務だけではなく、ある程度の失敗をおそれずに新たな取り組みや改善にチャレンジできる機会を設けることが有効です。
内発的動機付けを促進させるポイント#3
結果ではなく、努力や試行錯誤を評価する
何かよい成果があがったときに、昇級や昇進をほのめかすのではなく、そこに至るまでの「努力や試行錯誤」に対して評価者は言及をするべきです。
- 例:これ大変だっただろうにありがとう
- 例:ここをやってくれたのが凄く助かった
このように、「ああ、この人の役に立てたんだ」と思える褒め方をすることが大切です。そのほかにも、顧客がいるような業務内容であれば、顧客の感謝や喜びの声を知れるような機会をつくるのもいいでしょう。
また、同僚や上司がやりがいを持って主体的に行動している姿を見る、それぞれがやりがいを共有するような方法もあります。