ジェームズ=ランゲ説とは
ジェームズ=ランゲ説とは、何らかの刺激に対して、まず体が反応し、それが意識化されることで感情が生まれていく、と考える理論です。
つまり、一般論として知られる「悲しいから泣く」といった『情動→身体変化』ではなく、「泣くから悲しくなる」といった『身体変化→情動』の道筋が示唆されています。
1884~1885年ごろに2人の心理学者ウィリアム・ジェームズとカール・ランゲによって提唱されて以降、広く知れ渡るようになりました。
「ジェームズ=ランゲ説」の由来
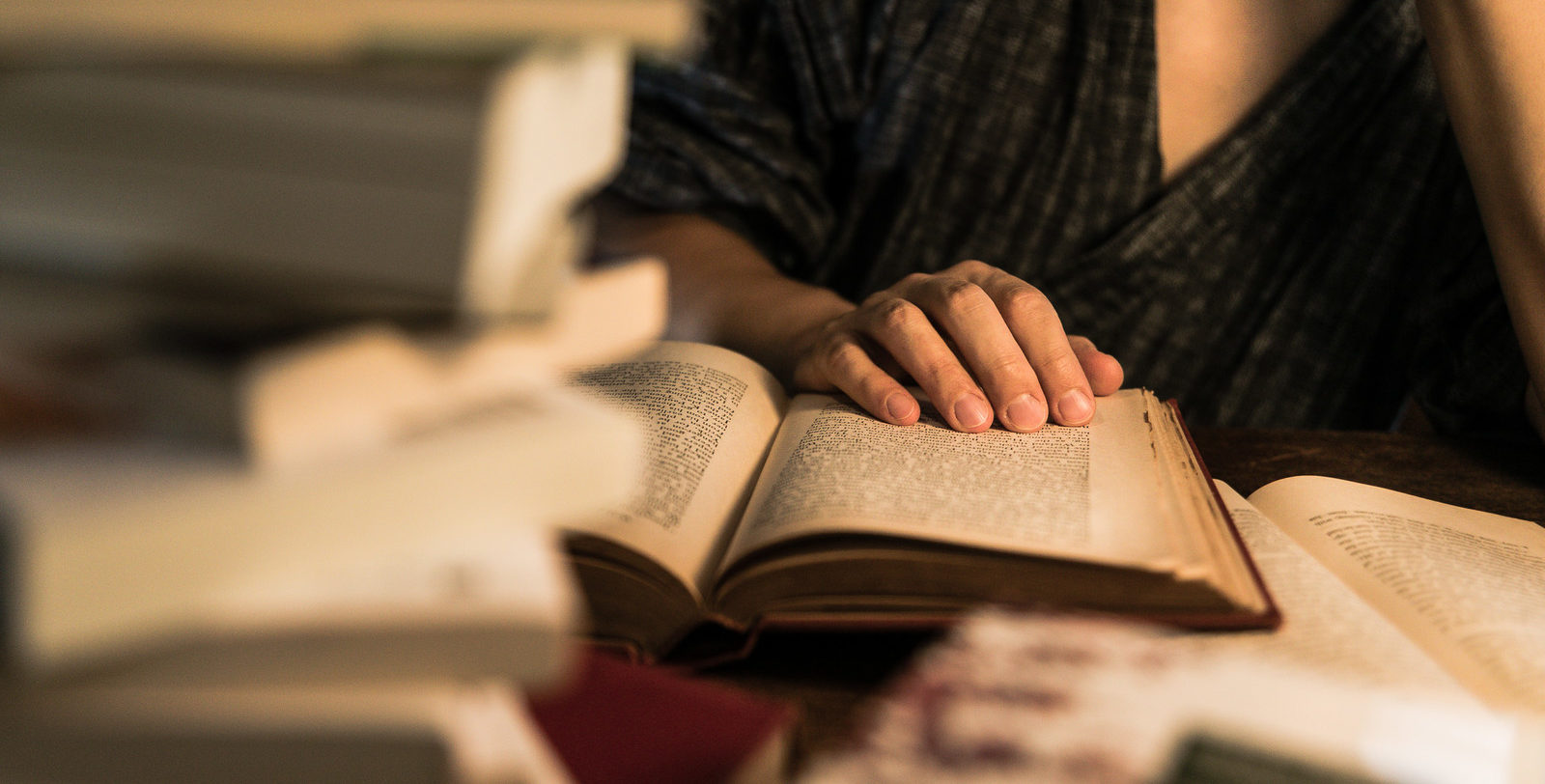
涙が流れると悲しくなる、笑うから楽しい気持ちになる、というように、
「なんらかの出来事(刺激)があり、それに対してまず体が反応し、それが意識化されることで感情が生まれていく」
とアメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズ(James, W)とデンマークの心理学者カール・ランゲ(Lange, C)によって提唱されました。
もともと2人は別々に研究をしていたのですが、1884~1885年に同じような説を唱え始めたため、2人の名前をとって「ジェームズ=ランゲ説」と名付けられたのです。
「ジェームズ=ランゲ説」は末梢起源説と呼ばれる
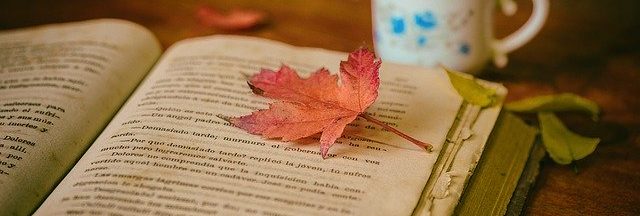
心理学の世界では、別名「末梢起源説」とも呼ばれており、「環境に対する身体的・生理学的反応の認知が、情動を生む」と説明されています。
なお、「感情」はこころの状態を指しますが、「情動」は、比較的短期間の強い感情で、表情や行動、体内の生理的活動というニュアンスも含む専門用語です。
また、ジェームズ=ランゲ説(末梢起源説)に対して、中枢起源説(例:悲しい&泣くは同時)という説も提唱されています。
末梢起源説と中枢起源説はどちらが正しいとも言い切れない
ちなみに、ジェームズ=ランゲ説は、1920年代、アメリカの生理学者ウォルター・ブラッドフォード・キャノン(Cannon, W.B.)が提唱した「中枢起源説」によって否定されています。
この中枢起源説とは、何らかの出来事(刺激)により脳が活性化し、そこから身体反応(例:泣く)と情動体験(例:悲しい)が同時に起こるとする考えのことです。
この「なぜ人が感情を抱くのか?」という疑問は、現在に至っても解明されておらず、感情心理学というひとつの分野になっているほどです。
現在、「中枢起源説」も「ジェームズ=ランゲ説」も、感情のメカニズムすべてを説明はできていないものの、部分的には正しいところがあると捉えられています。
「ジェームズ=ランゲ説」の実証実験

1884~1885年ごろに提唱された「ジェームズ=ランゲ説」ですが、心理学者も含めた多くの人は、“悲しいから泣く”と考えており、机上の空論と受け止められていました。
そんな中、いくつかの実験により、特定の表情をつくることによって感情が左右されることが証明され、部分的には正しいことが証明されたのです。
ではそれぞれ解説していきます。
レアード, J. D.(Laird, J. D.)の実験
レアードは被験者(実験の参加者)に、顔の筋肉の動きを調べる実験だと嘘をついて、表情筋の動きを調べる電極を顔に取り付けます。
次に、「歯をくいしばって」「頬を上にあげて」などと1つひとつ指示を出し、特定の表情筋を動かさせました。
被験者たちは、言われるままに表情筋を動かし、1つの指示が終わるごとに、その時の気分を尋ねるようなアンケートに繰り返し回答します。
その結果、「頬を上にあげて」という指示で楽しいときの表情(笑顔)をつくらせた後は、楽しい気分や嬉しい気分になっていることがわかったのです。
同じように、怒った顔をつくったときには、怒った気分になっていることもわかりました。
シュトラック, F.(Strack, F.)の実験
シュトラックの実験でも、被験者には感情の実験であることは伏せてあり、手足が麻痺してもペンを咥えて書くためのトレーニングの研究」と説明しています。
被験者は2つの指示に従い、ペンを咥えます。
シュトラックがした2つの指示
- ペンを唇でしっかりと咥えること
→ムスッとした表情をつくらせるため - 唇を優しく広げること
→ニコッとした表情をつくらせるため
それぞれの咥え方で文字を書く練習をした後、漫画を読み、面白さを回答してもらいました。
その結果、同じ漫画を読んでいるのに、ムスッとした表情をつくったときよりも、ニコッとした表情をつくったときの方が、面白いと回答されたのです。
「ジェームズ=ランゲ説」の事例

「ジェームズ=ランゲ説」は、何らかの出来事に対してまず体が反応し、それが意識化されることで感情が生まれていく、と考える理論です。
この正しさは、意外と身近な体験からも実感することができます。例えば、
- テレビや映画を見ていていつのまにか涙を流していたとき、自分が泣いていると自覚した途端によけいに泣けてくる
- 相手に不快感を示すために怒った表情をしていたら、本当に腹が立ってきた
- 大勢の前でプレゼンテーションするようなとき、緊張で手汗が出ていることに気がつくと、ますます緊張が高まって汗をかいてしまう
- お化け屋敷やジェットコースターに乗ったとき、鳥肌が立っているのを見て、自分がこわがっているんだと気づく
というようなことです。
参考事例:笑いヨガ

近年、笑いヨガというものがほどほどに流行っていますが、これには複数のポジティブな効果が見込めるとされています。
例えば、
- 免疫力アップ(生理学的効果)
- 笑うことで元気になる(心理学的効果)
- 人と人との距離が縮まる(社会的効果)
などです。
特に生理学的効果については、血液中の成分の望ましい変化が医学的に証明されているのですが、自然な笑いでも、作り笑いでも、体への作用は一緒ということがわかっています。
つまり、感情やそれに伴う心身の変化は、“形から入る”ことも十分に効果的なのです。
それどころか、意識的にはなかなか変化させられない血液中の成分を変化させることすら可能になるのです。
これはジェームズランゲ説に加え、引き寄せの法則やプラシーボ効果といった、思い込みが現実となる心理効果も一部働いて、一定の効果に期待できるものです。
「ジェームズ=ランゲ説」の活用方法
「ジェームズ=ランゲ説」を活用することによって、意図的に表情や体を動かすことから、自分の感情をコントロールすることが可能となります。
大切なのは、そのときに感情に注目するのではなく、「形から入ること」なので、まずはその感情になったつもりになって、表情筋や体を動かしてみてください。
引き起こしたい感情が少しでも本当に感じられるようになってきたら、あとはその感情に合った場面を想像したり、もっと大きくその感情を表現したりが良いでしょう。
ではそれぞれ見ていきましょう。
笑顔によって緊張をほぐす
例えば、大事な会議やプレゼンテーションの前に緊張で力が入ってしまうようなとき、あまり気乗りしない商談や作業が目の前にあるとき、
「1・2・3・4」と大きく口を動かしながら繰り返し数えてみてください。特に、「2」と「4」を意識します。
「2」はニコッとした笑顔、「4」は感じのいいにこりとした笑顔のときと同じように表情筋が動きますから、穏やかでリラックスした気持ちになりやすくなります。
体の力を抜いてリラックスする
表情だけではなく、体の動きを加えることも効果的なので、リラックスしたいときには、のびをして体の力を抜いてみてください。
なにより、「クスクス」と笑っているときには肩が揺れるものですから、笑っているつもりで肩を揺らしてみてください。
ここぞと気合いを入れたいようなときには、口をグッと結び、拳をギュッと握ってみて、笑っているつもり、気合い満々になったつもりで、体全体を動かしてみてください。
誰かを励ましたいならまず、笑わせろ
「ジェームズ=ランゲ説」は、誰かを励ましたいときにも有効です。
例えば、仕事で失敗した部下を慰める場合や、恋愛で失恋した友達を元気付けたい場合など、「元気を出して」と声をかけるだけでは、なかなか相手を元気にできないことが多いでしょう。
その場合は、「ほら、笑って欲しいな」「笑顔のほうがずっと素敵だよ」と伝えてみてください。
そして、落ち込む理由となった話題ではなく、別の話題、なにか面白いことを言ってクスクス笑わせられれば、もう励ませたも同然です。
こっちが笑えば、つられて相手も笑う
ただ、残念ながら「ジェームズ=ランゲ説」も万能ではないので、表情筋を動かすだけではいまいち元気がでない、楽しい気持ちになれない、ということもあるでしょう。
その場合、こっちが笑うのも一つの手です。
というのも、人間の脳には、無意識的に働いてくれるミラーニューロンというものがあり、相手の表情を見ているうちに、
自然とミラーニューロンが相手の真似をして、相手と同じようにうまく表情筋が動いてくれるということが実証されているからです。
そのため、最終的には、脳の特性をうまく使うのもありでしょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。
ここまで説明してきたように、ジェームズ=ランゲ説とは、何らかの出来事に対してまず体が反応し、それが意識化されることで感情が生まれていく、と考える理論でした。
そして「笑えば、楽しくなる」「泣けば、悲しくなる」といったように、感情を行動によって制御できることが実証されているので、日常での活用シーンも多くあるでしょう。
このページを読んだあなたの人生が、
より豊かなものとなることを祈っております。
参考文献
Laird, J. D. (1974). Self-attribution of emotion: The effects of expressive behavior on the quality of emotional experience. Journal of Personality and Social Psychology, 29, 475-486.
Strack, F., Stepper, S., & Martin, L. L. (1988). Inhibiting and facilitating conditions of the human smile. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 768-777.
福島裕人(2008).ラフター(笑い)ヨガの効果に関する基礎的研究.笑い学研究,15,56-63.
