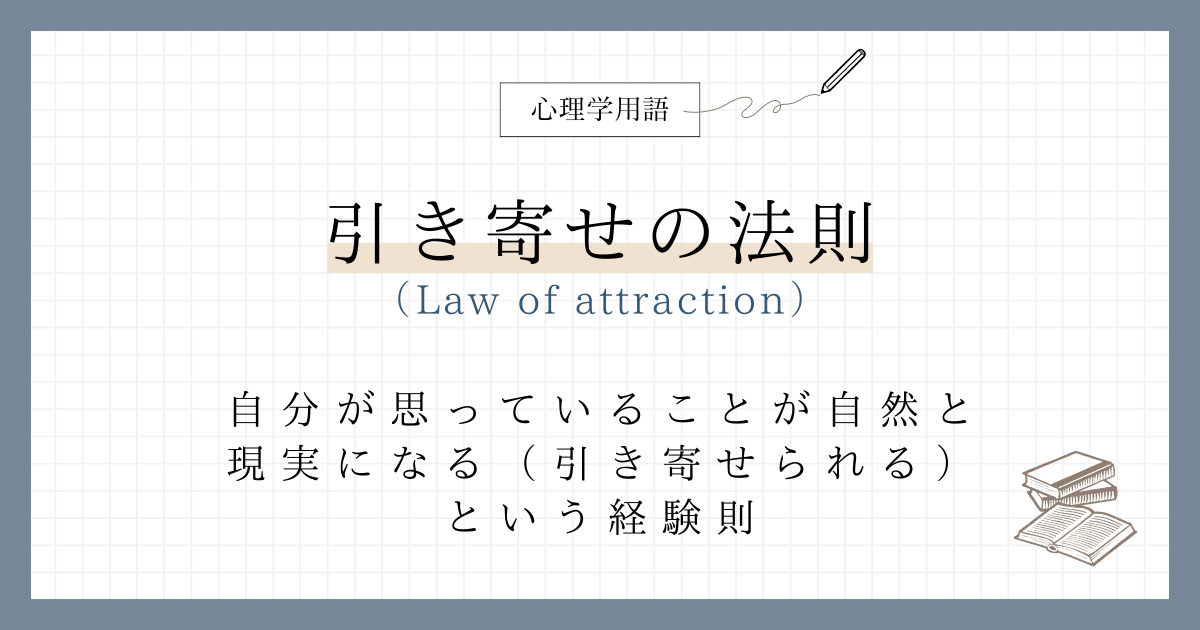引き寄せの法則とは
引き寄せの法則とは、「自分の思っているものごとが、自然と現実になる(引き寄せる)」という経験則のことです。
科学的に実証されてはいないものの、自分の気持ちを改善することで、ものごとをうまく進めるようになったり、良い成果につながったり、といった「ポジティブシンキング(積極思考)」の観点から、主に自己啓発の領域で支持されています。
ロンダは、信じることで願いを達成できるというポジティブシンキングを信念としており、引き寄せの法則は「思考が現実になる」という思考を、自己啓発として提唱したものです。
当書によれば、良い結果だけではなく、悪い側面(例:病気や事故、災害)までも、自分自身のマイナス思考が引き起こすとされています。
引き寄せの法則とは
科学的ではないので否定意見が多い
ロンダが根拠として挙げた科学概念が擬似的なものであると否定されている(つまり科学的には実証されていない)ことから、否定する意見があります。
一方で、すでに心理学において実証済みの、類似した心理効果が複数存在していることから、支持する意見も存在しているのも事実です。次章で紹介していきます。
 運営者
運営者強く願って「行動すること」で達成に近づくことはありますが、ただ願うだけでは叶いませんよね(魔法使いではないので…)
引き寄せの法則に類似した心理効果
引き寄せの法則には、類似した心理学の理論や効果がいくつかあり、実はこれらが人の心や言動に影響を及ぼしているという説もあります。
ただ、類似したものとしてあげられる心理学理論は出典が不明なものも多くあり、今回は提唱者があきらかなものに絞って紹介します。
- プラシーボ効果
- カクテルパーティ効果
- 確証バイアス
引き寄せの法則に類似した心理効果#1
プラシーボ効果
プラシーボ効果とは、偽物の薬を「これは効果がある」といわれ、偽物だと知らさられずに服用していると、本来は効果がなくても改善することがあるという現象です。
ハーバード大学麻酔教授であったヘンリー・ビーチャー(Henry Knowles Beecher)が1955年に研究報告を行い、現在まで広く知れ渡っています。自分が病気になった際、引き寄せの法則で「絶対に治る」と自分に言い聞かせることで、このプラシーボ効果が起こり、回復に至るというケースが該当します。



効果があったりなかったりするので科学的には実証されていませんが「病は気から」などに近いかもしれませんね。
引き寄せの法則に類似した心理効果#2
カクテルパーティー効果
カクテルパーティー効果とは、パーティー会場のようにたくさんの人が雑談している騒がしい空間の中でも、自分が興味の向けている会話や単語は、自然と聞き取ることができるという心理効果です。
- ざわつく部屋でも、自分の名前が呼ばれるとはっきりとわかる
- 大勢の人が集まった飲み会でも、自分が話したい相手の声は比較的聞き取りやすい
- 元々長く吹奏楽の経験がある人がオーケストラを聴いていると、自分の担当していた楽器の音がよく聴き取れる
このカクテルパーティー効果は、人によっては効果が弱いこともありますが、効果自体は立証されています。
だからこそスポーツでは「絶対勝つ」という意識を持つことで、無意識に「勝つための情報」を拾いやすくなったり、試合中の状況判断が早くなるといった、ポジティブな影響が働くとされているのです。



自然と五感が受け入れている「膨大な情報」のどこに注意を向けるか、という集中力の使い方が変わるためですね。
引き寄せの法則に類似した心理効果#3
確証バイアス
確証バイアスとは、自分の仮説や信念を検証しようとするような場合に、自分を支持する情報ばかりを集め、反対意見を無視・軽視する傾向、認知バイアスです。
つまり、引き寄せの法則で「自分は幸運の持ち主だ」と思い込むことで、どんな些細なことであっても「自分は運がいいからだ」と理由づけるようになります。逆に不都合なできごとには目が向きません。



自己啓発にハマって、引き寄せの法則を盲信する方は、この確証バイアスによる影響が背景にあるのかもしれませんね。
引き寄せの法則に類似した心理効果#4
ことわざに類似したものは多い
実は日本のことわざに、引き寄せの法則と似たものがいくつか存在します。
- 笑う門には福来る
- 類は友を呼ぶ
- 噂をすれば影がさす
- 人を呪わば穴二つ
有名なことわざなので解説は割愛しますが、これらも何かの言動によって結果が引き起こされるという点で、引き寄せの法則に類似しています。
余談ですが、1970年ごろに日本でも流行した「マーフィーの法則(起こる可能性のあるものは、絶対に起こる、失敗する可能性のあるものは失敗するという経験則)」にも似ていますね。
引き寄せの法則の活用事例
願うだけで叶うというほど都合の良いものではありませんが、「達成したい」「手に入れたい」と強く望むからこその“副次的効果”あるいは“ポジティブシンキング”という意味で、肯定的に用いられることがあります。
引き寄せの法則の活用事例#1
スポーツの試合で勝ちたい
先述しましたが「自分は勝てる」と思い込むことによって、勝利に繋がることが往々にしてあります。
- 監督の的確な指示がよく耳に入る
- 周囲の負けるという予想の声があっても諦めなくなる
- 直前に飲んだサプリメントの効果が出てパワーアップ
これらのように、勝敗に大きな影響は与えないまでも、ポジティブで都合の良い思い込みによって、粘り強いパフォーマンスや積極的に挑む姿勢が強化され、勝利へと結びつくことがあるのです。



行動しなければ意味はありませんが「勝つために何ができるか」を最後まで執念深く考えることでパフォーマンスは上がります。
引き寄せの法則の活用事例#2
好きな相手との恋を成就させたい
この事例はややグレーかもしれませんが、意中の相手を射止める時に「絶対にこの人は私を好きになる」といったように余裕を持つことで、成就する可能性があります。
- 自信と余裕を持てるので魅力的になる
- ポジティブな心理状態が表情や肌ツヤに現れる
- 相手のしぐさや言動を自分に好意があるように捉えられる
思い込みが度をすぎて事件を起こさないか心配ですが、結果としてその人自身の外見的、内面的な魅力が上がり、恋の成就に一歩前進する可能性も否定はできません。



自分に自信がなくて相手に依存しやすい人よりは、自分の魅力を信じて疑わない人の方がモテますからね。
引き寄せの法則の活用事例#3
ビジネスで目標を達成したい
ビジネスで達成したい目標を掲げる(例:営業で月に目標売上XX万円達成する)ことによって、日々の意識や行動量が変化して、達成に近づくかもしれません。
- 知識や技術の習得に、意欲的になる
- 失敗に落ち込む暇なく次に挑戦できる
- 目標意識から今やるべきことがぶれない
実際、「営業職」のようにやることが明確で行動量がものをいう職務では、目標意識を高く持っている社員ほど、目標を達成しやすい傾向にあります。



なにより「目標を掲げてそれに向かって一生懸命頑張っている社員」は周りから見ても応援されやすくもなるものです。
引き寄せの法則に関する注意点
引き寄せの法則は、強く願うがために「行動すること」から達成に近づくことはありますが、ただ願うだけでは叶いません。盲信には注意しましょう。
引き寄せの法則に関する注意点#1
科学的でないので他人への伝え方に注意しよう
引き寄せの法則は、科学的根拠のないスピリチュアルな考え方です。性質としては占いや宗教に近いので、盲信するのはやめましょう。特に、他人に伝えるときは注意が必要です。
もちろんポジティブシンキングの一貫で「願うといいことあるって言うしね」と明るく触れるには問題ありません。ただ「願うだけで何もしなくても叶うんだよ!」のように熱量高く振舞ってしまうと、日本人の多くからは避けられるようになります。



目標を持って「行動すること」に意味があります。行動を伴わない目標には意味がありません。叶っても運です。
引き寄せの法則に関する注意点#2
現実とズレた妄信が成長を阻害する
思い込みの方向性によっては、自分のプライドを守るためだけの「認知の歪み」となり、事実や他人の意見を素直に受け入れることができず、成長の機会を損なう可能性があります。
例えば「自分は仕事で絶対に成功する人間だ」と思い込むことで、上司からの否定的な指摘を軽んじたり、自身に都合の悪い事実から目を伏せたり、などです。
さらに場合によっては「ここは自分のいるべきところではない」「もっと自分の才能を認めてくれるところがあるはずだ」と仕事を辞めてしまうことも想像に難くはありません。



自らの間違いを正しく認識して「次はどうしたら成功できるだろう?」と考えなければ、人は成長しないんですよね。