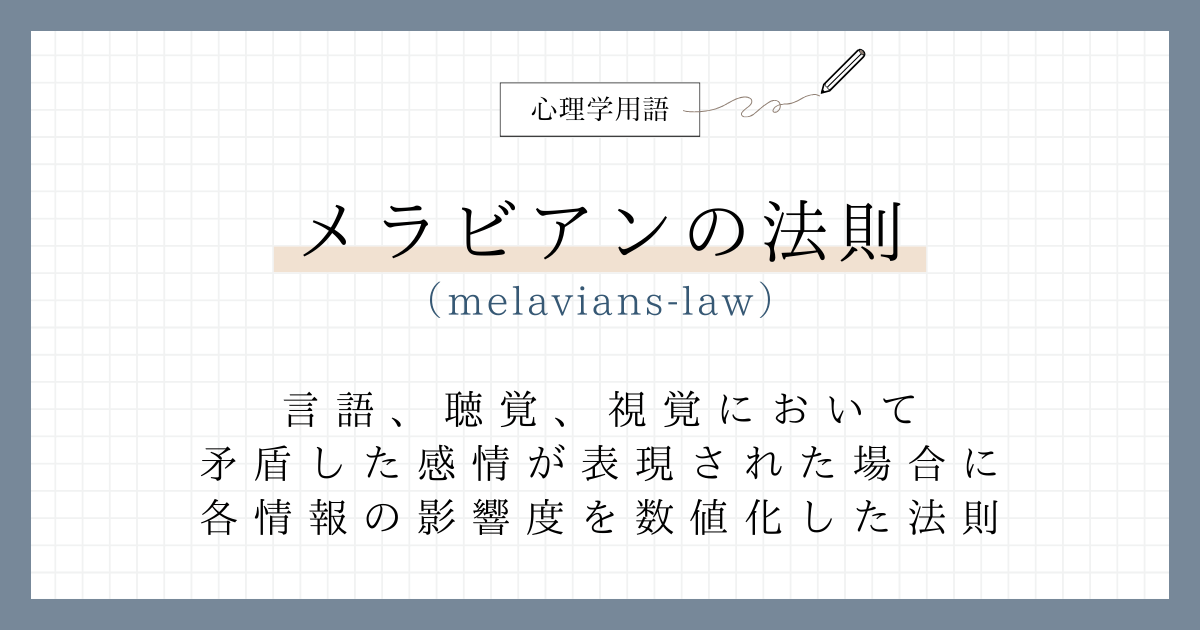メラビアンの法則とは
メラビアンの法則とは、3つの情報伝達軸「言語、聴覚、視覚」において、喜怒哀楽といった感情が【矛盾して】表現された場合の受け止められ方を、定量的に示した法則です。
アメリカの心理学者アルバート・メラビアン(Albert Mehrabian)が1971年の著書内で発表した実験では、情報が矛盾した際の受け手に及ぼす情報の影響は、以下割合であるとされています。
- 言語情報:7%
話している内容 - 聴覚情報:38%
声のトーンや話す速度 - 視覚情報:55%
顔や表情など
別名として「7-38-55のルール」「3Vの法則」とも呼ばれます。(3Vは、言語(Verbal)聴覚(Vocal)視覚Visualの頭文字から)
 運営者
運営者例えば、暗く浮かない顔で「このケーキはとても美味しいですね」と低いテンションで言われたら、ほんとに!?と思いますよね。
【よくある誤解】一般的な伝わり方の比重ではない
メラビアンの法則は、言語/聴覚/視覚それぞれの情報が【矛盾して表現された場合】にどの情報を優先して判断されやすいかであって、一般的な伝わり方の比重を指してはいません。
下記は「メラビアンの法則」ではありません。
- 見た目が一番重要である
- 話の内容より、声や速度が重要である
よく誤解されている「コミュニケーション全般においてメラビアンの法則が適用される」という解釈は、メラビアンの実験結果に対する、本来の解釈とは異なるので注意が必要です。



コミュニケーション全般で「メラビアンの法則」が当てはまるという解釈は、科学的根拠がなく、拡大解釈された俗説に過ぎません。
メラビアンの法則の実証実験
メラビアンの法則の実験では「好き、嫌い、普通」といった異なる感情を「言語情報、聴覚情報、視覚情報」の3種類を混ぜて伝えた時に、受け手はどの印象を優先したのかを調べたものです。
- 言語情報
好き、嫌い、普通といった言葉 - 聴覚情報
好き、嫌い、普通を想起される話し方を録音 - 視覚情報
好き、嫌い、普通を想起される表情の顔写真
そして、感情(好き、嫌い、普通)が矛盾する組み合わせ、例えば「好き」をイメージさせる言葉を「嫌い」な話し方、「普通」な顔写真とともに被験者に提示し、どう感じたかを集計しました。
メラビアンの法則に注意すべき事例
- 楽しかったことは楽しそうに伝える
- 怒っていることを怒っているように伝える
簡単なようですが、少しでも矛盾があると、伝えたいことが伝わらないかもしれません。
コミュニケーションにおいて、視覚/聴覚/言語のコミュニケーションが矛盾を生むことはほとんどありませんが、面接やプレゼンといった「緊張しやすいシーン」ではよくあるので注意しましょう。



実は私は、感情表現が得意ではなく、楽しくても無表情なことがあるので「本当に楽しんでいる?」とよく誤解されていたり。。
メラビアンの法則に注意すべき事例#1
慣れない採用面接
採用面接では、緊張や不安によって3V情報(視覚/聴覚/言語)が矛盾しやすくなります。緊張しないように、経験を積んで慣れていくしかありません。
例えば、企業が求めている人材がリーダーレベルのものであれば、どっしりと構えて落ち着いた口調と穏やかな顔で受け答えする態度が望ましいといえるでしょう。
他にも、面接でのよくある質問、「楽しかったプロジェクト」や「失敗したプロジェクト」の話をする時には、言語以外の「聴覚、視覚情報」を揃えにいくことが重要です。



すべての受け答えが固くオドオドとしていると魅力的に見えなかったりしますもんね。普段通りの会話をするためにも慣れていきましょう。
メラビアンの法則に注意すべき事例#2
営業の商談
商談の場で「弊社の商品は御社にとって必ず役に立ちます!」と力説されても、受け答えに自信がない態度が出てしまうと説得力がありません。
- 相手の目を見る
- 声のトーンを大げさでない程度に上げる
- 落ち着いた表情や必要に応じて笑顔を見せる
- 適宜ボディランゲージをはさみこむ
このように「落ち着いて自信のある態度」を演出することで、より説明が効果的に伝わります。さらに「商談において自分をどう印象付けたいか」まで意識して信頼を勝ち取れれば、営業職として一皮剥けるでしょう。



営業トークは慣れなので、上司や先輩とのロープレを繰り返していくことが重要ですね。
メラビアンの法則に注意すべき事例#3
プレゼンテーション
プレゼンテーションは演技力が必要です。各スライドメッセージを伝えたときに想起される感情と、話し方や表情を合致させるようにしましょう。
- 悲観的な状況を伝えたいのであれば、時おり声のトーンを落として現状を憂うような顔を見せる
- 危機感を抱かせたいのであれば声のトーンを変えて、大げさではない程度に煽る
また、ネガティブな状況を伝える際に、極端ですがラフで派手な格好をしていると視覚情報が矛盾し、マイナスの印象を与えかねないので、スーツや落ち着いた服装で行うことも重要です。



極端な例ですが、謝罪記者会見をアロハシャツでやっていたら「反省しているのか!」となりますからね…
メラビアンの法則に注意すべき事例#4
部下を褒めるとき
例えば、部下の頑張りを褒めるときに、より伝わりやすいのは以下2つのどちらでしょうか。
- 部下の席まで行って部下の顔を見て笑顔で評価を伝える
- 部下を呼び出して自分のパソコンに目を向けて作業をしながら余裕のない顔で評価を伝える
いうまでもなく、前者のほうが好ましいでしょう。自分の感情や言葉を表に出すことが苦手な管理職もいるかもしれませんが、部下のモチベーションを高めるのも重要です。



部下も「上司から期待されている」と思うことで、モチベーションが高まる(ピグマリオン効果)ので、損をしない伝え方をしてくださいね。
メラビアンの法則に注意すべき事例#5
相手の悩みを聞く際のコミュニケーション
相手が「話を聞いてほしい」と悩みを自分に打ち明けるときには、相手の心に寄り添っている真摯な姿勢を見せることが重要です。
相手の感情にミラーリングして寄り添うことを意識してみてください。逆に、相手が悲しそうにしているのに、話を聞いている自分が楽しそうに聞いていたら、二度と相談をしてもらえなくなります。