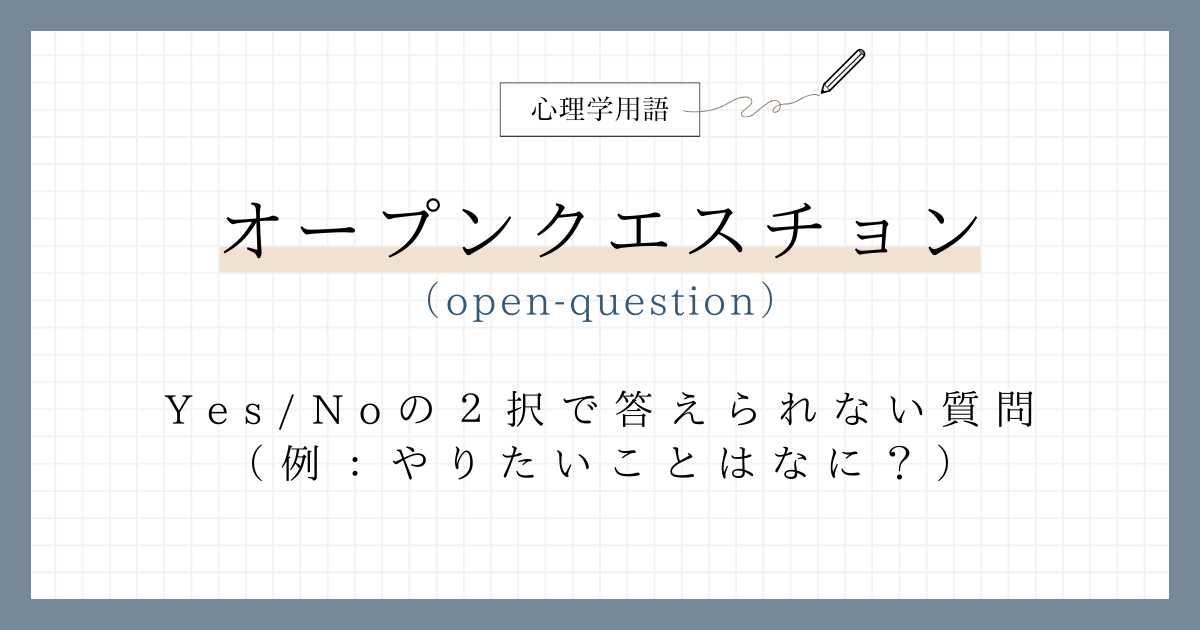オープンクエスチョンとは
オープンクエスチョンとは、「YES or NO」の2択で答えられない質問のことを指します。日本語だと「開いた質問」と訳されますね。
例えば、「あなたが今困っていることは何?」などで、「いつ」「どこで」「誰が」「何?」「なぜ」「どのように」といった「5W1H」から始まる質問になります。
逆の概念として、クローズドクエスチョンという、「YES or NO」の2択で答えられる質問も存在します。
では早速、オープンクエスチョンについて解説していきます。
オープンクエスチョン&クローズドクエスチョンの由来
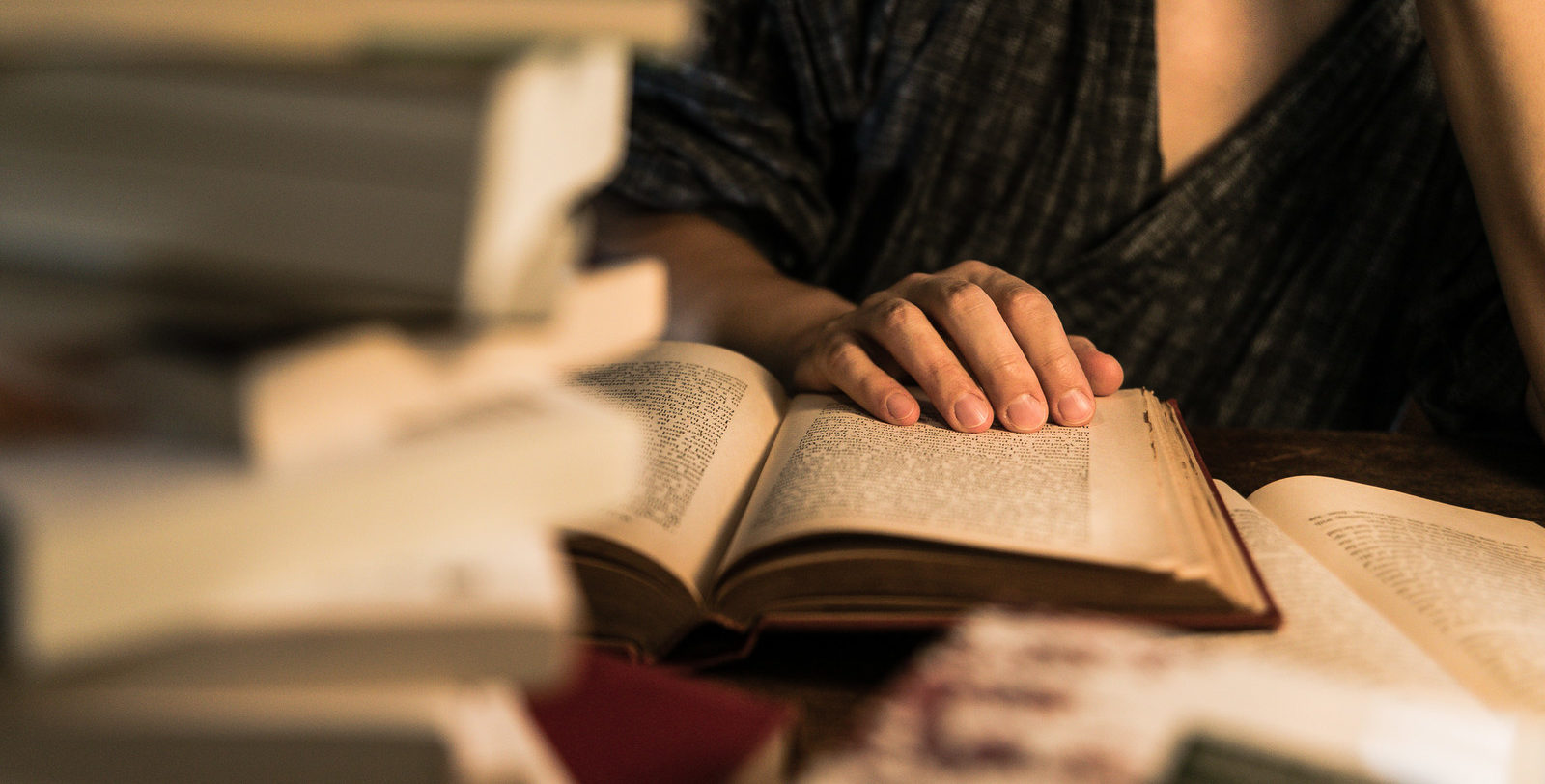
オープンクエスチョン・クローズドクエスチョンは、もともと「コーチング」の分野から生まれたとされています。
コーチングとは、関わる相手に自発的な行動を促すためのコミュニケーション手段で、組織のマネジメント手法として管理職の方々がコーチングの技法を学ぶことがあります。
そしてこのコーチングに関する技法において、「質問」は知っておくべき基本的なスキルだといわれています。
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの違い
オープンクエスチョンはクローズドコミュニケーションと比較して、相手から自由な意見を引き出しやすい質問の方法です。
先ほどの例でいうと、「困っていることは何か」というオープンクエスチョンにおいては、例えば、
- ちょうど作業に詰まっている
- 企画を考えるのに時間がかかっている
- ここがわからない
と、自由度の高い回答を相手から引き出すことができます。
逆に「何か困っていることはある?」というクローズドクエスチョンの場合、その性質として詰問(きびしく問いただされること)のニュアンスが生まれるため、
困りごとがあったとしても人によっては「いいえ、ありません」と答えてしまう可能性も大いにあるでしょう。
またもし「はい(、あります)」と答えると結局は「何に困っているの?」というオープンクエスチョンに至るため、コミュニケーションにひとつ工程が増えることになります。
無駄とはいわなくても、まどろっこしさを感じられてしまうことがあるかもしれません。
オープンクエスチョンの注意点
ここまでの説明を通すと、「オープンクエスチョンはクローズドクエスチョンより優れている」と思われるかもしれませんが、そういうことでもありません。
オープンクエスチョンの特徴として、相手が答えを出すために頭を使って考える必要があるため、回答までにしばしば時間を要します。
またコミュニケーションが不得手な人(口下手な人や口数の少ない人など)にとっては、気軽に返すことのできない質問のために、負荷が高い、すなわちストレスになりやすいという可能性も考えられます。
これは、会話の最初に「最近どう?」と聞かれるより「元気だった?」と聞かれたほうが楽だという理屈です。
人によっては、オープンクエスチョンが続くと苦痛を感じることもあるので、はじめはクローズドクエスチョンで頭を使わないやりとりから会話を始めることも、円滑なコミュニケーションにおいては重要といえるでしょう。
オープンクエスチョンを活用するために
オープンクエスチョンはその性質を知っていれば、相手から意見や思いの丈を引き出す効果的なテクニックとなります。
そして活用するための3ステップを紹介していきます。
ではそれぞれ見ていきましょう。
相手から意見を引き出して終わりではない
オープンクエスチョンによって相手の思っていることを引き出せばそれで完了というわけではありません。
例えば、「何か困ってる?」と部下に聞いたとして、部下が「実はちょうど作業に詰まっているんです」と返しても、
「そうか、わかった」で会話を終わらせるのは不自然ですし、部下の問題解決に至っていません。
「チャンクダウン」を活用して具体化しよう
ここでもうひとつの会話スキルとして「チャンクダウン」について触れておきます。(ちなみに「チャンク」とは「かたまり」を意味します。)
これも同じくコーチングの基本スキルであり、抽象的で曖昧なものをより小さな単位の行動レベルに落とし込むというものです。
今回の例だと、「わかったよ、じゃあどこでどのように詰まっているのかな?」と具体的に聞くことで、部下の困難をより明瞭に把握することができるわけです。
仮に上司が、部下に質問を続けていくとしたら、詰まっている内容を明らかにした上で、
- それぞれをどう処理すべきか
- 処理するために必要な作業は何か
- 各作業にどのくらいの時間がかかるか
と、より細かく落とし込んでいくことができるでしょう。
最後にフォロー「チャンクアップ」も忘れずに
ただ、チャンクダウンで具体的に深掘っていくのは、一定のストレスがあるので、場合によっては受け手のすべき行動が多くなり、曖昧だったときよりも逆に負担を強いる可能性が生まれます。
このときのフォロー策として最後に「チャンクアップ」を紹介します。
チャンクアップはチャンクダウンとは逆に、具体的に散らばった事柄を抽象的に「かたまり」としてまとめあげることです。
今回の質問で最後にチャンクアップをすると、「これでやることがわかったね、これをすべてやれたらどうなりそう?」という質問が近いでしょう。
このチャンクアップを行うことで、チャンクダウンによって見失いがちな「本来の目的」を相手に思い出させる効果があります。
ただ、クローズドクエスチョンの方が楽ではある
とはいえ、話し手にとっても聞き手にとっても、頭を使う必要がないという意味においてクローズドクエスチョンのほうが「楽」です。
「今日の作業は終わった?」と聞くのと、「今日の作業はどこまで終わった?」もしくは「今日の作業はいつごろに終わりそう?」と聞くのとでは、
原則「はい」か「いいえ」の回答しか返ってこない前者のほうが、内容を受け止めやすく、気軽に聞きやすいのではないでしょうか。
そのため、オープンクエスチョンは意識的に行わないと、質問はクローズドクエスチョンになりがちかもしれません。
オープンクエスチョンやチャンクを活用している例
決してコーチングを学んでいなくても、以下のテクニックを普段の生活において実践している人たちは多くいます。
例えば、以下のシーンに適しているでしょう。
コーチングのテクニック例
- 相手の意見を引き出すオープンクエスチョン
- 会話に緩急をつけるためのクローズドクエスチョン
- 具体化のためのチャンクダウン
- 抽象化のためのチャンクアップ
ではそれぞれ見ていきましょう。
【 会話にも優しさ 】
✅ オープンクエスチョン(OQ)にも方向性を
OQは自由に答え会話を広げるメリットがありますが
〇〇どうですか?
って聞く人がいますどうってなにが?ってなり
会話が迷宮入りする😞〇〇どういうとこが不便に感じますか?
と方向性を示すと
会話がスムーズになりますよ☺️✨— ヒロタコ@失敗談のセキララ投稿 (@hirotaco_skrrtk) May 7, 2020
コツは不器用でいいから、オープンクエスチョンするねん!
相手の返してくることを予測してさらに質問で答えれるようなこと話す。それだけ。だから少し考える。特にテキストベースの場合。
とにかく間違うとかより知識をそもそも使わないこと、文章を変えないことが問題。— トク@サブ (@j1jVkK1qWc3DDEu) May 6, 2020
人への質問かける時、オープンクエスチョンを選ぶようにしているけど
長くなりそうだと思ったらクローズドクエスチョン選ぶ
要点まとめにはさくさく進めたいしね
しかし、ついつい言いたい事を伝える時にクローズドクエスチョンに混ぜ込む時ある、それはあまり良くないなって思ってる— 磊なぎ (@kalanchoenoha) April 30, 2020
例)配管シムを作りたい
↓
配管をつかんで、部材同士を繋げて、繋がったら光らせる。
↓
1.オブジェを掴む
2.アクターのスナップ
3.条件によってのマテリアルの変更みたいにチャンクダウンしていけば必ずヒントがあります!
いまどんなものを作りたいですか?— TARK (@LideTark) December 29, 2019
行動出来ない人は
やりたい事が大きすぎる。
例えば、起業したい!って
大きすぎるチャンク(かたまり)
で見ることなく、自分が過剰に負担を感じることなく、
これなら取り組みやすいと感じられるまで
チャンクダウン(かたまりを小さくバラす)する事がポイント💡— みつき@行動力専門家 (@Mitsuki_EXIT) April 20, 2020
物事を考える時に
チャンクアップ
するのがオススメチャンクアップは
目的や理由を問い続けて
本質を探りますやる事いっぱいで
頭が混乱したら
チャンクアップで
これをする目的は何か?
と問い続けると本当の
目的がわかります本当の目的がわかれば
優先度が高いタスクを
選択し易くなります— ナカヤマケイコ@アパレル物販女子 (@H1fYulE1BKlixQ6) March 15, 2020
最後に
いかがでしたでしょうか。
コーチングの世界でよく使われるテクニックである、オープンクエスチョンは、「YES or NO」の2択で答えられない質問のことで、
一方、クローズドクエスチョンは、「YES or NO」の2択で答えられる質問のことです。
オープンクエスチョンはクローズドコミュニケーションと比較して、相手から自由な意見を引き出しやすく、議論を積み上げていくときに適した方法です。
ぜひ日々の仕事に活かしていくとよいでしょう。
このページを読んだあなたの人生が、
より豊かなものとなることを祈っております。