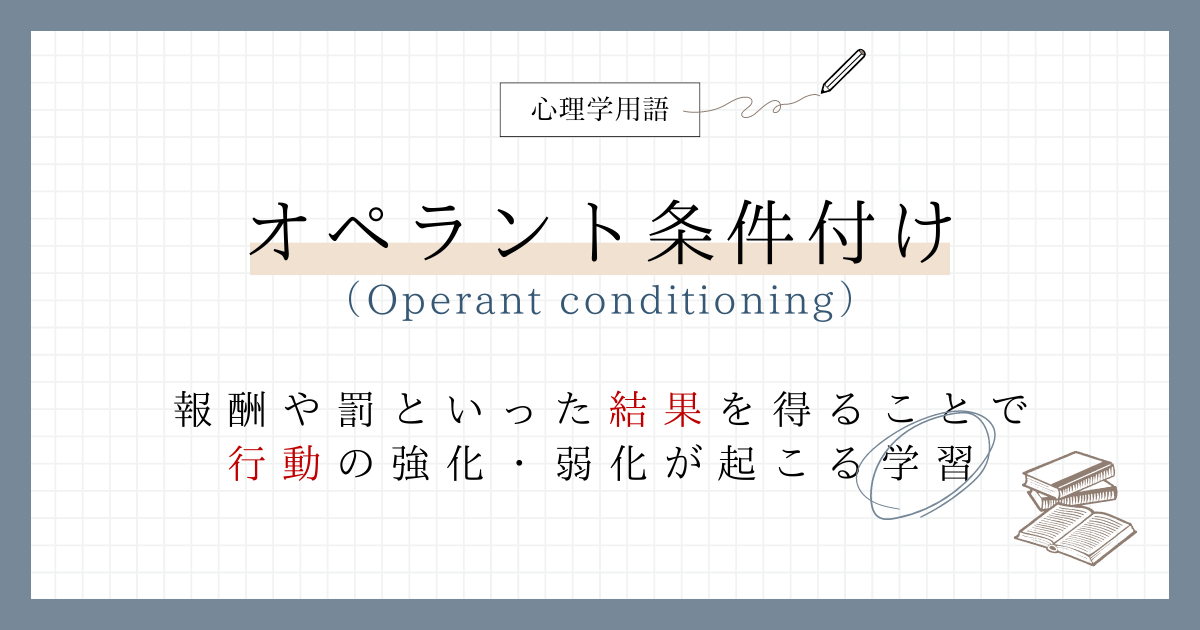オペラント条件付けとは
オペラント条件付けとは、“能動的な行動”によって得られる、報酬や罰といった”刺激”に応じて、その”能動的な行動”の強弱が変化する「学習」のことです。
- 勉強して褒められたのが嬉しくて、より勉強を頑張るようになる
- 困っている人を助けたら感謝されて嬉しかったので、困っている人を見たら助けるようになる
名前は「operate(動作する)」に由来しています。1898年に、エドワード・L・ソーンダイクが行った試行錯誤学習に関する実験にて命名されました。
オペラント条件付けの特徴
「三項随伴性」の性質を持つ
「オペラント条件付け」の学習メカニズムを見ると、行動分析学における「三項随伴性」の性質を持ち合わせていることが特徴です。
この三項随伴性とは【刺激→行動→結果】の3項目で成り立つ連鎖(関係性そのもの)のことで、それぞれの頭文字からABC分析とも呼ばれています。
- 刺激(Antecedent)
例:ブザーがなる - 行動(Behavior)
例:レバーを押す - 結果(Consequence)
例:エサが出てくる
このように「C.結果」によって「A.先行刺激」がある状態での「B.行動」に強化・弱化が起こる関係性を「随伴性がある」と言います。
そして『刺激→行動→結果』の三項で「随伴性」の性質を持っている学習を「オペラント条件付け」と言い、この時の行動を「オペラント行動」と言います。
オペラント条件付けの実証実験
オペラント条件付けの研究は、1938年に、バラス・スキナー(アメリカの心理学者・行動分析学の創始者)による「スキナー箱の実験」が有名です。
まず、ネズミを、ケージに入れました。
このケージでは、定期的にブザーが鳴るようになっており、ブザーが鳴っているときにレバーを押すと餌が出るようになっています。
そして、時間が経つうちに、たまたまネズミは「ブザーが鳴ったときにレバーを押して餌が出てくる」という経験をします。
その後、ネズミは、ブザーが鳴るとレバーを押すようになりました。
このように「エサが出てくること(結果)」を求めて「レバーを押すこと(行動)」が強化されるので、条件付け(学習)がなされた、と示されています。
オペラント条件付けの分類と具体例
ここまで紹介してきたオペラント条件付けには「結果の正/負」と「行動の強化/弱化」の組み合わせで4分類が存在しています。
| 分類 | 行動 | ||
| 強化 (増える) | 弱化 (減る) | ||
| 結果 | 正 (得る) | ①正の強化 | ②正の弱化 |
| 負 (失う) | ③負の強化 | ④負の弱化 | |
余談ですが、行動の強化を促した結果のことを「好子(こうし)」と呼び、弱化を促した結果のことを「嫌子(けんし)」と呼びます。
オペラント条件付け①
「正の強化」の具体例
結果を得る(+)ことで、行動が増えた(+)ケースです。例を見てみましょう。
- 暑い(先行刺激)
- プールで泳ぐ(行動)
- 気持ちが良い(結果)
この場合、「C.気持ち良い」という結果を得る(+)ため「正」に該当し、「A.暑い」という先行刺激を受けて「B.プールで泳ぐ」という行動が増加(+)するので、「正の強化」に該当します。
オペラント条件付け②
「正の弱化」の具体例
結果を得る(+)ことで、行動が減った(−)ケースです。別名「正の罰」とも言います。
- 犬を見る(先行刺激)
- 触る(行動)
- 吠えられて恐怖を感じる(結果)
この場合「C.恐怖」という結果を得る(+)ため「正」に該当し、「A.犬を見る」という先行刺激を受けて「B.触る」という行動は減少(−)するので、「正の弱化」に該当します。
オペラント条件付け③
「負の強化」の具体例
結果を失う(−)ことで、行動が増えた(+)ケースです。例を見てみましょう。
- かゆい(先行刺激)
- 掻く(行動)
- かゆみが減った(結果)
この場合、「C.かゆみ」を失った(−)ため「負」に該当し、「A.かゆい」という先行刺激を受けて「B.掻く」という行動は増加(+)するので、「負の強化」に該当します。
オペラント条件付け④
「負の弱化」の具体例
結果を失う(−)ことで、行動が減った(−)ケースです。別名「負の罰」とも言います。
- 嫌いな食べ物(先行刺激)
- 残す(行動)
- おやつ抜き(結果)
この場合、「C.おやつ」を失った(−)ため「負」に該当し、「A.嫌いな食べ物」という先行刺激を受けて「B.残す」という行動は減少(−)するので、「負の弱化」に該当します。
- 正の強化
結果を得て(+)、行動が増える(+) - 正の弱化(別名:正の罰)
結果を得て(+)、行動が減る(−) - 負の強化
結果を失い(−)、行動が増える(+) - 負の弱化(別名:負の罰)
結果を失い(−)、行動が減る(−)
他の条件付け理論との違い
オペラント条件付けと古典的条件付けの違い
オペラント条件付けは「行動の強/弱」に関する理論であるのに対して、古典的条件付けは「条件反射」に関する理論です。主体性の有無が異なります。
オペラント条件付け
結果に伴って、行動の強弱が起きる学習
学習前:行動→結果
学習後:行動(強化or弱化)→結果
古典的条件付け
条件刺激なしで条件反射が起こる学習
学習前:中性刺激→条件刺激→条件反射
学習後:中性刺激→(なし)→条件反射
このように、オペラント条件付けは「結果に伴い、行動の強弱が起きる学習」で、古典的条件付けは「条件刺激なしでも条件反射が起きる学習」です。
古典的条件付けとは
古典的条件付けとは、中性刺激(特に意味のない刺激)のあとに、条件刺激(何か反射を誘発する刺激)の提示を繰り返すことで、中性刺激によって反射が誘発されるようになる現象です。
例えば「梅干しを見ただけで、食べていなくても、唾液が出る」ですね。もし、スキナー箱の実験で「ブザーが鳴ると、よだれが出る」という条件付けがなされたのであれば、これも古典的条件付けに当てはまります。
2つの条件付けが併発することもある
オペラント条件付けと古典的条件付けは、同時に学習されるケースがあります。スキナー箱のネズミを例に挙げると、下記のような状況です。
- 古典的条件付け
ブザーが鳴って、唾液が出た - オペラント条件付け
ブザーが鳴った後、餌を出すために、レバーを押した
オペラント条件付けの活用方法
オペラント条件付けでは「自発的な行動の強/弱」がなされるので、良い習慣をつけたい場合、あるいは悪い習慣を改めたい場合に有効です。
一般的には、子どもやペットの教育において使われるケースが多いですね。
オペラント条件付けの活用方法①
良い習慣をつけたい
オペラント条件付けを用いることで、良い習慣を身につけることが可能です。
- 勉強する(行動)→お菓子がもらえる(結果)
- 運動する(行動)→ジュースを飲める(結果)
- 人に優しくする(行動)→褒められる(結果)
上記のいずれでも「結果」を得るために「行動」が強化されるはずです。
オペラント条件付けの活用方法②
悪い習慣を改めたい
オペラント条件付けを用いることで、悪い習慣を改めることが可能です。
- 宿題をサボる(行動)→怒られる(結果)
- イジワルする(行動)→怒られる(結果)
上記のいずれでも「結果」を得ないために「行動」が弱化されるはずです。