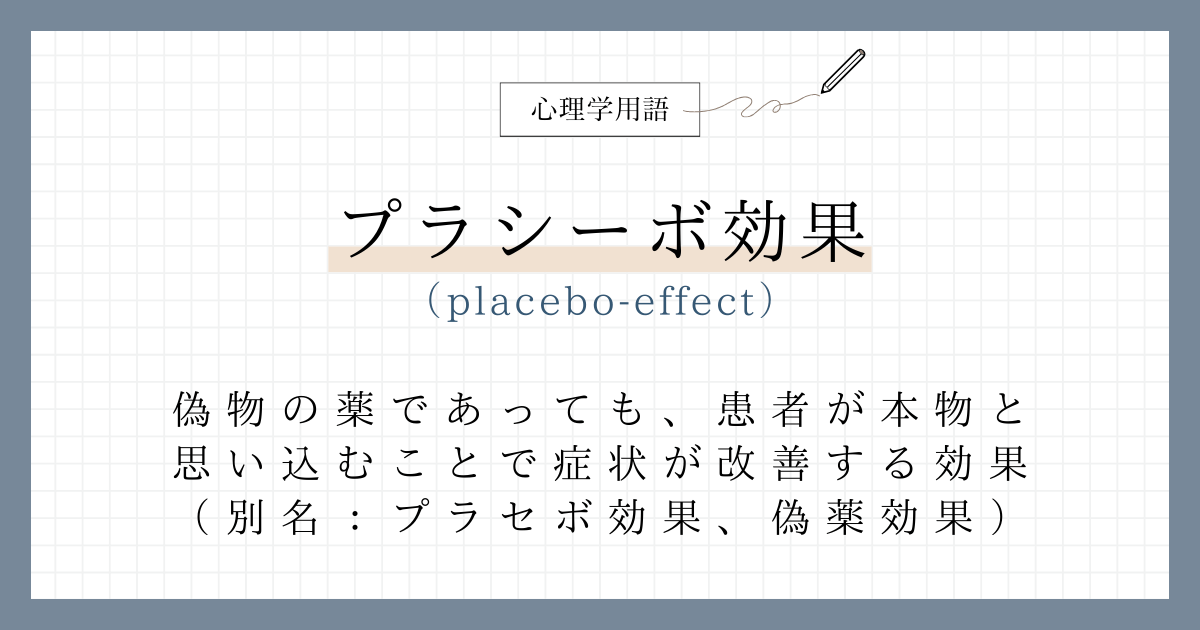プラシーボ効果とは
プラシーボ効果とは、本来は効果のない偽物の薬であっても、患者が本物と思い込むことによって、症状が緩和、改善回復したりする効果のことです。
別名「偽薬効果」とも言われ、本来は薬としての効果を持たない物質(ブドウ糖や乳糖など)を、外見だけ本物の薬のように見えるようにして販売する会社もあるくらい、大きな力を持っています。
さらに、実際には薬だけでなく、治療と思わせる手法であればその内容は問わないため、より広義で使われる用語となっています。
プラシーボの語源は偽薬

「プラシーボ(placebo)」は「偽薬」という意味の英語で、もともとは「喜ばせる」というラテン語に由来します。
一説によると、「病気で辛い思いをしている人を喜ばせて、苦痛を和らげよう」という意味が本来の語源といわれています。
昔は今ほどすぐに薬の手に入る時代ではなかったため、こういった言葉が生まれ、プラシーボ効果が発見されるに至ったのかもしれません。
プラシーボ効果の具体例
厳密にはプラシーボ効果と呼べないかもしれませんが、ある種の思い込みが心身に良い(もしくは悪い)影響を及ぼすことは大いにあります。
飲食物やサプリメント

「健康になりますように…」と期待して服用したサプリメントによって元気になる現象は、プラシーボ効果が関係している可能性があります。
それこそ、エナジードリンクや栄養ドリンク、もしくは酔い止めの類も同様だと考えられます。
さらに、「一人より大勢で食べる食事のほうが楽しい」と思っている人は、同じ料理でも、大勢で食べた方がより美味しく感じることができ、栄養の吸収効率も上がりやすいといった説もあります。
美容

サプリメントにもかかわってきますが、「自分はキレイになれる」という思い込みが実際にその人をキレイにするという俗説があります。
こちらも実証はされていませんが、プラシーボ効果に似たもので、化粧乗りがよくなったり、髪や肌ツヤがよみがえったりというプラスの効果が生まれたりするとの説もあるのです。
ヘンリー・ビーチャーによる実証実験
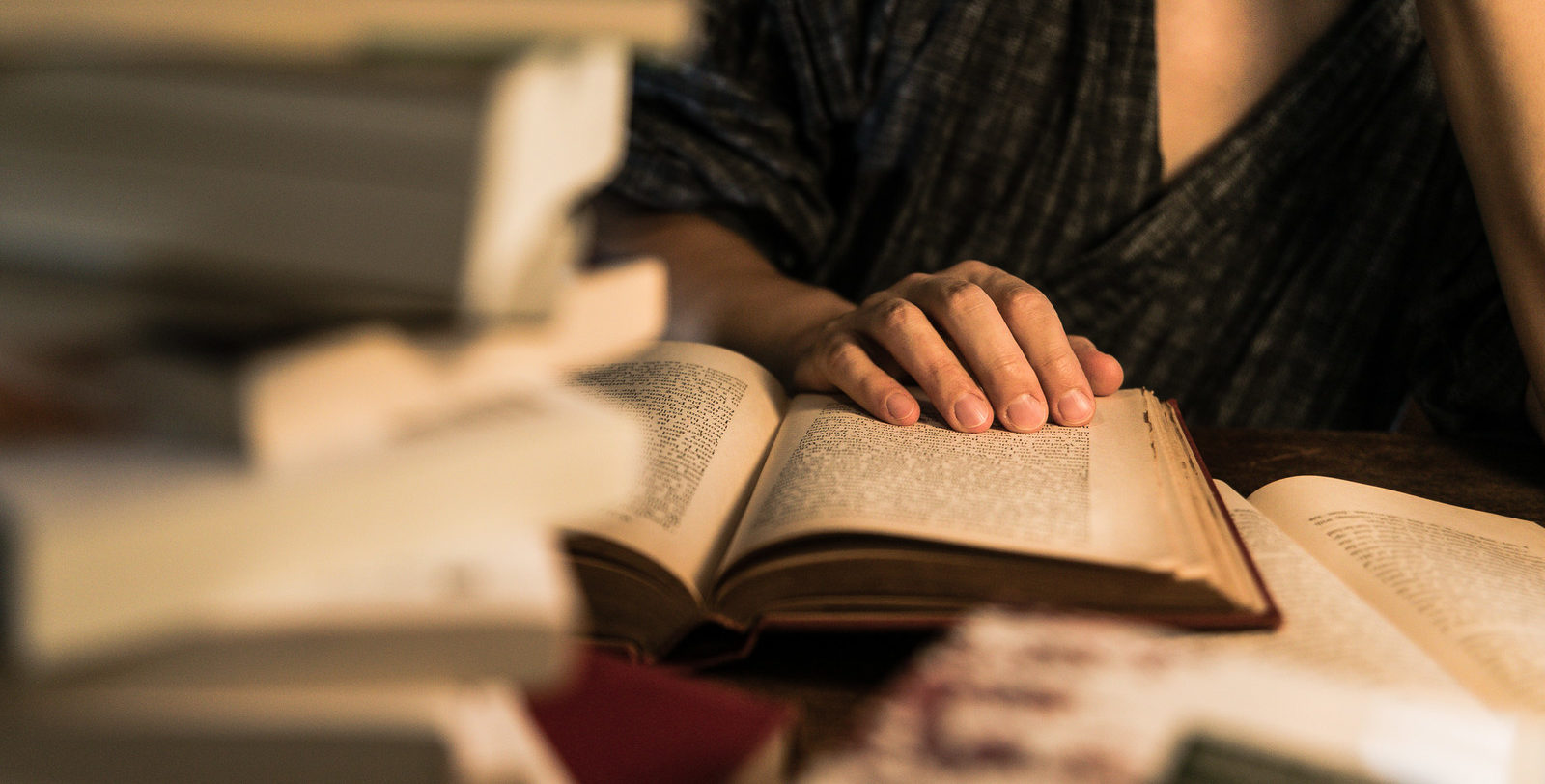
プラシーボ効果はその応用範囲の広さから多くの研究者が実験を行っていますが、最初にプラシーボ効果を提唱したのは、1955年、ハーバード大学の麻酔教授であるヘンリー・ビーチャーです。
ビーチャーは、術後の痛みを和らげる薬剤としてモルヒネと偽薬の効果比較を、患者を2つのグループに分類して行いました。
- グループAの患者
1回目はモルヒネ、2回目は偽薬を投与 - グループBの患者
1回目は偽薬、2回目はモルヒネを投与
そして下記のような結果となりました。
- グループAの患者
-
2回目の偽薬でも、鎮痛効果が見られた。
- グループBの患者
-
2回目のモルヒネで、鎮痛効果は十分見られなかった
ここから以下2つの効果が実証されました。
- グループAから実証できること
-
1回目にモルヒネを投与されて鎮痛効果を実感した人は、2回目の注射に鎮痛効果を期待してプラシーボ効果が起こった。
- グループBから実証できること
-
1回目に偽薬を投与されて鎮痛効果を実感できなかった人は、2回目にモルヒネを投与されても『マイナスのプラシーボ効果』が起こって鎮痛効果が実感できなかった。
実はプラシーボ効果のメカニズムは、現代でも科学的に実証されていない
ただ、プラシーボ効果が起こるメカニズムは、今でも科学的には実証されていません。
ピッチャーのように「プラシーボ効果は思い込みを越えて身体に作用する」と主張する研究者もいれば、逆に「プラシーボ効果にはエビデンスがない」と主張する研究者が一定数います。
というのも、ピッチャーの実験を受けて、モルヒネ以外にもさまざまな薬や手段で検証が行われたのですが、それぞれの実験によってプラシーボ効果の発生有無や程度が異なっていたためです。
プラシーボ効果と関連する用語
- 引き寄せの法則
- 病は気から
性質は引き寄せの法則に似ている
日常生活におけるプラシーボ効果は、「自分の思っているものごとを自然と引き寄せ、現実のものにする」という引き寄せの法則に似ています。
引き寄せの法則も科学的に実証されておらず、強い思い込みが自分のパフォーマンスを上下するという効果は、プロスポーツ選手などが「火事場の底力」としてしばしば経験することであり、完全に否定することも難しいものです。
そのため、自分にとってプラスになることであれば、楽観的・前向きに信じてみることで、自分の心身にとって都合よく働くのかもしれません。
病は気から
日本では「病は気から」ということわざがあります。「病気はその人の心の持ちようでいかようにも変化しうる」というものです。
また、子供が怪我をしたときなどに「いたいのいたいのとんでけ!」といった言葉をかけることもありますが、これらも科学的に実証されていないものの、ある種のプラシーボ効果であるとも考えられます。