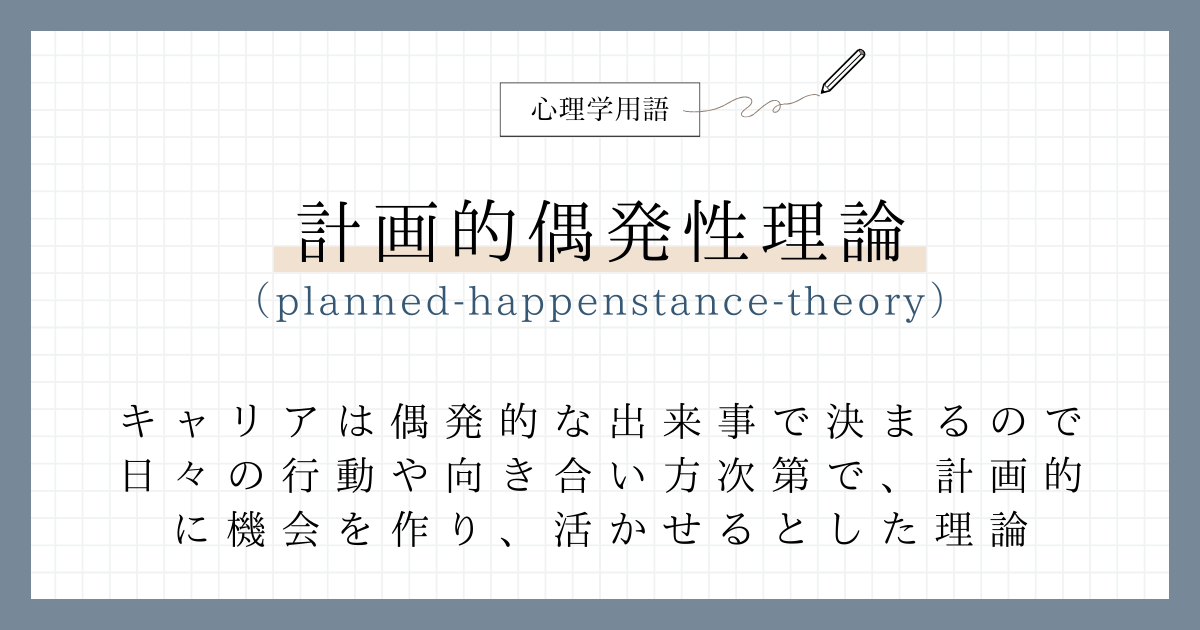計画的偶発性理論とは
計画的偶発性理論とは、キャリアは偶発的な出来事で決まるので、日々の行動や向き合い方で、計画的に機会を呼び、活かすことを説いたキャリア理論です。
1999年、キャリア論の第一人者である教育学者、米国スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ(Krumboltz, J. D)教授らによって提唱されました。(出典:Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities)
たとえ現時点で夢や目標がなくても”今を集中して生きる”ことで、いつか遠くない未来で点と点が繋がることを説いています。
キャリアは「偶発」的な出来事で8割決まる
計画された偶発性理論における「キャリアが偶発的な出来事によって決まる」というのは、偶然の出来事によって、自身の現在や中長期的な未来が決まっていくという考え方です。
例えば、以下のような例です。
通常業務とは別の突発的に振ってきた仕事に対しても「とりあえずやってみよう」と前向きに挑戦したところ、「あっ、この仕事は面白いな」と興味を持つようになった。
そして、その後も度々「あの仕事をまたやりたい」と思うようになり、その仕事をメインで進められるような部署に異動した。
このように、人のキャリアは偶然によって左右されるケースが非常に多く、「将来はこうなりたい」というなんとなくのビジョンを持っていても、実際にキャリアを決定づけていくのは、現在進行形で携わっている仕事であるほうが多かったりするのです。
下記のようなことを心がけましょう。
- 自分だけの唯一無二の仕事を見つけようと躍起にならないこと
- 先の見えない状態をあまり不安に感じないようにすること
- 選択肢を狭めすぎず、もっとオープンな状態を保っていること
- 想定外の出来事に遭遇しても、前向きに捉えて対処すること
- まずは将来より目の前のことに一つひとつ集中して取り組むこと
キャリアを決める「偶然」は「計画」的に呼び込める
計画された偶発性理論において、キャリアの8割を決める「偶発」的な出来事は、自ら計画的に行動することで呼び込めるとされています。
そして偶発性が起こりやすい行動特性は5つ。
- 好奇心 (Curiosity)
- 持続性 (Persistence)
- 柔軟性 (Flexibiliy)
- 楽観性 (Optimism)
- 冒険心 (Risk Taking)
いくつか例をあげると、
- 知らない仕事もやってみたい(好奇心)
- 新しいことに挑戦してみよう(冒険心)
- 自分の担当以外の業務も引き受けるスタンスで働こう(柔軟性)
などで、これらの行動が、偶然を計画的に呼び込むとされているのです。
未来ばかりに気を取られず、今に集中しよう
ここまで説明してきた「計画された偶発的理論」が示唆しているのは、未来にばかり気を取られず、今に集中しようということです。
事実、キャリアを描こうとすると「こうなりたい、ああなりたい」と、5年、10年先といった未来ばかり考えてしまいますが、世の中にどのような仕事があるのか、どのような未来が待っているのか、など、ほとんど読めない状態で、将来のことを決めて、今の自分を縛るのはナンセンスです。
もちろん夢がある方は、そこを目指すことになんら問題はありませんが、まだ夢や大きな目標を持っていない方であっても、無理に作る必要はありません。
昔は、キャリアに多様性がなく、キャリアパスも描きやすかった
計画された偶発的理論に重きが置かれるようになった理由のひとつに、「5年後、10年後の未来が見えない」という時代背景の変化が挙げられます。
一昔前、終身雇用制がまだ一般的だったころは、新卒で入社した会社で実績と在籍年数を積んでいくことで昇進できるという、確実なキャリアパスが描きやすいものでした。
しかし今は、そもそも今働いている企業がこの先残るのかどうかも見えない、極めて予測不可能な時代です。
そこでクランボルツ教授は、重要な意識の転換として、「あまり先のことばかり考えないで、今をしっかり生きよう」と提唱したわけです。
今まさに起こりうる、新たな人や仕事、チャンスなどの出会いを大事にすれば、自ずと未来は拓けるという、仕事だけでなく人生においても非常にポジティブな考え方だといえるでしょう。
参考:Connecting the dots(点と点を繋げる)
Connecting the dots(点と点を繋げる)とは、過去の経験が、その当時は思いもよらなかったことに未来活かせる状況を指します。
これは、スタンフォード大学の卒業式スピーチにて、スティーブ・ジョブズが取り扱ったことで大きく広まった考え方です。
Text of Steve Jobs’ Commencement address (2005) |STANFORD UNIVERSITY
自分の興味の赴くままに潜り込んだ講義で得た知識は、のちにかけがえがないものになりました。たとえば、リード大では当時、全米でおそらくもっとも優れたカリグラフの講義を受けることができました。キャンパス中に貼られているポスターや棚のラベルは手書きの美しいカリグラフで彩られていたのです。
退学を決めて必須の授業を受ける必要がなくなったので、カリグラフの講義で学ぼうと思えたのです。ひげ飾り文字を学び、文字を組み合わせた場合のスペースのあけ方も勉強しました。何がカリグラフを美しく見せる秘訣なのか会得しました。科学ではとらえきれない伝統的で芸術的な文字の世界のとりこになったのです。
もちろん当時は、これがいずれ何かの役に立つとは考えもしなかった。ところが10年後、最初のマッキントッシュを設計していたとき、カリグラフの知識が急によみがえってきたのです。そして、その知識をすべて、マックに注ぎ込みました。美しいフォントを持つ最初のコンピューターの誕生です。
もし大学であの講義がなかったら、マックには多様なフォントや字間調整機能も入っていなかったでしょう。ウィンドウズはマックをコピーしただけなので、パソコンにこうした機能が盛り込まれることもなかったでしょう。もし私が退学を決心していなかったら、あのカリグラフの講義に潜り込むことはなかったし、パソコンが現在のようなすばらしいフォントを備えることもなかった。
もちろん、当時は先々のために点と点をつなげる意識などありませんでした。しかし、いまふり返ると、将来役立つことを大学でしっかり学んでいたわけです。
繰り返しですが、将来をあらかじめ見据えて、点と点をつなぎあわせることなどできません。できるのは、後からつなぎ合わせることだけです。
だから、我々はいまやっていることがいずれ人生のどこかでつながって実を結ぶだろうと信じるしかない。運命、カルマ…、何にせよ我々は何かを信じないとやっていけないのです。私はこのやり方で後悔したことはありません。むしろ、今になって大きな差をもたらしてくれたと思います。
ここからわかるように、今を全力で生きているからこそ、次に活かせる学びに繋がりますし、過去の点と点を繋げて、一つの線を作ることができるのです。
最後に
いかがでしたでしょうか。
計画された偶発性理論(Planned Happenstance Theory)とは、「個人のキャリアの8割は、予想していなかった偶発的な出来事によって決まる」というキャリア論のことで、その偶発的な出来事は、計画性を持って「今」に集中することで、巡り会えるとされています。
夢や大きい目標を持つことが美徳と盲信されている現代において、この考え方はキャリアに悩む全ての人に理解しておいてほしい内容です。
例え、現時点で夢や目標がなくても、無理に作ろうとせず、いつか遠い未来で点と点が繋がることを信じて、常に今を全力で生きてください。
このページを読んだあなたの人生が、より豊かなものとなることを祈っております。