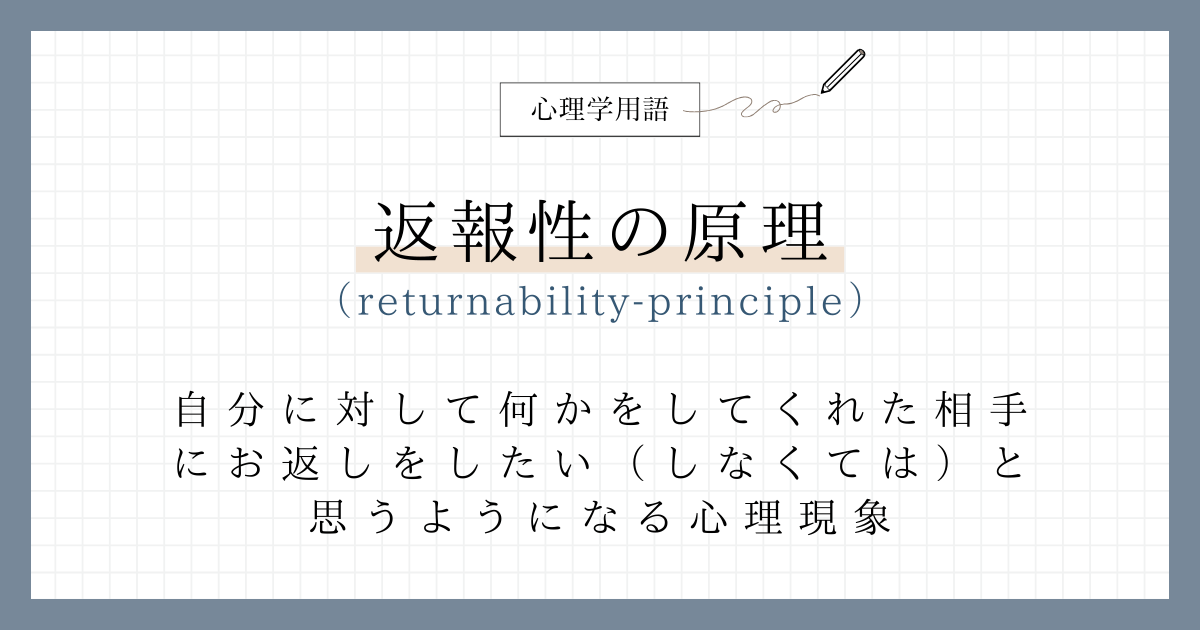返報性の原理とは
返報性の原理とは、相手が何かをしてくれたり譲歩してくれたりした際に生じる、お返しをしたい(しなければならない)と思う心理現象のことです。
4つの分類があるのでみてみましょう。
「返報性の原理」の4分類
- 好意の返報性
例:この前お土産をもらったから、私もお土産を買っていこう - 譲歩の返報性
例:500円も値引いてくれたから、買ってあげないと悪い - 自己開示の返報性
例:ここまで打ち明けてくれたから、私も隠さずに話そう - 返報性の規範
例:〇〇してもらったから、私も〇〇しないわけにはいかない
いずれも身に覚えがあるのではないでしょうか。「返報性の原理」が心理に影響を与える状況は日常的にあるので、馴染みが深い行動原理と言えるでしょう。
返報性の原理には4つ分類がある
「返報性の原理」は、主に社会心理学で使われる用語で、4つの分類があります。
「返報性の原理」の4分類
ではそれぞれ見ていきましょう。
(1) 好意の返報性とは
好意の返報性とは、他者から何らかの施しなど『好意』を受けとった際に、お礼やお返しをしたくなる心理現象のことです。
例えば、以下のようなものが好意の返報性に当てはまります。
「好意の返報性」の事例
- 以前お土産をくれた人に、お土産を買っていきたくなる
- 自社を思っての提案をしてくれる営業から買いたくなる
- 好意的な言葉を言ってくれる相手に、好意的な言葉を返したくなる
このように、自分から好意を伝えたり親切にしたりすれば、巡り巡って自分に良いことを返ってくる、というのは昔から知られていて、
日本のことわざでいうと「情けは人のためならず」が代表的でしょう。
「情けは人のためならず」は好意の返報性を意味している
「情けは人のためならず」とは、人に情けを掛けておけば、巡り巡って自分に良い結果が返って来るという意味のことわざです。
ちなみに由来は、旧五千円札の顔として知られている新渡戸稲造氏の詩の一部、「施せし情は人の為ならず おのがこゝろの慰めと知れ」から来ています。
「返報性の原理」が日常生活のなかで多く生じており、それに信頼を置いている実態があるからこそ詠まれた一節と言えるでしょう。
(2) 譲歩の返報性とは
譲歩の返報性とは、相手が譲歩してくれたら、次は自分が譲歩しなければいけない気持ちになる心理的現象のことです。
例えば、以下のようなものが譲歩の返報性に当てはまります。
「譲歩の返報性」の事例
- この商品を1,000円も値引いてくれたから、買わないと悪い
- あの仕事、本当は今すぐやって欲しいらしいけど、1日待ってくれるらしいからやらないと悪い
- 友達が本当は10万円貸して欲しいらしいけど、1万円でもいいって言ってくれてるから、貸さないと悪い
ここにあげた例のように、先に譲歩することで相手にも譲歩をさせる心理効果があり、これをテクニックとして用いることを「ドア・イン・ザ・フェイス」と言います。
(3) 自己開示の返報性とは
自己開示の返報性とは、相手が自己開示をしてくれたときに、自分も相応の秘密を開示しなければいけない気持ちになる心理現象のことです。
例えば、以下のようなものが自己開示の返報性に当てはまります。
「自己開示の返報性」の事例
- 自己紹介されたから、自分も自己紹介しよう
- 悩みを打ち明けてくれたから、自分も打ち明けよう
このように、自分が開示すれば相手も同じものを開示してくれるので、聞き出したい情報があれば、まずは自分から出してみることをお勧めします。
(4) 返報性の規範とは
返報性の規範とは、相手が何かをしてくれたのにそれにお返ししないことで、自責感を抱いたり他者や社会がそれを責めたりしてしまう現象のことです。
例えば、以下のようなものが返報性の規範に当てはまります。
「返報性の規範」の事例
- 年賀状をもらったら、返さないわけにはいかない
- 誕生日おめでとうと言われたら、ありがとうと返さなくてはいけない
- コンビニにトイレを貸してもらったから、何も買わずに出る訳にはいかない
このように、返報することが常態化すると、一種の心理的圧力を帯びるようになるので、次第に「返したくないものは受け取りたくない」とすら思うようになります。
好意の返報性とは|実証実験や事例・活用方法

好意の返報性とは、他者から何らかの施しなど『好意』を受けとった際に、お礼やお返しをしたくなる心理現象のことです。
そのため、ちょっとした相手への気遣い心遣いや投資によって、自分が意図した成果やお返しを得やすくするテクニックとしてよく使われています。
ここでは、そんな好意の返報性について詳しく解説していきます。
目次
ではそれぞれ見ていきましょう。
「好意の返報性」の実験

アメリカの心理学者デニス・リーガン博士は、仕掛け人が飲み物を買いに行き、その後で被験者に有料チケットの購入をもちかける、という実験を行いました。
被験者は2つのグループに分けられます。
デニス・リーガン博士による実験
- グループA
仕掛け人は自身の飲み物だけを買っていく - グループB
仕掛け人は自身と被験者で2人分の飲み物を買っていく
すると、仕掛け人が2人分の飲み物を買ってきたグループBでは、有料チケットの購入率がグループAの2倍にものぼったのです。
ここから、飲み物を買ってくれたという仕掛け人の好意に対して、被験者が有料チケットの購入という形でお返し行動をとった、と考えられています。
「好意の返報性」が活用されている事例
好意の返報性は、「お試し、サンプル、無料体験」として無料でサービスを提供して、お客さんに満足してもらい、購買意欲を掻き立てる営業手法としてよく使われます。
例えば、以下のようなものです。
ではそれぞれ見ていきましょう。
事例(1) コンビニエンスストアのトイレ
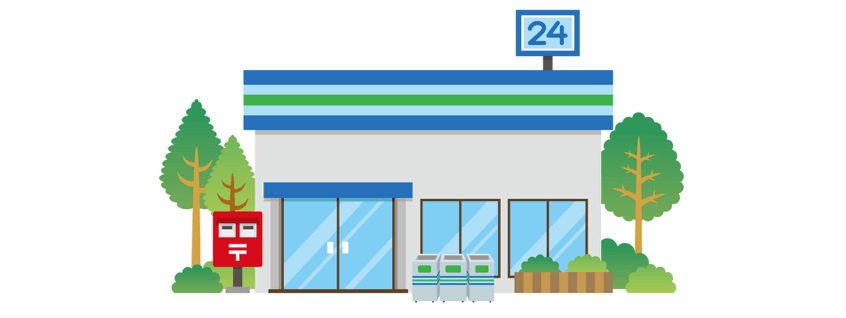
「返報性の原理」をうまくつかったマーケティング戦略の例には、コンビニエンスストアに設置されているトイレがあげられます。
実際、「トイレ借りてもいいですか?」と店員さんに聞いて、快く「どうぞ!」と貸してもらった場合、「好意の返報性」によって、何も買わずに立ち去る人はそうそういません。
というのも、利用者は”トイレを使わせてもらえて助かった”ことで、お返しとして何らかの商品を購入したくなるためです。
また、「返報性の規範」によって、トイレを借りたのに商品を買わない訳にはいかない、と感じる方も一部いるので、非常に効果的でしょう。
事例(2) 化粧品売り場での無料カウンセリング
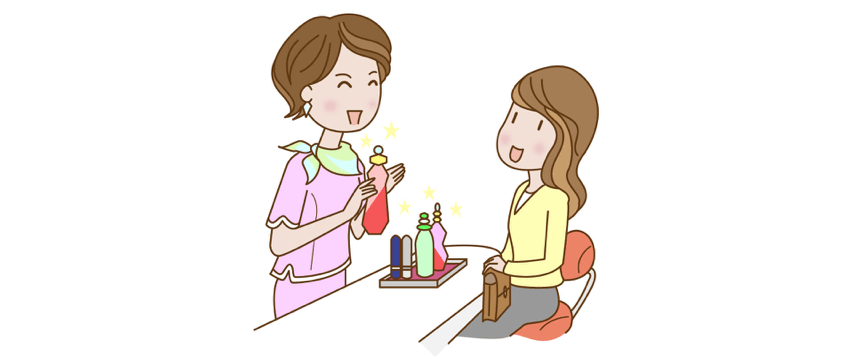
また、化粧品売り場での無料カウンセリングも「好意の返報性」を狙ったものになります。
もともとは化粧品の購入を目的に入店したわけではなくても、カウンセリング後には、そのお店で化粧品を1つ2つと購入しているケースも少なくはないでしょう。
これは、例えばお肌の悩み対策や、年齢にあった化粧品を教えてくれる、という施しを受けることによって、その内容に満足した利用者は「お返しをしたい」と思うためです。
このように、無料のうたい文句に誘されてしまうと、“タダでここまでしてもらったのだから”という心理が働き、1つ2つと商品を購入してしまうのです。
事例(3) デパートやスーパーの試食販売

デパートやスーパーでの試食販売も同じ原理です。
本来、買いに来たのは別の商品であっても、美味しそうな匂いに誘われて一口食べてしまえば、「好意の返報性」によって、ついつい購入してしまうのです。
なお、子どもが試食しようとするのを必死に止める親がいるのは、試食したからには買ってお返ししなければという思い(返報性の規範)があるためでしょう。
他にも、「好意の返報性」の原理は、試供品や無料サンプルの配布、フィットネスジムやお教室の無料体験、新聞や雑誌の無料購読などに使われています。
「好意の返報性」は好意を感じるほど強くなる

「好意の返報性」は、人は相手からの好意や善意を強く感じれば感じるほど、お返しの気持ちや行動が起こりやすくなることがわかっています。
例えば、トイレの事例を例にあげると、緊急性が高い状態でトイレを貸してもらえたときには、”助かった・助けられた”という気持ちが強く湧くことでしょう。
加えて、本来コンビニは長時間過ごす場所ではなく、トイレを設置している必然性はありませんから、より強くコンビニからの善意を汲み取ることになります。
特に、通常お客さま向けのトイレを設置していない店舗で従業員用のトイレを使わせてもらった際なども、善意が強く印象づけられます。
今となっては、コンビニにトイレがあることは常識となり、ありがたみは薄れていますが、設置率が低かった時代には、それなりの高価があったと考えられるでしょう。
「好意の返報性」で注意すべき2つのポイント
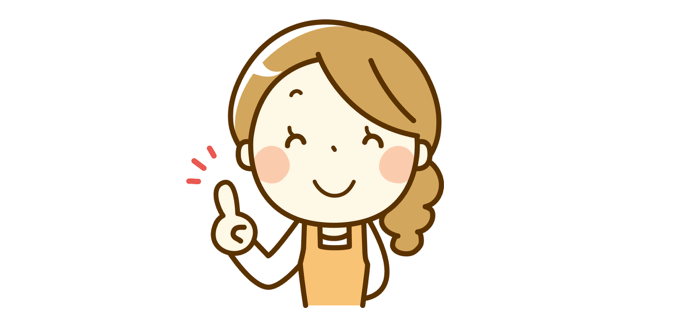
気をつけるべき点は以下の2つです。
- 注意点(1) 相手が善意と感じなければ意味がない
- 注意点(2) 過度な善意は「返報性の規範」に繋がる
ではそれぞれ見ていきましょう。
注意点(1) 相手が善意と感じなければ意味がない
「好意の返報性」を使う上で注意したいのは、受け止める側が善意を感じなければ、効果を発揮しないということです。
実際に、下心が見え見えの偽善だと、相手はそれに気がついてしまい、返すことを求められているような窮屈感を感じ、離れていってしまうでしょう。
せっかく無料で化粧品のカウンセリングをしても、あからさまに購入を勧めるトークをしたなら、消費者はそれに気づき、購入するどころかそそくさと退店しようとしてしまうかもしれません。
ときには、「こちらは値が張るので購入はおすすめしないのですが」とか、「本来こちらは無料ではお試しいただけないものなのですが」などの言葉を添えてみましょう。
注意点(2) 過度な善意は「返報性の規範」に繋がる
好意の返報性で、あまりに過度な好意を相手に送ると、「返報性の規範」に繋がりかねないので注意が必要です。
ここでいう「返報性の規範」とは、過度な好意や譲歩などによって、返報することが常態化し、一種の心理的圧力を帯びるようになることで、
いわゆる、返すことが義務のようになってしまい、”重い”と感じてしまうのです。
他の「返報性の原理」をみる
譲歩の返報性とは|実証実験や事例・活用ポイント
譲歩の返報性とは、相手が譲歩してくれたら、次は自分が譲歩しなければいけない気持ちになる心理的現象のことです。
そのため、ちょっとしたことでも相手に譲ることで、自分が意図した成果やお返しを得やすくするテクニックとしてよく使われています。
ここでは、そんな譲歩の返報性について詳しく解説していきます。
目次
ではそれぞれ見ていきましょう。
「譲歩の返報性」の実験
アメリカの心理学者ロバート・B・チャルディーニは、被験者を2つのグループにわけ、それぞれに「1日ボランティアをしてほしい」とお願いしました。
ロバート・B・チャルディーニの「譲歩の返報性」実験
- グループC
最初に3年間のボランティアを依頼し、その後「1日だけのボランティアでもいいから」と要求を引き下げる - グループD
最初から1日だけのボランティアを依頼しました。
すると、2段構えの交渉をしたグループCでは、最初から1日を提示したグループDよりも、2倍超の人が参加すると答えてくれたのです。
このように「譲歩の返報性」は、相手との交渉や説得に活かすことができます。
「譲歩の返報性」が活用されている事例
高額の商品だと一部、値引き交渉を前提している「応相談」といった値札があります。
どうせ値引きをするのであれば、最初から金額を下げた表記にしてもいいように思われますが、「譲歩の返報性」を活かすならば、やはり値引き前の値段を表記していくことが必要です。
「譲歩の返報性」では、相手が譲歩してくれればしてくれるほど、自分も相手に譲歩しなければいけない気持ちになっていきます。
「38,000円、35,000円、32,000円」と下げれば売り手の譲歩は2回ですが、「40,000円、38,000円、3,600円、35,000円、32,000円」と下げれば4回譲歩したことになります。
当初は30,000円まで値切ろうとしていた相手も、2,000円くらいは譲歩しようという気持ちになってくれる可能性が高まります。
また、値引き交渉で上司に相談するのは、相手から譲歩を引き出すために非常に有効な方法です。
なぜならば目の前の販売員だけではなく、上司まで譲歩してくれたことになるからです。
「好意の返報性」の効果が受け止める側に善意を感じてもらえるかどうかで左右されたように、「譲歩の返報性」では、相手に苦渋の決断であることを訴えかけることで効果を増大させることができます。
ですから値引き交渉では、淡々と値段を下げるのではなく、何度も電卓を叩いたり、頭を悩ませて困ったり、
「34,000円。いや、35,000円で勘弁してもらえないでしょうか」と四苦八苦する姿を見せることも大切になります。
あまり大げさにやって演技と見抜かれれば逆効果ですが、ちょっとした演出は営業努力の範疇です。
自分が要求する側に立つ場合には、ロバート・B・チャルディーニの実験のように、まず大きな要求を提示し、断られたあとに小さな要求を出すことで相手から譲歩を引き出してみましょう。
他の「返報性の原理」をみる
自己開示の返報性とは|実証実験や事例
自己開示の返報性とは、相手が自己開示をしてくれたときに、自分も相応の秘密を開示しなければいけない気持ちになる心理現象のことです。
そのため、相手からの自己開示を引き出すことがメリットになるような場面において、使われることが多いテクニックです。
ここでは、そんな自己開示の返報性について詳しく解説していきます。
ではそれぞれ見ていきましょう。
「譲歩の返報性」の実証実験
1980年代に、自己開示が「対人魅力と返報性」に与える効果を調べた実験が日本で行われています。
被験者は女子大学生90名で、研究者側の協力者(サクラ)から、内密度「高」「中」「低」の3段階に分けられた自己開示を受けたあと、アンケートに回答してもらったものです。
まず、研究者側のサクラ1名と、被験者2名の組み合わせで実験室に招き、サクラは予め決められた手順にしたがって被験者に話をしました。
そして、話を聞き終えた被験者にアンケートを渡して、自分が話し手(サクラ)に話をするとしたらどの話題を話したいかについて、12の話題から2つ選んで回答してもらいました。
なお、この12の話題は、自己開示の内密度「高」「中」「低」から選ばれていて、どの話題を選んだかによって、どの程度内密な自己開示をしたいのか、がわかるようになっています。
結果として、サクラからより内密度が高い自己開示を受けたグループは、被験者もより内密度が高い自己開示をしたいと思うことが実証されたのです。
また、以下のようなこともわかっています。
自己開示の内密度に応じた返報性の度合い
- サクラが内密度(中)で自己開示をしたとき
→相手と同じくらいの内密度で自己開示をしたくなる - サクラが内密度(高)で自己開示をしたとき
→相手より少し低い内密度で自己開示をしたくなる - サクラが内密度(低)で自己開示をしたとき
→相手より少し高い内密度で自己開示をしたくなる
このように、自分が自己開示する場合、その内密度が高ければ高いほど、相手も内密度の高い自己開示を返報してくれる傾向があるのです。
ちなみに、この実験結果からは、自分が内密度の高い自己開示を行った方が、相手が自分に対して対人的魅力を高く感じてくれる傾向があることも示唆されています。
「自己開示の返報性」が活用されている事例
ここでは、自己開示の返報性が日常で活用される事例をご紹介していきます。
ではそれぞれ見ていきましょう。
事例(1) 心理カウンセリング
心理カウンセリングでは、なかなか自分の話をしたがらないクライエントに対して、カウンセラーが自己開示をすることで言葉を引き出すような場面で用いられます。
クライエントがあまりためらわずに自分の恥ずかしい話もできるように、カウンセラーの方から先に自分の恥ずかしい失敗体験を明かすのも、同じ原理を狙ったものです。
事例(2) 部下の悩みを引き出したい
同じように、取引先や上司との関係で悩んでいそうな人がいるとき、さりげなく自分がかつて悩んだ経験などを話してみてください。
その方が相手もずっと悩みを打ち明けやすくなるでしょう。
事例(3) インタビューや取材
ビジネスの世界で相手から自己開示を引き出すことが利益になることはあまり多くありませんが、相手から言葉を引き出したいインタビューや取材などでは比較的よく用いられています。
例えば、年齢や家族構成など、相手には聞きにくいことを聞きたい場合など、まずはこちらから明かせば、相手も隠しておくことに気が引け、自分から明かしてくれるようになるでしょう。
質問せずに相手から情報を引き出す、ちょっとしたテクニックです。
他の「返報性の原理」をみる
返報性の規範とは|事例や注意点
「返報性の規範」とは、過度な好意や譲歩などによって、返報することが常態化し、一種の心理的圧力を帯びるようになることです。
つまり、返すことが義務のようになってしまうので、お互いに息苦しくなってしまうのです。
実際、「好意の返報性」や「譲歩の返報性」をテクニックとして使ったとしても、場合によって逆効果となるケースがあるので、注意しましょう。
ここでは、そんな「返報性の規範」について詳しく解説していきます。
では、解説していきます。
「返報性の規範」の事例:mixiの足跡機能

2004年に開始したSNSのmixi(ミクシィ)は若者達に当時、大流行しました。
後に利用者が減少していく一因となった「足あと」という機能は、誰がいつ自分のページにアクセスしたかを閲覧することができるというものでした。
当初は友人が自分の書いた日記を読んでくれたかどうかを「足あと」で確認できることが革新的で好評だったのですが、
次第に、「読んでいないことが知られないようにページにアクセスだけはする」という義務感にすり替わっていってしまったのです。
最近でも、LINEで相手に送ったメッセージが「既読」になるかどうかを気にする若者が増え、巷では“LINE疲れ”のような言葉も聞かれるようになってきています。
「返報性の規範」の注意:プレゼントや好意は重くならないようにしよう
そこまで相手と親しくない状態では、重い好意(例えば、気持ちの篭ったプレゼントやメッセージ)を送るのは逆効果なので避けましょう。
なぜならば、プレゼントや好意を贈る、受け取る、お礼をする、という一連の流れが繰り返され常態化すると、
受け手はお礼をすることに義務感や心理的負担感を抱くようになり、相手にお返しをできないようなものは受け取りたくない、という気持ちになるからです。
また、人はプレゼントや好意をお断りすることに強い心理的負担を感じやすいため、そもそも贈られるような機会をつくらないよう、次第に贈り手との接触を避けるようになります。
このように、「返報性の規範」がもたらす心理的な息苦しさは、素性を知る相手同士や直接対面している場面、高価な贈り物の受け渡しで特に生じやすいため、
訪問販売や対面での営業活動では、プレゼントや無料特典が常態化したり過剰になったりしないように留意する必要があるでしょう。
本来、プレゼントや無料特典は特別なものなので、「返報性」のよい効果が発揮されるよう、緩急をつけて適度に行うことが大切なのです。
他の「返報性の原理」をみる
最後に
いかがでしたでしょうか。
返報性の原理とは、相手が自分に対して何かをしてくれたり譲歩してくれたりした際に生じる、自分から相手に何かお返しをしたいと思う心理現象のことでした。
これは、好意であろうと譲歩であろうとまず最初にこちらから送ることで、相手も返してくれるという心理効果であるため、ビジネスを中心に多くの場面で利用されています。
ただ、この「返報性の原理」は本来、“何かをしてもらったら何かをしてあげたい”という博愛精神が元になっているものです。
そのため、裏が見え透いた善意は通用しませんし、過度な好意は時として、自分を相手から遠ざけることになるので、自分本位になりすぎないように注意しましょう。
このページを読んだあなたの人生が、
より豊かなものとなることを祈っております。
参考文献
- 安藤清志(1986)「対人関係における自己開示の機能」『論集(東京女子大学紀要)』,36,167-199.
- 相川充・大城トモ子・横川和章(1983).魅力と返報性に及ぼす自己開示の効果.心理学研究,54(3),200―203.
- Cialdini, R. B., Green, B. L., & Rusch, A. J. (1992) “When tactical pronouncements of change become real change: The case of reciprocal persuasion”, Journal of Personality and Social Psychology, 63, 30-40.
- Byrne, D. & Rhamey, R. (1965) “Magnitude of positive and negative reinforcements as a determinant of attraction”, Journal of Personality and Social Psychology, 2, 884-889.
- 『影響力の武器』