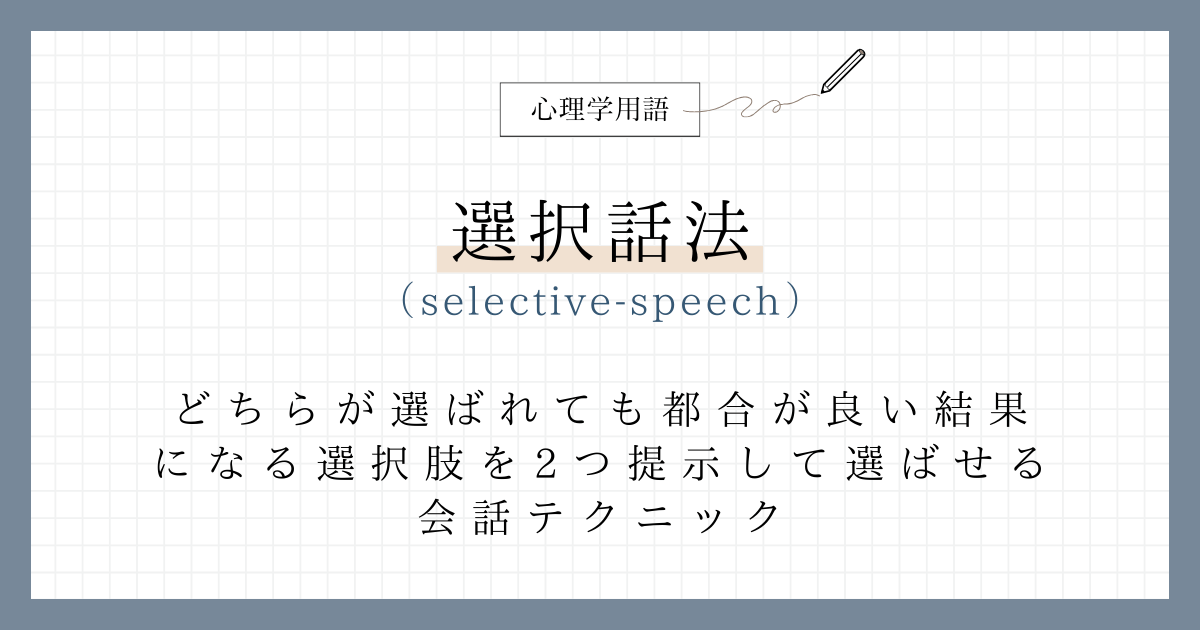選択話法(二者択一話法)とは
選択話法(二者択一話法)とは、相手に2つの選択肢を提示して、どちらが選ばれても自分の期待する結果が得られる会話テクニックです。
例えば、「商品Aと商品Bどちらを購入しますか?」といったような営業トークが挙げられます。これはABどちらを選んでも、「商品を購入すること」が前提となっており、
どちらがいいですか?と聞かれた側はつい「どっちが良いだろう?」と考えてしまうので、無意識のうちに隠された前提が刷り込まれていくのです。
そこで今回は、この選択話法について解説していきます。
「選択話法」は精神科治療でミルトン・エリクソンに用いられた「選択肢の錯覚」に由来している
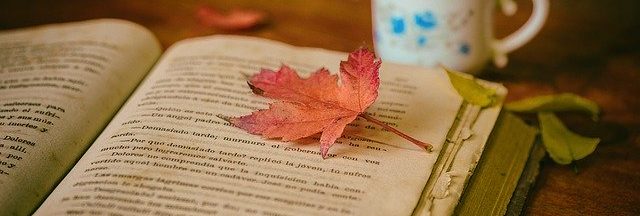
「選択話法」は、アメリカの精神科医ミルトン・エリクソン(Milton・H・Erickson、1901-1980)がの精神科治療に用いた「選択肢の錯覚」という技法に由来しています。
選択肢の錯覚とは
「選択肢の錯覚」とは、症状を消失させる治療のために、選択肢のどれを選んでも「患者の症状消失」に繋がるように工夫した問いを投げかける技法です。
質問は、以下のようなものが挙げられます。
- この症状がなくなるのは、2週間と3週間、どちらの方が現実的だと思うか?
- トランス(催眠状態)に入るなら今?それとも少し後?どちらが良いか
このように、ミルトン・エリクソンは斬新かつ変幻自在なアプローチで、次々と精神科患者の症状を消失させていったことが有名ですが、
患者に合わせて柔軟にアプローチを変えるべきと考えていたので、治療技法を体系化することはありませんでした。
そのため、この「選択肢の錯覚」という言葉が広まったきっかけは、ミルトン・エリクソンではなく、
その弟子たちが、師のテクニックを自分のものにしようと研究する過程で用いたことにあります。
注意:「選択肢の錯覚」はダブルバインド(二重拘束理論)とは違う
「選択肢の錯覚」は、2択(ダブル)で縛る(バインド)ことから「ダブル・バインド」とも呼ばれることがありましたが、
これに着想を得てグレゴリー・ベイトソンが提唱したダブルバインド(二重拘束理論;double bind theory)とは異なった理論です。
稀に、インターネットなどで、「選択肢の錯覚」と「二重拘束理論」を混同して解説している記事があるので、間違えないよう注意してください。
参考:「言葉の魔術師」と呼ばれたミルトン・エリクソン
ミルトン・エリクソンは、症状が消失することが最も優先されるべきと考えていたため、患者に症状自体やその原因を自覚させることすらさせません。
そして患者は、ミルトン・エリクソンの奇想天外な質問に答えたり、出された課題に取り組んだりしていると、よくわからないうちに症状がなくなってしまうのです。
正に煙に巻かれたような状態のまま症状がなくなるので、ミルトン・エリクソンは「言葉の魔術師」とすら呼ばれました。
ミルトン・エリクソンの「選択肢の錯覚」による治療事例
ここでは、選択話法の元となった「選択肢の錯覚」の事例を紹介していきます。
ではそれぞれ見ていきましょう。
事例(1) この症状がなくなるのは、2週間と3週間、どちらの方が現実的だと思うか?
なかなか症状がよくならないことに苛立って来院し、どうにか早く治して欲しいと訴える精神科患者に対し、ミルトン・エリクソンが放った質問です。
「あなたはこの症状が2週間でなくなるか、3週間でなくなるか、どちらの方が現実的だと思いますか?」
ミルトン・エリクソンにこう質問を返され、患者は面食らったことでしょう。
首をひねりながら、「3週間」と答えたかもしれません。
この質問で大事なのは、症状が長期間治らずにいた患者に対し、いつのまにか、“この症状はなくなるとして”という前提をつくってしまっているところです。
この“前提”が大切です。
患者は症状がよくならないと強固に訴えていたのに、この質問に答えた時点で、“この症状はなくなる”という前提をいとも簡単に受け入れてしまうのです。
弟子が出版した書籍にこの結末は書かれていませんが、ミルトン・エリクソンの術中にはまったこの患者の症状は、3週間を待たずに消失することでしょう。
事例(2) 催眠状態に入りたいのは、今と少し後、どちらか?
ミルトン・エリクソンが患者に催眠をかけようとして、以下のような言葉を投げかけました。
「あなたは、今、トランス(催眠状態)に入りたいですか? それとも、この面接の少し後の方がいいですか?」
催眠と言うと、テレビやショーで行われるような術者の意図通りに人を動かす催眠術をイメージするかもしれませんが、精神医学や心理学で使われる催眠療法は、それとは全く質が異なります。
特にミルトン・エリクソンの催眠は、その人が今までと違った考えや行動を発見できるように、
それまで持っている思考や考えの堅さを程よく緩め、治療者の言葉に対して自然かつ本能的に適切な反応を示せるような状態をつくる
ことを意味します。
ただ、多くの患者は催眠状態に入らされることに不安や恐怖を抱き、抵抗を示すので、患者が抵抗なく催眠状態に入れるように「選択肢の錯覚」を用いたものでしょう。
この質問で大事なのは、催眠に多かれ少なかれ抵抗感を抱く相手に対し、いつのまにか、“催眠状態には入るとして”という前提をつくってしまっているところです。
この結末も書籍には書かれていませんが、ミルトン・エリクソンの催眠導入は百発百中でしたから、この患者もあっけなく催眠状態に入ったことでしょう。
このように、選択肢の錯覚では、この“前提”が大切で、質問に答えた時点で提示された前提を受け入れてしまい、質問者の土俵に乗っているのです。
誰もが「選択話法」を日常的に使っている

「選択話法」は、誰もが日常の様々な場面で知らず知らずのうちに使っています。
例えば、
- ご飯を食べる?お風呂にする?
- 今日の夕食、そばとうどん、どっちがいい?
などです。いずれにしても相手が、
- いや、ひとまず横になりたい
- いや、寿司が良いかなぁ
と気軽に言えるタイプの人であれば通用はしませんが、呈示した選択肢のどちらかを選んでくれる確率はそれなりに高く見積もれるでしょう。
ただ、毎回同じような質問をしていると相手も何らかの意図に気づき、次第にこちらが呈示した選択肢以外を返答するようになってしまいます。
「選択話法」を「どちらかを選んでもらうことで、相手にNOを言わせなくする」テクニックとして使うと、できる誘導はこのくらいです。
「選択話法」は”前提”を意識すれば効果倍増
ここまで説明してきた選択話法は、“選択させること”ではなくて、“用意した前提”を気づかないうちに受け入れてもらうことを意識すると効果が上がります。
例えば、以下のような変換です。
- ご飯を食べる?お風呂にする?
→ゲームする前に、ご飯にする?そもともお風呂? - 今日の夕食、そばとうどん、どっちがいい?
→簡単に作れるものだと、そばかうどんがあるけど、どっちがいい?
といった変換で、それぞれ以下のような前提を刷り込むことができます。
- ゲームは、ご飯とお風呂の後
- 簡単に作れるものしか作らない
ただ、ポイントとしては、妙に強調するようなことはせず、もうそうすると思い込んでいるとばかりに、自然な会話の流れで話すことが大切です。
こうすることで、相手は、選ばされていることもさほど意識せず、自分で自分の行動を決めているような感覚で自然に行動してしまうのです。
「選択話法」はビジネスに活かしやすい
ビジネスでは相手にこちらの希望やセールスを受け入れてもらうことが重要になりますから、「選択話法」の使いどころには欠きません。
それぞれ説明していきます。
活用例(1) セールストークで商品を買わせたい
セールストークに選択話法を用いる場合、催眠術と違って全く買う気がない相手や、強引な勧誘などには向きませんが、
相手がいくつかの商品で迷っているとき、少なくとも“買わない”という選択肢を消す効果には期待ができます。
この場合、“今日ここで商品を買うとして”が前提になります。
「商品Aと商品Bなら、商品Aがおすすめです。
こちらは3ヶ月くらいもちますから。
それとも、短期間で効果が強い商品Bの方をお求めですか?」
—
「キャンペーンをやっていますから、商品Bなら1,000円分のポイントが返ってきますね。
対象外の商品Aは長期的なコストパフォーマンスがいいので、1年後の5月にはかえってお得になります。
こちらの方がよろしいですか?」
などです。
そして、あたかも「今日買うのが当然」と思い込んでいるように話すことがポイントです。
なお、「今ならお得」などと言うと、「今ならお得だけど、後で買えば損」という、今買わない選択肢まで意識させてしまいますから使ってはいけません。
活用例(2) アポを早めにとりたい
選択話法は、なかなかアポイントを取りにくい取引先から、約束の日時を取り付けるような場面でも使えます。
ここで刷り込む前提は、“約束はなるべく早い日時に設定できた方がいい”です。
「早ければ、来週の後半以降におうかがいできます。
次は再来週の後半になりますが、遅すぎるでしょうから、来週前半でも調整は可能です。
来週前半と後半ならば前半の方がよろしいですか?」
などと尋ねれば、多くの場合、遅くても再来週後半には約束を取り付けられるでしょう。
もし来週後半までには互いの都合がつかなかったとしても、大事なのは、“約束はなるべく早い日時に設定できた方がいい”という前提を相手に受け入れてもらうことです。
このように「選択話法」は、何らかの前提とそれに沿った選択肢さえ立てられれば、様々な場面に応用可能です。
活用例(3) 部下を動かしたい
なかなか動きが早くない部下を動かすときにも選択話法は使えます。
今後の成長を考えると、仕事の優先順位を上司がつけることは望ましくないものの、ある程度こちらがマネジメントしなければ業務に支障が出る場合、
「業務Cを終わらせるには、作業Dからはじめるか。それとも作業Eから片付けた方が効率いいだろうか?」
などと質問します。
相手は「業務Cを終わらせる」という前提を受け入れた上で、2択から優先順位を選んで作業に取り組むことでしょう。
ただし、ここで「まず業務Cを終わらせるとして」などと言ってしまうと、こちらの手の平(前提)を相手に明らかにすることになるので注意してください。
不得手なことを責めてしまうと労働意欲が下がって、かえって非効率なので、こうした表現は控えるのが得策です。
作業種類であっても自分で優先順位をつけて業務を片付けられれば、それが少しずつ自信になり、成長のきっかけにもなっていくことでしょう。
最後に
ここまで選択話法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
選択話法は、そもそもの「選択肢の錯覚」にあったエッセンス、“前提を自然に受け入れてもらう”ということを意識することによって、
相手に強引さや不快感を与えずに、自然とこちらに好ましい変化や行動をとってもらえるテクニックでした。
テクニックと言うだけあって、上手な前提と選択肢の呈示には練習が必要ですから、まずは使ってみながら磨きをかけていってください。
このページを読んだあなたの人生が、
より豊かなものとなることを祈っております。