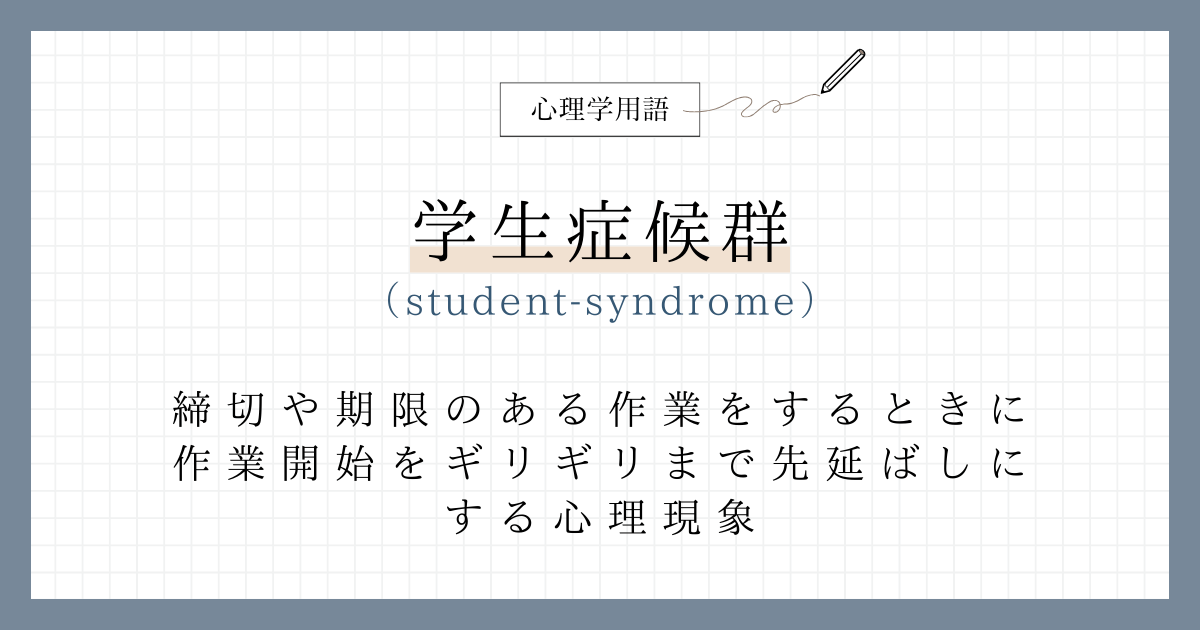学生症候群とは
「学生症候群(Student Syndrome)」とは、締め切りや期限のある作業をする際に、締め切りぎりぎりまで作業開始を先延ばしにしてしまう人間の心理を表す言葉です。
誰しも1度や2度は、以下のような経験があるのではないでしょうか。
- 夏休みの宿題に終盤まで手をつけずに放置
- 待ち合わせ時間ギリギリに身支度を開始する
- 申請期限のある書類を提出日当日になって慌てて記入し始める
- 資格取得や昇進のための試験勉強を試験日近くまで始めない
このように人は、時間に余裕があるとついつい、“もう少し後でやっても十分間に合うだろう”と甘く見込み、ゆっくり構えてしまう傾向があるのです。
学生症候群の由来は、生産スケジュール理論
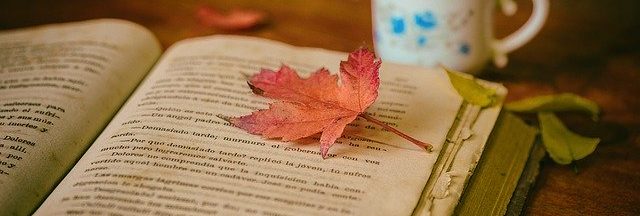
「学生症候群」は、イスラエル出身の物理学者であるエリヤフ・ゴールドラット博士(Dr. Eliyahu M. Goldratt)の著書『Critical Chain』で用いられ、広まりました。
ゴールドラット博士は、企業の収益最大化のための経営手法「生産スケジューリング理論」の提唱者でもあり、
スケジュールに十分な時間的余裕があるにも関わらず、プロジェクトが遅れる原因の1つとして、「学生症候群」を用いました。
なお、企業活動に関する理論が「学生症候群」と名づけられたのは、ゴールドラットがこの心理を説明する際に、
「期間が短いと主張して宿題の提出期限を延ばしてもらったのに、すぐに取りかからない学生」
を例にあげたことに由来しています。
「学生症候群」の悪影響
「学生症候群」が発生すると、当初は十分に時間的余裕のあるスケジュールであったのに、取りかかるのが遅れ、実際に作業する期間は短くなってしまいます。
さらに、時間的余裕のない状態で作業を行うことになりますから、ミスが起こって不良品発生率が高まったり、製品の質が低下するリスクも高くなるでしょう。
また、緊急に対応しなければならない案件が入ってきたり、突発的な事故や仕様変更などが生じたりすれば、作業期間が想定よりも長くなり、納期に間に合わなくなってしまうかもしれません。
本来はこうした突発的な事態などのリスク対応があっても納期が守られるようにスケジューリングしたはずなのに、です。
苦手、面倒なものほど先送りにしてしまう
特に、取り組むべき作業が自分の苦手な分野であったり、手がかかって面倒なものであったりすると、「学生症候群」の心理は加速します。
事実、「学生症候群」の背景には、「やりたくないな」「面倒だな」「休みたいな」という無意識的な気持ちがあることが少なくありません。
逆に、“細々としたことを先に片付けてから専念しよう”などと、時機をあたため過ぎるために「学生症候群」の状態に陥ってしまうこともあります。
「学生症候群」で納期を守れた経験があると、さらなる油断を招く
さらにやっかいなのが、「ギリギリに始めたのにも関わらず納期を守れた」という経験があると、それが悪い意味での成功体験となり、
「ギリギリに作業を始めても大丈夫だ」という妙な自信が芽生えやすいのです。
それが積み重なると、ギリギリに始めることが常態化するだけではなく、「もう少し遅く始めても間に合いそうだ」などと、ますます作業開始を遅らせる心理が働いてしまいます。
それに慣れてしまった頃に突発的な事故などが起こると、生産体制が総崩れになってしまうことすらあり得るのです。
「学生症候群」に陥りやすい人のタイプ
学生症候群に陥りやすい人は、以下のようなタイプです。
- 何でも先延ばしにしやすい
- 想定外のことが発生するリスクに無頓着
- おおざっぱなスケジューリングを立てて感覚で仕事をする
また、一気に作業を終わらせようとする短期集中型の人も注意が必要です。
というのも、会社で働いていると細かく役割を分担して少しずつ進められる場合が多いからです。
他にも、想定工数を見積もる際に、ベストコンディションでかかる作業時間で決めてしまうと、その状態で作業に取り組めなかったときには、その分だけ作業進捗が遅れてしまいます。
「学生症候群」に陥りやすい組織習慣
組織の場合には、例えば以下のような習慣を持っている場合に「学生症候群」の状態に陥りやすいと言えます。
- 工程ごとに時間的余裕を設けている
- 少し余裕をもってプロジェクト期間を設けている
これはいずれも、完成までに十分な時間的余裕があると認識しやすいからです。
また、プロジェクト(工程)の進捗ペースにベースラインのようなものがあり、進捗が遅れた場合にはそのベースラインに戻るコントロールを行っている場合もあてはまります。
「学生症候群」の日常での事例
ここでは、ビジネスの現場でありがちな「学生症候群」の事例を2つ、紹介していきます。
では見ていきましょう。
事例(1) 月末の経費締め日まで申請をしなかった事例
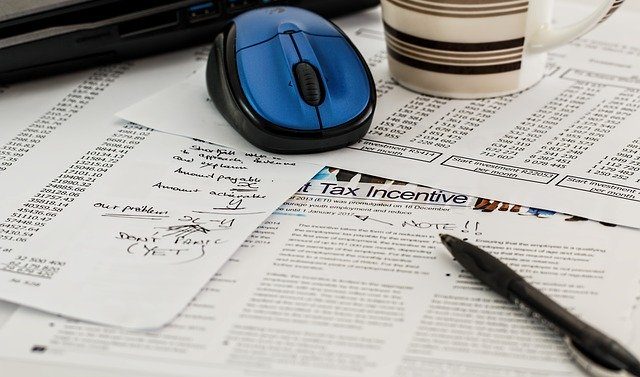
例えば、経理担当部署に提出する領収書です。
これまでも毎月、締め切り日当日に領収証を整理して間に合っていたので、その月も締め切り日当日に作業を始めました。
ところが、どうしても見つからない領収証があります。
数日前に出張に行った際の領収証は、いつもの通勤バックのなかではなく、旅行用鞄のなかに入れたままであったことを思い出します。
家に帰ればすぐに用意できるものなのに、当日に作業を始めたばかりに締め切りを守れず、担当部署に頭を下げることになってしまいました。
事例(2) 商談のプレゼンテーションギリギリに準備

これまで数ヶ月にわたって重ねてきた商談の大詰め、ついに取引先の最終責任者を相手にしたプレゼンテーションにまで漕ぎ着けることができました。
自分の昇進もかかった商談なので、ほかの細々とした業務をこなし、プレゼンテーション日直前の1週間で集中して作業することにしました。
幸い資料づくりは効率よく進み、あと2日を残し、あとは最終確認の上で上司の決裁を得るだけとなりました。
少し気むずかしいところがある上司なので、2日間かけてゆっくり資料を推敲し、前日午後に上司の決裁を得ることにしました。
ところが前日午後、上司は別件で必要となった緊急対応のために外出し、そのまま直帰することになってしまいました。
当日午前中、朝一番に上司をつかまえようと出社しましたが、当日午前も件の緊急対応で朝から社外にいて戻ってきません。
結局、捕まえることができず、確認のないままプレゼンテーションをする結果になってしまい、その後どうなったかは言うまでもないでしょう。
「学生症候群」に陥らないための対策
学生症候群に陥らないためには以下2つを意識すると良いでしょう。
では、見ていきましょう。
すぐ終わるものはすぐやってしまう

すぐできるものは、先延ばしにしないことが一番です。
小さい対応であっても、ひたすらに「完了。完了。完了。」と終わらせることだけを意識して、すぐやってしまい、記憶からも積みタスクからも消してしまうのが一番楽です。
逆に、面倒だからと放置していると、その数もたまってしまいますし、学生症候群によってギリギリまでやらなくなる可能性が高まります。
すぐ終わらないものはWBSを引こう

すぐ終わらないタスクであれば、成果物に必要な作業全体を洗い出してスケジュールを管理していく「WBS」を作成するのがおすすめです。
参考:WBSとは
WBSは、Work(作業)Breakdown(分解)Structure(構造化)の頭文字をとって名付けられたもので、成果物に対してタスクを細分化し、それぞれに納期を設けて管理する方法です。

タスク状況に遅延がないか、を細かく管理することができるので、PM(プロジェクトマネージャー)であれば知らない方はいないでしょう。
もし、工程が遅れれば計画を立て直せばいいですし、工程が早く完了したならば、次の工程やプロジェクトを前倒ししていけば良い、と非常に便利です。
このように、プロジェクトリーダーや部下を持つ人は、人や組織は「学生症候群」に陥る可能性があることを常に想定しつつ采配していくことが求められます。
また、始めと終わりだけを管理するのではなく、
- 無理もなくたるみもなく作業が行われているか
- 締め切りや完成予定日が達成確率五分五分で設定されているか
- 現在の進捗で締め切りや完成予定日の立て直しが必要かどうか
などがマネジメントのポイントとなるでしょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。
ここまで説明してきたように、「学生症候群」とは、締め切りや期限のある作業をする際に、締め切りぎりぎりまで作業開始を先延ばしにしてしまう人間の心理を表す言葉でした。
その結果、作業進捗が遅れてしまうことが多々あり、ビジネスにおけるスケジュール管理では注意しなくてはいけない現象とされています。
事前にすり合わせた納期から毎回遅れていると、組織の中でどんどん信用を失っていくので、思い当たる点がある方は、意識して改善していきましょう。
このページを読んだあなたの人生が、
より豊かなものとなることを祈っております。