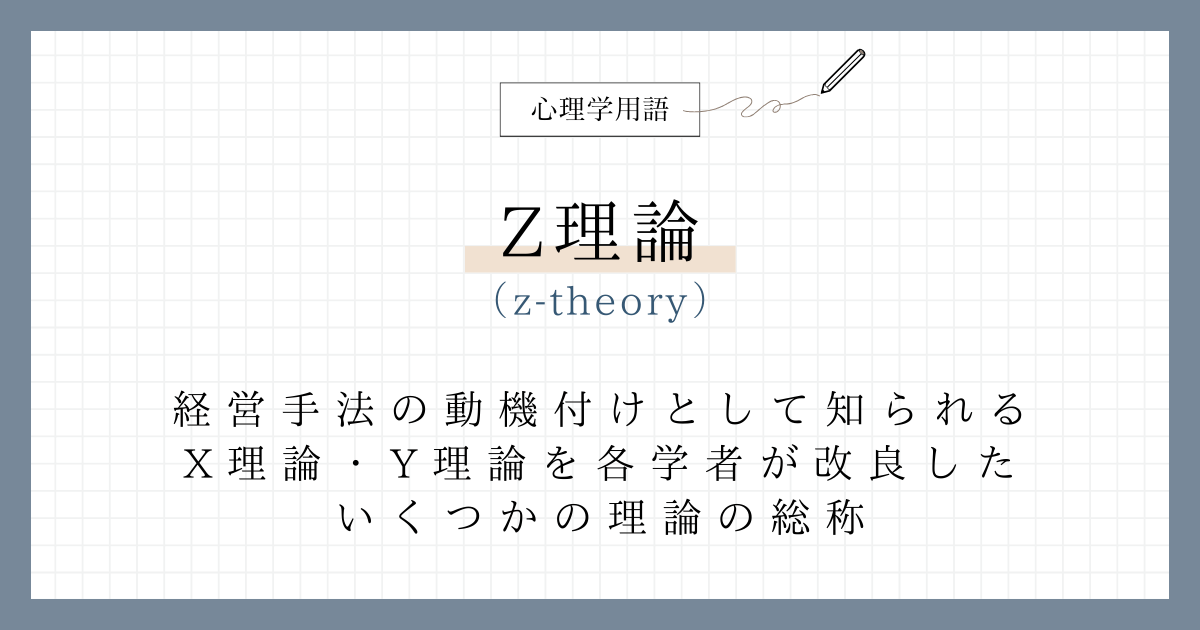Z理論とは
Z理論とは、経営手法における不完全な動機付け理論とされた「X理論・Y理論」を改良した理論の総称です。複数あるZ理論のうち、特に有名な2つを紹介します。
- アブラハム・マズローのZ理論
- ウィリアム・オオウチのZ理論
マズローのZ理論は「人間性の成長」に焦点が当たられているのに対して、オオウチのZ理論は「企業と従業員の信頼関係」に焦点が当てられています。簡単に見ていきましょう。
 運営者
運営者余談ですが、X理論・Y理論は「マズローの欲求階層説」に影響を受けているので、マズローがZ理論に興味を持つのは自然といえますね
有名なZ理論#1
アブラハム・マズローのZ理論
まず、マズローは、Y理論がうまく機能しない理由を、以下のように分析しています。
これを踏まえ、マズローは「社会環境の変化により、従業員や経営者の人間性をより高次なものに移行する必要がある」とし、Y理論を発展的に修正する方針で、Z理論を構築しました。
「経済的安定が確保されれば、その後、人は自然と価値ある人生や、創造的で生産的な職業生活を求めて努力するようになる」という考え方をしています。
つまり、Y理論に基づくような「主体的で創造的な経営」を成立させるためには、従業員も経営者も企業も経済的な安定を得ていて、欲求段階がより高次元である必要があるということです。
心理学者のマズローらしい「欲求5段階説」に基づいた理論ですが、実際の企業活動に応用する具体的な手段が明確ではないというデメリットがあります。しかし「マズローのZ理論」は人間性に頼った理論でもあったため、ビジネスの世界でそう広まることはありませんでした。
有名なZ理論#2
ウィリアム・オオウチのZ理論
1970年代にアメリカの経営学者ウィリアム・オオウチ(William Ouchi)が提唱したZ理論を紹介していきます。日系3世でもあったオオウチは、その頃目覚ましい経済的成長を遂げていた日本企業の経営に着目し、その原因を、X理論とY理論の優れたところが集まっているからだとしました。
- 当時の日本的経営
-
当時の日本的経営の特徴は、終身雇用や経験の蓄積に伴うゆっくりとした昇進など、雇用と被雇用の関係を超えた、企業内で人間を育てていく経営手法でした。
- 当時のアメリカ的経営
-
知的労働者であるホワイトカラーと、肉体労働者であるブルーカラーが明確に分かれており、指揮命令系統が明確になっています。企業内で人間を育てていくという文化は少なく、企業は必要とする能力のある人を採用する、労働者はスキルアップして自分を高く評価してくれる企業に転職していく、といった利害関係のはっきりした能力主義・個人主義的な経営手法です。
この日本的経営特有の、企業内で人間を育てて、人生まるごとお付き合いをしていく「平等で親密な雰囲気」こそが、個人を主体的に動かしていくのだろうと考えました。



おそらく、従業員が自分の利益のためではなく、会社のために自ら身を粉にしていく姿が、新鮮に映ったのでしょうね。
「日本的経営手法を備えたアメリカ的経営手法」をモデルに提唱しました。
例えば、終身雇用制によって企業が従業員を守れる体制を整えることで、企業内での経験の蓄積を重視しつつも、指揮命令系統がはっきりとしている状態です。
こうした企業では、従業員が自発的に行動し、企業の発展成長に貢献してくれるため、細かな管理監督がなくとも企業活動が適切に発展していくと考えたのです。
このように「体制の整備」という方針は、企業としても取り入れやすいため、オオウチのZ理論は、アメリカの経営改革の流れに大きな影響を与えました。
オオウチがあげた日本的経営の7つの特徴
- ゆっくりとした昇進
- ジェネラリストを育成する傾向
- 非明示的な評価
- 意思決定の基準や目標
- 稟議による重要な意思決定
- 個人ではない集団的責任
- 職場以外の人間関係の形成
なお、オオウチはこれら7つの特徴を、アメリカ企業の管理職に見せて「特徴にあてはまる社名」を答えさせたところ、IBMやHPをはじめとした有名企業の名前ばかりが挙げられたと報告されています。
しかし、当時の日本的経営が高く評価されたのは、高度経済的成長により爆発的な成長を遂げていたからにすぎません。現在の日本では、Z理論がうまく当てはまらないケースが非常に多いのです。



実際に、オオウチがあげた7つの特徴の多くは、日本企業が欧米の企業に劣る点として指摘されることも少なくありません。
Z理論の元になっているX理論とY理論
X理論・Y理論とは、米国の心理学者ダグラス・マグレガーが1960年に著『企業の人間的側面』のなかで記した、経営手法としての動機づけ理論のことです。
- X理論
-
性悪説に基づいた経営理論
- 人間を働かせるには報酬や罰が必要
- 人間は怠け者で、強制されたり命令されたりしなければ仕事をしない
- 命令されることで責任回避、安全を望む
→権限行使と命令統制を中心とした経営
- Y理論
-
性善説に基づいた経営理論
- 仕事をするのは本性で、強制は不要
- 人間は自ら進んで設定した目標に対しては自主的・積極的に働く
- 承認欲求や自己実現欲求が満たされるような目標に対しては特に動機付けが高まる
→統合と自己統制を中心とした経営
上記のように、X理論/Y理論はそれぞれ性悪説/性善説に基づく相反する理論です。どの理論に基づくかによって、経営手法が異なることが示されています。
不完全なX理論・Y理論から生まれたのがZ理論
実際の企業活動や業務は、X理論・Y理論のそれぞれが向いている業務が複雑に絡み合っており、どちらの経営手法を取り入れるべきかを選ぶことが困難であるという欠点がありました。
また、本来はY理論に向いている状況のはずなのに、Y理論だけではうまくいかない事例があり、Y理論では不十分との批判もされるようになりました。
これを受け、マグレガー自身もX理論とY理論の融合を目指しましたが、それを達成せずに生を終え、別の学者によってZ理論が成立することとなったのです。
企業経営の動機付け理論で有力な説はまだない
ここまで説明してきたように「マズローのZ理論」や「オオウチのZ理論」ですら不完全な点が多く、いずれとも理論として完全なものには至っていません。いまだに、現代の経済活動や企業経営手法に当てはまる「動機付け」研究で、有力な説は発見されていないのです。
それでも、これらの理論を学ぶことは無駄ではなく、それぞれの良し悪しがわかっていてはじめて、適切な取捨選択が可能になるものです。
実際、多くの経営者は、企業の発展状況や経済基盤、従業員の意欲、業務内容に応じて、X理論、Y理論、Z理論、セオリーZ、日本的経営、アメリカ的経営、それぞれの手法を適宜取り入れています。
重要なのは、どの理論を採用するかではありません。会社や現場の状況をよく把握し、それに応じて経営手法を変化させていける柔軟性こそが、Z理論の終着点とも言えるでしょう。