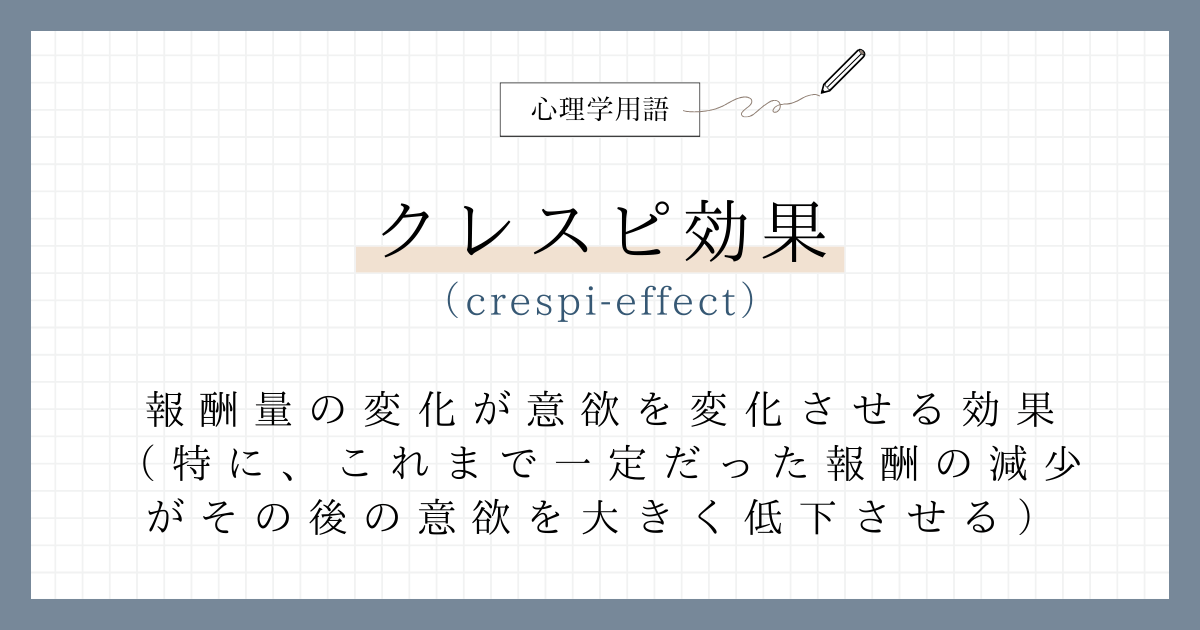クレスピ効果とは
クレスピ効果とは、報酬量の変化によって意欲が変化する心理現象のことを指しています。
特にマイナス効果である「それまで一定だった報酬が減少すると、その後の意欲が顕著に低下する」現象が非常に有名ですね。
クレスピ効果の例
これまで時給1,000円で働いていたのに、ある日突然「明日から時給990円」と言われたら、今までと変わらないモチベーションで働くことはできるでしょうか。
元々1,000円だった時給が10円減らされたので、下がった金額はわずか1%なのですが、それに伴った意欲低下が1%で済まないことは言うまでもありません。
「クレスピ効果」は1940年代アメリカの心理学者クレスピが提唱
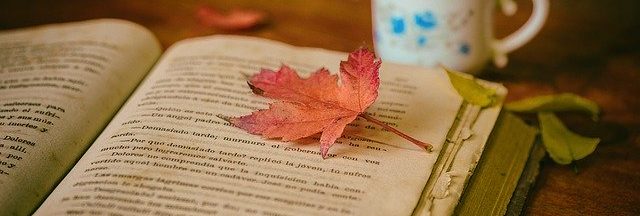
「クレスピ効果」は、1940年代に米国心理学者クレスピ(Crespi, L. P.)が発見した心理学的現象で、「動機付け(motivation)」という行動心理学の分野で使われる専門用語です。
ちなみに「動機付け」と言うとイメージしにくいですが、ここでは日常的に使われている「モチベーション」とほぼ同じ意味と理解して問題ありません。
この「動機付け」は大きく分けると以下の2つあります。
動機付けには2種類ある
- 外発的動機付け
手に入れたい外的報酬(賞罰)があり、それを得るための手段として行動をとっている状態 - 内発的動機付け
結果として得られる賞罰や成果のためではなく、それに向かっていくプロセスそのものや自身の内的報酬(充実感や自己実現)が動機付けになっている状態
「クレスピ効果」でいう報酬は、“外的報酬”のことを指すので、同じく外的報酬によって動機付けされている「外発的動機付け」と深い関連を持っています。
「クレスピ効果」の実証実験

クレスピが行った実験内容を説明していきます。
実験ではまず、条件が同じネズミを2つのグループにわけ、両グループに「ボタンを押すと、一定量の餌が出てくる」ことをオペラント条件付けによって学習させました。
そして2つのグループで、ボタンを押したときに出てくる餌の量に、以下のような差を作ります。
クレスピ効果の実験内容
- グループA
一定量の餌を与え続ける - グループB
出てくる餌の量を減らす
その結果として、もちろんグループA(餌:一定)のネズミは、状況が変わっていないので、スイッチを押す量も変わりませんが、
グループB(餌:減量)のネズミは、最初はスイッチを押す量が変わらないものの、何度か減った量の餌が出てくることを経験すると、スイッチを押す量が激減したのです。
もともとネズミにとって、餌が出ることは嬉しいことであるはずで、量が減ったからといって、もらえることは変わりません。
なにより、もっと餌が欲しいのならば、スイッチを押す量を増やせばいいはずです。
ところが、グループB(餌:減量)のネズミは、もう実験本番前のようには、スイッチに興味を示さなくなってしまうのです。
そして、1度減らした報酬をもとに戻しても、行動や意欲はもとに戻らず、もとに戻すためには、当初よりもさらに多くの報酬が必要になることがわかっています。
参考:心理学の実験ではよくネズミを使う
行動心理学の実験では、より本能的・生物的な心理傾向を把握するために、実験ではよくネズミなどの動物を使います。
人間は、理性的・知性的な機能によって行動が左右されることもありますが、本能的・生物的な傾向の方が無意識的に生じ、意識的に抗うことが難しいためです。
言い換えれば、動物を使った実験で証明された心理学的反応や現象は、私たちが気づかないうちに人間の行動や感情に大きな影響を与えている、ということになります。
そのため、動物を使った心理学的反応を知っていれば、知らない人よりも対策しやすい分、より合理的な選択に近づく可能性があると言えるでしょう。
「クレスピ効果」の事例:コロナ給付金

2020年、世界は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の脅威にさらされ、感染拡大を予防するために全国規模で緊急事態宣言が発令、日本の経済活動も大打撃を受けました。
その打撃は国民一人ひとりの財政を直撃するものであったため、日本政府は「一人当たり10万円の給付金」を配ろうとし、一斉に報じられたものです。
当時、政府や閣僚でも賛否両論があったので実現しないかもしれないとは思いつつ、多くの国民が、10万円給付金に期待を寄せ、我が家はいくら受け取れるのだろうと皮算用したことでしょう。
ところが数日後、1人あたり10万円の給付ではなく、ある基準値まで収入が落ち込んだ1世帯あたりに30万円給付、という方針が発表されました。
その結果、30万円給付の対象とならなかった国民、一律10万円給付ならば40万円以上の給付金を受け取れるはずだった世帯は落胆し、政府への不満をインターネットで発信しました。
また、各メディアの世論調査でも、条件付き世帯30万円給付への否定的意見は多数を占めたこともあり、結果として、政府は方針を再検討し、一律10万円給付が決定したのです。
当初は多くの人が期待を寄せた一律10万円給付が決まったということになるわけですが、多くの人々はもう、当初のような喜びを感じることはできませんでした。
このように、一番最初と受け取れる金額は変わらないはずなのに、一度減らされたために同じような気持ちにはなれないのです。
「クレスピ効果」は無意識に影響を受けるもの
「外的報酬」の量は、従業員の行動や意欲に大きな影響を与えますが、これは本能的・生物的な反応であるため、全ての人が無意識に影響を受けることがわかっています。
例えば、時給が1,000円から990円に減少されたとしても、とある従業員は「お店も大変だし、1%くらいどうってことない」と思っていたとしても、
気づかないうちに作業の質が低下していたり、ふとしたときに疲れを感じやすくなったりするなど、無意識で「クレスピ効果」の影響を受けるのです。
「クレスピ効果」は給料以外の外的報酬にも左右される

人事労務管理における「外的報酬」は、給料だけではありません。
例えば、
- 有休の付与日数
- 社員割引の割引率
- 支給品の有無
- ○○達成で昇進、という慣例
などがあげられます。
ただ、クレスピ効果がよく働く場面は、「いつも一定に与えられていた外的報酬」なので、もらう側も変動しやすいとわかっている賞与などによる影響は大きくはありません。
とはいえ、さきほどの一律10万円給付など、もらえることに大きく期待しているような内容だと、1度でもその影響は大きくなるので、注意が必要です。
「クレスピ効果」はマーケティングの前提知識として抑えるべき
マーケティング戦術でも、クーポン、内容量の増量、追加費用なしの付加サービスなどを、消費者にとっての「外的報酬」として用いるケースは多くあります。
これは、一時的なキャンペーンとして行っており、消費者も“今だけのお得”と認識しているので、キャンペーンがなくなったとしても、購買意欲や消費行動に大きな影響は与えません。
ところが、一時的なキャンペーンと銘打っていながらその状況が長く続いていれば、消費者はそれを“あたりまえのお得”と感じるようになってしまいます。
つまり、消費者にとっては、「クレスピ効果」が働きやすい、いつも一定に与えられていた「外的報酬」のようになってしまうということです。
そして、期間の長すぎるキャンペーンは、キャンペーンが終わった後に、急激に購買意欲や消費行動が減ってしまうリスクを負う、ということになるのです。
そのため、マーケティング戦略で“お得キャンペーン”を銘打とうとするときには、キャンペーン中に購買意欲や消費行動がどのくらい増えるかだけではなく、
キャンペーンを終えたときに購買意欲や消費行動が急激に低下する可能性についても考える必要があります。
最後に
いかがでしたでしょうか。
クレスピ効果とは、報酬量の変化によって意欲が変化する心理現象のことを指しています。
特に、「それまで一定だった報酬が減少すると、その後の意欲が顕著に低下する」現象が非常に有名で、現代において気をつけねばならないシーンが多くありました。
そのため、一定額の報酬を変更する際には、細心の注意を払う必要があるでしょう。
このページを読んだあなたの人生が、より豊かなものとなることを祈っております。
参考文献
『新・動機づけ研究の最前線』